千島や樺太に関する書物を「国立国会図書館デジタルコレクション」で探していると、思った以上に多くの点数がヒットする。いくつかの本を拾って実際に読んでみると、戦後になってからはあまり語られてこなかったロシアの脅威が記されている本が少なからずあり、その多くがGHQによって焚書にされていることが判る。
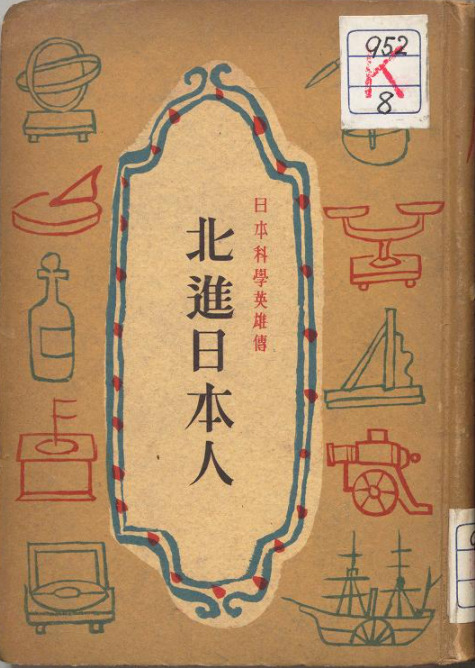
貴司山治 著『北進日本人』(GHQ焚書)という本は、昭和十七年に児童向けに書かれたものだが、ここにはこう記されている。
徳川氏が政治を司っている三百年の間、日本は固く国を閉ざしてほとんど外国と交通をしなかった。日本歴史の上ではこの時代を鎖国時代と呼んでいる。徳川氏は日本の国民が国内に閉じこもって暮らしていくことが自分の司る封建制度(大名が国を分けて治めるやり方)をいつまでも保つ上に一番都合がいいと考えたのである。たしかに鎖国によって徳川氏は三百年間続いたし、その間、日本もたしかに平和であった。
しかし日本が鎖国している三百年間に、世界は休むまもなく変化していた。ポルトガルとスペインは早くからインド洋を越えて東洋に出て来た。スペインなぞは今のフィリッピンの国を自分の領土にしてしまった。そのあとから東洋に侵入してきたオランダは南洋の島々を奪い、イギリスはインドやオーストラリアを取り、マレー半島を取ってシンガポールを建設し、支那にまでその力を及ぼしてきた。アメリカは太平洋をわがものにしてその捕鯨船は遠く支那へやってくるようになった。一方北の方を見ると、ロシアはシベリアを占領して世界無比の大きな国となり、なおあき足らないで日本の近くにまで力を伸ばしてきた。すなわちカムチャッカ半島を足場として千島のエトロフ島や国後島にまでロシア人が乗り込んできた。樺太もロシアのものにしてしまった。
黒竜江沿岸はそのころ支那の領地であったのをだんだんロシアが攻め込んでいって、ついにその領土にしてしまった。こうなると日本の北端にある蝦夷(今の北海道)も今にロシアのために奪われてしまうかも知れないのである。南からも北からも、鎖国日本はだんだん危ない状態の中へおとしいれられてしまったのだが、徳川氏は少しもそれをさとらなかった。もちろん北方の防備などのできているわけがない。蝦夷や千島はもとから日本の領土であるのにかかわらず徳川氏はこれを守ろうとも、開発しようともしないで、うちすててしまってあった。鎖国主義を取っている徳川氏は、津軽海峡を渡って蝦夷に入ることを外国に行くことのように考えて、松前氏という大名に任せたきりにしておいた。松前氏は蝦夷の本州に面した辺りだけを治めて、奥地の方はどうなっているか、だれにもさっぱり様子がわからなかった。
そうしてうちすてておいては千島や樺太はいうまでもなく、蝦夷の国も、今にロシアの領地にされてしまうことは火を見るよりもあきらかであった。
(貴司山治 著『北進日本人』春陽堂書店 昭和17年刊 p.3~6)
ロシアにそなえて北の方を守らなければならない。北の方がどうなっているかよくしらべなければならない、という考えが、はじめて日本人の間におこってきたのは、今から百四五十十年前の、明和年間のことである。
工藤平助や本田利明などは江戸時代のすぐれた地理学者であるが、こうした人たちがいち早く北方防備の急にめざめ、天明三年には工藤平助は『赤蝦夷風説考』という本を著して、日本に向かって南下してくるロシア人の様子を知らせ、蝦夷開発の大切なことを述べた。
その後、林子平が『三国通覧図説』を著し、間宮林蔵、松田伝十郎、近藤重蔵、最上徳内らが北方を探検し、多くの著作を残したことが詳しく記されているのだが、戦後はわが国の領土がロシアに奪われないように尽力した人々の話を知る機会がかなり少なくなっている。このことは、そのようなことを記した本の多くがGHQによって焚書にされたことと無関係ではないであろう。
1905年、日露戦争の後で締結されたポーツマス条約でわが国は、ロシア領の沿岸地域における漁業権が承認され、1907年には日露漁業協約が締結されて、カムチャツカ半島の沿岸や沿海州の日本海沿岸での北洋漁業が拡大していったのだが、わが国が合法的に獲得した権益がその後ソ連に犯されていくこととなる。GHQ焚書の『守れ!権益 北方の生命線』の一節を紹介したい。

見よ、ソ連の邦人漁業に加えた緊迫ぶりを!逐年、既得権益侵害行為は極めて露骨となり、かつその数も枚挙にいとまがない程多数にのぼり、最近では漁業権の行使さえ危ぶまれ、このままに放棄しておけば、北海漁場より邦人が駆逐される日も遠からぬという状態を示すにいたったのであるから、日ソ両国が、国家的尖鋭的に対立し、いまだかって見ざる最悪の瀬戸際に立つにいたった。
その間の、実情を知るものは、口に隠忍といっても、よくここまで辛抱してきたものだと驚歎する外ないのである。漁区競売の際、個人の仮面をかぶった国営企業が、入札に参加してむやみに価格をつり上げ、不当落札を企図したこと、ないしは本邦船の査証拒否、漁業員の渡航禁止から始まって漁区の一方的閉鎖要求、漁場における交通禁止、搬魚の制限、食料品の補給禁止、薬品、医療器具の持ち込み制限等々、そのいずれもが圧迫のための圧迫であり、故意に目論んだ不都合極まることのみである。
なかんずく、漁場現場におけるソ連取締官憲の不信行為は、言語に絶するものがある。例えば、ウラジオの漁業庁より、漁場地区内に井戸を掘る許可を受けて作業を開始し、いよいよ堀りあがったので、これに給水装置を施さんとしたところ、現場官吏は、井戸を掘る権利は与えているが、給水装置の許可は漁業庁から届いていないと称して工事を妨害し、すったもんだの揚句には、改めて漁業庁に許可の申請を為すべしと強要し、或いは、作業上必要な地均しの許可は承知しているが、その地上の草を刈る許可は与えていないという。
(大靖協会 編『守れ!権益北方の生命線』大靖協会 昭和14年刊 p.8~11)
こういう調子で、全く稚気に類した非常識極まる苛め方をして、とやかくとわが方の作業を妨害し、また当業者は、各漁場ごとに日誌を備えて、記入することになっているが、現場管理が点検した際、隣接した二個の漁場日誌において同日、同時刻の風速記入に一、二メートルの差のあるのを発見し、これを日誌記入不正確として調書を作成し、さらに租借漁区の地域外に於いて三、四の足跡を発見したソ連官吏は、右は無断地区外に出たものとして調書を作成した。
さらにまた、ラジオ受信の事であるが、ラジオの受信機はソ連の漁業用無税品中にちゃんと記載され、輸入は許されるが、それを使用する場合には、通信人民委員部の許可が必要であるとし、実際問題としては未だに設置できず、そのため日本からの気象通報の聴取は不可能となり、カムチャッカ方面で頻々と起こる時化(しけ)から、生命財産の危険を救うことができないという現状にある。
かかるソ連の暴状を何と見る。
かかる無法な圧迫と抗争しつつ、なおかく荒浪狂う北洋で漁業に従事し、もって国力増進に精進するわが営業者の意気、実に壮たりと雖も、何が故に、今日まで、赤裡々に国民の前に、ソ連の暴状を暴露し、国民と共にこれが排撃、政争の聖志を披歴しなかったか不思議と言わざるを得ない。
いわんや、かかるソ連の不法行為が白日の下に曝された今日、この禍根を芟除せずして何として紛争の解決を企図する事が出来よう。
戦後GHQは日本漁船の遠洋操業を禁止したが、日本が独立を回復した1952年に北方漁業の再開が決定され、1956年に日ソ漁業協定が調印され、日ソの国交も回復し、1957年から旧北洋漁業海域での操業が再開されている。しかし、北洋漁業は厳しい漁獲割当量に悩まされ、ソ連の国境警備隊やアメリカの沿岸警備隊による拿捕事件が相次ぎ、日本の北洋漁業は急速に衰退していく。
また尖閣諸島周辺では、わが国の領海に中国船が侵入するようになって久しいのだが、北洋漁業の問題にせよ尖閣の問題にせよ、わが国のマスコミは国境の危機をどれだけ報じて来たであろうか。マスコミがこれらの問題をきちんと報じていれば、国民の国防意識がたかまり、憲法改正の世論も盛り上がっていたであろうが、今のマスコミは憲法改正につながるような事件はほとんど報じようとしない。
一昔前のマスコミは中国よりもソ連・ロシアを忖度していた印象があるが、幕末以降何度もわが国に迫ってきたこの国に対する恐怖心はマスコミによって弱められてしまったと言っても過言ではない。北方領土問題がいつまでたっても良い方向に進まないのは、マスコミが逆方向に誘導していたからではないのか。。
下のリストは、「国立国会図書館デジタルコレクション」で樺太(カラフト、サガレン)、千島、北洋、北方に関してネット公開されている書籍の一部である。タイトルが太字で*が付されている本はGHQ焚書で、著者欄が太字になっているのは、著作の内に一冊でもGHQ焚書が存在することを意味している。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


【ブログ内検索】
大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。
前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。
全国どこの書店でもお取り寄せが可能です。もちろんネットでも購入ができます。
電子書籍もKindle、楽天Koboより購入できます。
またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。


コメント