著明な歴史学者のアーノルド・J・トインビー博士は、第二次大戦についてこう記している。
第二次大戦において、日本人は日本のためというよりも、むしろ戦争によって利益を得た国々のために、偉大なる歴史を残したといわねばならない。その国々とは、日本の掲げた短命な理想であった大東亜共栄圏に含まれていた国々である。日本人が歴史上に残した業績の意義は、西洋人以外の人類の面前において、アジアとアフリカを支配してきた西洋人が、過去二百年の間に考えられていたような、不敗の半神でないことを明らかに示した点にある。
(1956年10月28日/英紙「オブザーバー」)
戦前の東南アジアは、タイを除くすべての国が西洋の植民地であったのだが、日本は戦争に敗れたものの、日本軍が戦ってイギリスやフランス、オランダの勢力が排除したことに刺激を受け、戦後それぞれの国が次々と旧宗主国からの独立を果たしていった。そして、それらの国々は概して親日であり、日本に感謝する政治家や軍人の言葉は枚挙にいとまがない。
しかしながら、日本が西洋勢力を排除した後、旧宗主国と同じような統治をしていたなら、日本が敗戦した後に旧宗主国が植民地を取り返そうとした時に東南アジア諸国の人々が武器を持って立ち上がることにはならなかったであろう。
日本が統治した時代の教育と現地人からなる軍事力を創設したことによって、これらの国が相次いで独立を果たすことができたのだが、民衆に兵器を貸与して軍事訓練を行うためには、現地人と強い信頼関係が構築されることが重要であることは言うまでもないだろう。東南アジアは人種も言語も宗教も様々であり、短い期間に一つの国をまとめあげることは決して容易なことではなかったはずだ。
GHQ焚書の中には、日本が統治するにあたり現地の人々の宗教や信仰にどのような配慮をしたかということが書かれている本がある。今回は笠間杲雄 著『大東亜の回教徒』という本の一節を紹介したい。
オランダは搾取をなし、イギリスは甘言をもって諸民族を導きつつ不当の利益をおさめたが、南方の原住民たちは割合に幸福であった。南方へ行けばその現実に誰もが一応不思議に感ずるのだが、これは彼らに生活の安定と、自分に都合のいい程度の自由を与えた結果である。…しかし原住民たちには、何かもの足らぬものがあった。
もの足らぬもの、われわれ日本人は原住民が民族意識に醒めてきた現在、それを与えなければならない。それは正義と自由とを与えた上になお付加して与えなければならぬものである。即ち、東洋人の心、東洋人として日本人が持っている仁義の心、愛情である。愛情はオランダもイギリスもほとんど住民には与えてはいなかった。
愛情を与えるためには、彼らの風俗、習慣、信仰を知らねばならない。特に回教を知ることは、愛情の泉に指をひたすことである。これによって、回教民族を正しく認識できるのである。日本人の心を、彼らに知らしむると同時に、彼らの心を知る方法はこれ以外にはなく、彼らの心を端的に知ることは、ひいては共栄圏確立に拍車をかけることになるのである。
西洋人の統治政策理念は、まず行政機構、企画、体制といったものから出発するが、これは唯物的の考え方である。われわれは精神的なものから出発すべきである。俗に法三章というが、人間の心を握ることが出来れば、法律制度は三カ条で事足りるのである。
(笠間杲雄 著『大東亜の回教徒』六興商会出版部 昭和18年刊 p.106~107)
この本の大半の部分は、イスラム教の教義や歴史、信仰国の文化や習慣などについて解説されているのだが、ところどころに旧宗主国の統治について述べられているあたりが、GHQ焚書とされた原因なのだろう。
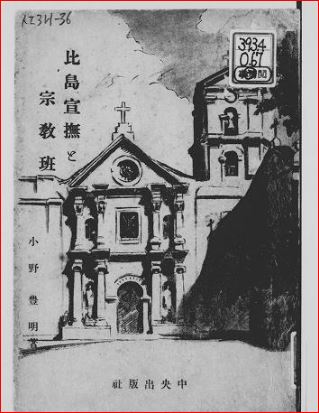
また、GHQ焚書の『比島宣撫と宗教班』には、日本カトリック教団が司教・司祭・神学生・信徒からなる宗教部隊や修道女および婦人信徒からなる女子親善部隊をカトリック教徒の多いフィリピンに派遣したことが書かれている。
今次大東亜戦争は東亜の天地から米英蘭の誅求的勢力を駆逐して各民族をしてその所を得しむるにある。したがって民衆を敵としないことは開戦と共に帝国政府が公表したところであって、また作戦上からいっても占領後一日も早く治安を回復して兵站基地としての役割を果さしめるには、民衆に対する意思疎通、即ち被占領地の民衆をして日本の真精神を十分理解せしめて日本と協力しつつ日本の指導の下に立ち上がらしめることが第一に必要なことである。このために今次作戦に於いては第一戦とともに各地域に作家、新聞記者、通訳、映画写真技師、放送技師などあらゆる方面の特殊技能者を各種要員、報道班員として従軍せしめ、この民衆に対する意思疎通に専心せしめたのである。宗教部員もまたこの一翼として従軍したのであって、上陸直後における我々の任務は「宗教を通じての意思疎通」にあったと言える。
そのためにわれわれは次に述べるような各種の方法を講じたのであるが、我々の唯一の武器は信仰である。カトリック者であるというこの一事である。カトリック教は世界の宗教であって、カトリック信者は国家民族を超えて同一の信仰を有しているのであって、この信仰という水準に於いては敵味方もない。「私は日本のカトリック司祭です。」といって手を差しのばせば、「私はフィリピンのカトリック信者です。」といって握り返すといった風に、そこに何のわだかまりもなく直ちに握手することが出来たのである。
(小野豊明 著『比島宣撫と宗教班』中央出版社 昭和20年刊 p.152~153)
今回はGHQ焚書のタイトルから、「仏教」「キリスト教」「儒教」「回教」「宗教」に関する書籍68点をリスト化を試みた。内14点が「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されているので、ネット環境があればだれでも全文を読むことができる。
| タイトル(仏教関連) | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |
| 印度仏教概説 下 | 大谷大学 編 | 法蔵館 | ||
| 皇国の三大公律と仏教 | 村井昌八 | 文明堂 | ||
| 国体と仏教 | 椎尾弁匡 | 東文堂書店 | ||
| 国体の信仰と仏教 仏教哲理の再認識 | 稲津紀三 | 大東出版社 | ||
| 国体明徴と仏教 | 利井与隆 | 一味出版部 | ||
| 国家と仏教 | 東京帝国大学 仏教青年会 | 日本青少年 教育会出版 | ||
| 真宗の護国性 | 普賢大円 | 明治書院 | ||
| 真宗の護国性 | 梅原眞隆 | 本願寺新報社 | ||
| 新東亜の建設と仏教 | 仏教連合会編 | 仏教連合会 | ||
| 人類の待望と 日本誕生の仏立宗教 | 梶本清純 | 仏立社 | ||
| 大乗仏教と日本精神 | 関 精拙 | 槻道書院 | ||
| 時宗新論 | 鈴木隆 | 高千穂書房 | ||
| 南方共栄圏の仏教 | 長井真琴 | 前野書店 | ||
| 南方共栄圏の仏教事情 | 中島莞爾 | 甲子社書房 | ||
| 南方仏教の様態 | 竜山章真 | 弘文堂 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1040278 | 昭和17 |
| 日本精神と仏教 | 高神覚昇 | 第一書房 | ||
| 日本精神の教育 非常時と日本精神と仏教思想 | 日高進 講述 | 第一人間道場 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1270620 | 昭和11 |
| 日本精神文献叢書 第11巻 仏教篇上 | 横尾弁匡 編 | 大東出版社 | ||
| 日本精神文献叢書 第12巻 仏教篇下 | 横尾弁匡 編 | 大東出版社 | ||
| 日本仏教 | 日本文化研究会編 | 東洋書院 | ||
| 日本仏教概論 | 大阪毎日新聞社編 | 一生堂書店 | ||
| 日本仏教の性格 | 梅原真隆 | 全人社 | ||
| 日本文化と仏教の使命 | 伊藤円定 | 日本禅書刊行会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021589 | 大正14 |
| 仏教の戦争観 | 林屋友次郎 島影盟 | 大東出版社 | ||
| 水戸学と仏教 | 布目唯信 | 興教書院 | ||
| 躍進日本と新大乗仏教 | 古川雄吾 | 中央仏教者 | ||
| わが国体より見たる 仏教の是非とその実相 | 服部宗明 | 神燎会 |
| タイトル(キリスト教関連) | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |
| 皇国神学の基礎原理 | 佐藤定吉 | 皇国基督会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1091708 | 昭和15 |
| 皇国日本の信仰 | 佐藤定吉 | イエスの僕会 | ||
| 国体と基督教 | 大谷美隆 | 基督教出版社 | ||
| 日本精神と基督教 | 藤原藤男 | ともしび社 | ||
| 不法の秘密 反基督の印章 | エス・テレス | 破邪顕正社 | ||
| 満州帝国とカトリック教 | 田口芳五郎 | カトリック中央出版部 |
| タイトル(儒教) | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |
| 儒教と国学 | 斎藤 毅 | 春陽堂 | ||
| 儒教と我が国の徳教 | 諸橋徹次 | 目黒書店 | ||
| 儒道報国時局大講演集. 第1輯 | 浜野知三郎 編 | 斯文会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1105803 | 昭和13 |
| 日本精神と儒教 | 諸橋轍次 | 帝国漢学普及会 | ||
| 日本精神文献叢書 第10巻 儒教篇下 | 山口察常 編 | 大東出版社 |
| タイトル(イスラム教) | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |
| 印度の回教徒 | 小川亮作 | 地人書館 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1040057 | 昭和18 |
| 概観回教圏 | 回教圏研究所 編 | 誠文堂新光社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1444937 | 昭和17 |
| 回教の歴史と現状 | 加藤 久 | 大阪屋号書店 | ||
| 回教民族運動史 | 陳 捷 | 照文館 | ||
| 大東亜回教発展史 | 櫻井 匡 | 三省堂 | ||
| 大東亜の回教徒 | 笠間杲雄 | 六興商会出版部 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1040049 | 昭和18 |
| 日本精神と回教 | 原 正男 | 誠美書閣 |
| タイトル (宗教) | 著者・編者 | 出版社 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL | 出版年 |
| アメリカの生産宗教 | 中村元督 編 | 日本興業倶楽部 | ||
| 広釈皇国の神と宗教 | 木津無庵 | 破塵閣 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1039902 | 昭和16 |
| 皇道と宗教 | 山岡瑞円 | 銀行信託社 | ||
| 国体本位の宗教教育 | 中根環堂 | 如是社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1089730 | 昭和13 |
| 国家の宗教的性格 | 宇野円空 | 日本文化協会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1207873 | 昭和11 |
| 宗教新体制草案 | 加藤一夫編 | 甲子社書房 | ||
| 宗教新体制への進路 | 岡本龍器 | 興教書院 | ||
| 宗教団体法釈義 | 市川三郎 | 宗教制度研究会 | ||
| 宗教における日本精神の探求 | 松倉菫直 | 風俗社 | ||
| 宗教日本 | 鶴藤幾太 | 教育研究会 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1039914 | 昭和18 |
| 宗教報国 | 大原性実 | 永田文昌堂 | ||
| 日本宗教 | 江原小弥太 | 千倉書房 | ||
| 戦争と宗教 | 高橋正雄 | 金光教徒社 | ||
| 大東亜建設と宗教 | 戦時中央委員会編 | 東京開誠館 | ||
| 大東亜戦争の宗教的構想 | 湯浅興三 | 警醒社 | ||
| 大東亜の民族と宗教 | 東京帝国大学 仏教青年会 | 東京帝国大学 仏教青年会 | ||
| 超宗教国体論 天皇信仰 | 遠藤友四郎 | 先進社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1175979 | 昭和6 |
| ナチスの宗教 | 丸川仁夫 | アルス | ||
| 南方圏の宗教 | 仏教研究会 編 | 大東出版社 | ||
| 南方宗教事情とその諸問題 | 大日仏教会 編 | 東京開成館 | ||
| 日本宗教 | 江原小弥太 | 千倉書房 | ||
| 日本宗教全史 第一巻 | 比屋根安定 | 教文館 | ||
| 比島宣撫と宗教班 | 小野豊明 | 中央出版社 | https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1460337 | 昭和20 |
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。
通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。
読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。
無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。
電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。
Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。





コメント