「安政五カ国条約」のアヘン輸入禁止条項で救われた日本
前回の「歴史ノート」の記事の最後に、わが国が安政五年(1858年)六月にアメリカと締結した日米修好通商条約の第四条にはアヘン輸入の禁止が書かれていたことを書いた。
この条約の全文テキストは、政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所のデータベース「世界と日本」に収められていて、第四条は輸出・輸入品に対する関税に関する取り決めが書かれている。その中にアヘン輸入禁止に関する条項があるのだが、原文では以下のようになっている。
「阿片之輸入厳禁たり 若し亜墨利加商船三斤以上を持渡らは 其過量の品は日本役人是を取上へし」
意訳すると「アヘンの輸入は厳禁、もし米国人が三斤(約1.8kg)以上所持していれば、それを超えるアヘンは取上げる」という内容である。

戦後の歴史書ではほとんど無視されているこの条項は、重要でないから省略されているとは思えない。この条項があることで、わが国がインドや中国のようにならなかったとも言えるものなのである。安政五カ国条約は最初に締結した日米修好通商条約内容がベースとなったので、他の四ヵ国についてもアヘン輸入禁止条項が存在した。そして、この条項によりアヘンの輸入を水際で防ぐことが出来た事件が明治初期に存在する。
GHQにより没収・焚書された菊池寛の『大衆明治史』の本の一節を紹介しよう。
西南戦役後、外務卿寺島宗則は条約改正に乗り出し、まず税権の改正について、米国との間に了解ができたが、英国公使の真っ向な反対を受け、せっかく調印した日米条約もフイになってしまった。
この頃、たまたまわが税管吏が英人の阿片の密輸入を発見し、これを英国領事に引渡し、その処罰を求めたことがあるが、領事はこれに対して無罪を宣告したことがあった。もしこの時、政府にかの林則徐のような硬骨漢がいたら、あるいは第二の阿片戦争が起こったかも知れないが、この事件はうやむやの中に葬り去られたのである。しかし国論はそのままでは収まらず、囂々(ごうごう)として政府の処置を難じ、自由民権論者は、国会が開設されぬから、こんな屈辱的条約に甘んぜねばならぬのだと、攻撃してやまなかった。寺島も遂にこのために辞職のやむなきに至り、この頃から条約改正は、時の政府の命取りとなったのである。
( 菊池寛の『大衆明治史』 p.142-143)
この事件は「ハートレー事件」と名付けられ、Wikipediaにこう解説されている。
1877年(明治10年)12月、横浜の外国人居留地に住んでいたイギリス商人ジョン・ハートレー(John Hartley)が生アヘン20ポンド(約9.072キログラム)を「染物」と称して密輸しようとして、税関に見つかり、税関長は神奈川のイギリス領事館に対し、ハートレーを日英修好通商条約(安政の五カ国条約のうちのひとつ)に附属する「貿易章程」違反のかどで訴えた。しかし、翌1878年(明治11年)2月、において、生アヘンを薬用に供するためであると強弁するハートレーに対し、領事裁判法廷は無罪の判決を言い渡し、関連法令にも違反していないとの判断を示した。アヘンは日英条約附属「貿易章程」第二則では輸入禁制品とされていたが、領事裁判法廷はイギリスの法令には違反していないとしたのである。
Wikipedia 「ハートレー事件」
このハートレーという商人は、事件が発覚した翌月にも再び吸煙アヘン12斤を密輸しようとしたという。明治政府は外交交渉で解決を図ろうとするも、この事件は迷宮入りしてしまったのだが、このようにわが国にアヘンを持ち込もうとしたイギリス商人が明治初期に実在していたことは極めて重要である。もし安政の五カ国条約にアヘン輸入禁止条項がなければ容易にアヘンがわが国にも持ち込まれていたことであろうし、あとで禁止条項が付け加えられても清国のように官僚が腐敗していたら密輸によりアヘンが広められて、わが国もインドや中国のように大問題となっていた可能性があったのである。
Wikipediaには、次のように解説されている。
この事件はコレラの検疫に関係する翌年のヘスペリア号事件とともに、法権の回復がなければ国家の威信も保たれず、国民の安全や生命も守ることのできないことを国民が知ることになる契機となり、列強の治外法権に対して条約改正を求めるため、鹿鳴館外交や欧化政策が進められる端緒ともなった。
同上
教科書などでは、条約改正の世論が盛り上がった有名な事件として明治十九年(1886年)のノルマントン号事件だけが書かれているが、よくよく考えるとノルマントン号事件は国会開設の詔(明治十四年:1881年)から五年も後に起きた話であり、条約改正の世論を盛り上げさせるような大きな事件が、国会開設の詔以前にいくつか存在しなければリアリティがないのである。
明治十二年(1879年)に起きたヘスペリア号事件というのは、中国でコレラが大流行して検疫体制を敷いていたわが国に、ドイツ船ヘスペリア号が、わが国の検疫要請を無視して中国から神戸港経由横浜港に入港を強行した事件である。この事件の起きた年にはわが国にもコレラが大流行し死者が十万四千人も出たのだが、ハートレー事件があった翌年にこの事件があったことに国民の多くが危機感を抱き、条約改正を望む声が一気に拡大して民権運動が興隆して国会開設につながっていった流れなのだが、奇妙なことに戦後の歴史叙述には、条約改正の世論が高まるきっかけとなったこの二つの事件について、ほとんど触れられることがないのである。
条約締結交渉時に日本側にアヘンの害毒についてどの程度の知識があったのか
話を日米修好通商条約に戻そう。この条約交渉のためにアメリカのタウンゼント・ハリスがサン・ジャシント号にて下田に到着したのは安政三年(1856年)七月二十一日のことだが、その少し前の七月十日付で記された長崎奉行から江戸幕府に宛てた書状が、徳富蘇峰の『近世日本国民史. 第35 公武合体篇』に紹介されている。
内容を簡単に紹介すると、オランダ商館長からの情報では、イギリスをはじめ各国が通商条約を締結する目的で日本に使節を送る動きがあり、もし日本がこれを拒めば、これまで対日貿易を独占してきたオランダがそれを妨害したと受け取られてしまうので、オランダとしては手が出せない。このような情勢下では日本の開国はもはや避けがたく、この際オランダが紹介する形で諸外国と交易を開始することが望ましいと記されている。
次いでオランダ領事キュルチュスから長崎奉行に宛てた七月二十三日付の長文の書翰には、日本が世界の趨勢に順応して速やかに開国することを勧めたうえ、交渉にあたっての留意点までが細かく記されているのだが、そこにはアヘンに関する言及はない。
しかしながら幕府は、オランダからは二百年以上前から様々なレポートを定期的に入手していた。オランダ商館長は寛永十八年(1641年) 以降、ポルトガルやスペインの動向などを記した「オランダ風説書」を幕府に提出していたのだが、アヘン戦争以降は世界の情勢を知らせるためにバタヴィアの植民地政庁で作成された「別段風説書」が邦訳されて幕府に提出されており、それによって幕府は西洋各国の情勢についてかなり詳しく知ることができたのである。アヘン戦争以降の「別段風説書」(1840~1845年)の原文と訳文は次のURLで読むことが可能だ。。
江戸幕府がオランダなどから得た情報に驚愕したことは確実だ。それまで幕府は異国の船は見つけ次第砲撃するという異国船打払令を出すなど強硬方針であったのだが、天保十三年(1842年)には方針を転換し、異国船に薪や水の便宜を図る薪水供与令を打ち出している。
しかしながら、アヘン戦争や世界の情報が入手できても、具体的にどのような通商条約を結べばよいかについての情報は乏しかった。その点、わが国にとっては最初の交渉相手がアメリカのタウンゼント・ハリスであったことは幸運であったと言える。
タウンゼント・ハリスの提案
下田に到着していたハリスは大統領親書の提出のために早期の江戸出府を望んでいたが、水戸の徳川斉昭ら攘夷論者が反対などがありなかなか実現せず、ようやく安政四年(1857)十月二十一日に江戸城に登城し、十三代将軍徳川家定に謁見して親書を読み上げている。

翌日ハリスは老中首座であった堀田正睦に会合を開くことを要望し、十月二十六日に堀田邸で開かれた会合で二時間を超える演説を行った。その時の会見筆記が残されており、徳富蘇峰の『近世日本国民史. 第36 朝幕背離緒篇』に引用されている。面白いのは、ハリスがイギリスの野望について語っている部分である。原文の読み下しは同書のp411~442に解説とともに出ている。
ハリスの発言を要約すると、
「五十年来、蒸気船や通信機などの発明により世界は狭くなり、諸国の交易が盛んになって、各国とも豊かになった。
その結果、各国は互いに使節を駐在させて親睦を図るようになり、自由貿易を当然と考えるようになった。
しかしイギリスは、ロシアが東洋で南下することを恐れている。植民地である東インドを守るために、樺太と北海道の箱館を占領して軍隊を置くことを考えており、そのため、日本と戦争を起こす機会を伺っているようだ。
イギリスはアヘンの事で清国と戦争(アヘン戦争)を起こし、そして今また英仏と清国との間に戦争(アロー号戦争)が起こっている。
イギリスと清国との戦争の根本原因はアヘンにあるが、イギリスはアヘンが有害であることを知りながら儲かるアヘン販売を止める意思はなく、日本においてもアヘンを売る希望を持っている。アメリカはそのことを心配している。
イギリスは清国との戦争が続いているが、戦争に目途がつけば五十隻の軍艦で日本に向かってくる。フランスも同様に日本に向かうだろう。そのような国と交渉するよりも、領土的野心を持たないアメリカと通商条約を結ぶ方が良策ではないか。」
ハリスの演説は幕閣にはかなり衝撃的なものであった。内容には誇張もあり事実相違もあったのだが、ハリスが自国の事だけでなく日本のことも良く考えて発言しているとの印象を与えることに成功したのである。
老中首座であった堀田正睦は下田奉行井上清直、目付岩瀬忠震を全権として十二月十一日から条約交渉を開始させ、その後交渉は十五回にも及んで双方の合意が得られるところまできた。しかし堀田正睦は幕府が独断で決めるという形をとりたくなかったので、孝明天皇の勅許を得て世論を納得させた上で通商条約を締結しようとした。ところが攘夷派の公家が抵抗したため、安政五年(1858年)三月二十日に孝明天皇は正式に勅許を拒否している。
一方のハリスは、清国との戦争が終結してイギリスとフランスの艦隊が襲来する前にアメリカと条約を結ぶことを強く勧め、幕閣の大勢もそれを支持するようになり、天皇の勅許がないまま日米修好通商条約は調印されることになったのである。
タウンゼント・ハリスとの通商交渉の意味
条約交渉と言っても、どのような条約を結べば良いか皆目わからない時代であった。このような時代に、最初に交渉した相手がハリスであったことはわが国にとっては幸運なことであったという見方がある。
今野幸助 著『太平洋は叫ぶ』も戦後GHQによって焚書処分された本だが、著者はハリスとの通商交渉について以下のように評価している。
このハリスの渡来が、これより五年遅れていたならば、…日本の門戸はシナ侵略(1860年の北京条約)を終えたイギリスの手によってなされ、日本が如何なる相貌を呈したであろうか。後の鹿児島砲撃、下関砲撃に於ける英国の態度をもってみて、ある種の戦慄を感ぜずにはいられないのである。
彼はまたアヘン輸入の禁制を布くことをも忠告した。この剴切(がいせつ:適切)な国際情勢の説明、通商条約へのやむなき道をも説示したハリスの勧説は、比較的西洋事情に明るかった堀田閣老によって非常な興味と注意とをもって聴かれたし、またハリスの誠意と熱情はその言辞態度の上に表れもしていたので、閣老は十分、将軍にその意を伝え、考慮すべき由を告げ深くその好意を謝してこの二時間にわたる会見は終えたのであった。
ハリスの演説によって覚醒された徳川幕府は、その後土岐丹後守、川路聖謨、井上信濃守、岩瀬肥後守などの外国掛をして、ハリスとの通商談判をなさしめた。通商談判といっても日本ではその経験はなく、したがって後年大隈重信候すら「当時は条約、条約と言っても何が日本に有利で、どの点で不利なのか一向わからず、不利な条件があっても、これでいいと思ったりしていたものだ」と言っている程であるから、当時の閣老連が何を談判すべきかであるかも知らず、ただ己の直感に信頼して、「ハリスは悪い男ではない」とみて、一切の通称草案の起草を依頼したのであった。まず交渉にあたって、岩瀬はハリスに向かって、「貴下は国命を奉じてわが国に来たり、わが国の為に誠意を以て事を議すべしと閣老に言明せられた。我々全権委員は貴下の公平誠実に信頼するのであるから、まず日本に利益ある草案を稿して言明偽りなきを明示されたい」と言ったものであった。思えば危険極まる話であったが、この直感は必ずしも外れてはいなかった。
後年この条約によって治外法権のため全日本は挙げて悩まされたが、翻ってこれをみれば、当時の日本としてはまたやむを得ない締結条約でもあったわけだ。
(今野幸助 著『太平洋は叫ぶ』p.25~26新東亜社 昭和15年刊)
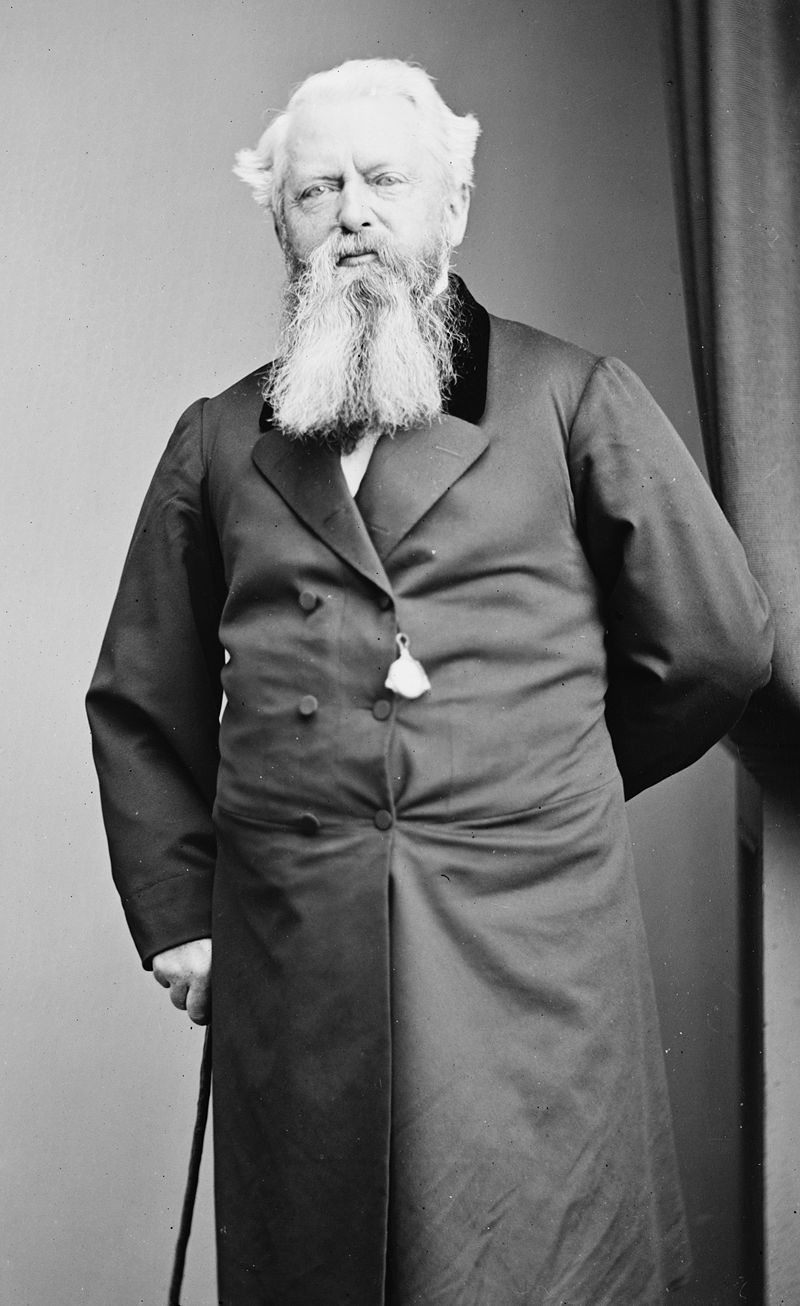
このように幕府はハリスに草案を依頼したのだが、ハリスは全権委員等と折衝しつつ草案を書き上げた。前掲書によると、
ハリスはよくわが国を蔑することなく、比較的正義の国使節に適わしい態度をもって終始し、その起草案が、井上、岩瀬全権によっ塗抹され、完膚なきまでに改竄されることを敢えていとわず、異習行われざるところとして枉(ま)げて日本全権の意に従った部分が多かった――と彼が、晩年岩倉使節一行が欧米訪問の節、米国に於いて使節一行に語ったと言われる。殊に関税については、日本の収入多からんことを計り、自由貿易の本則に従って平均二割とし、英仏使節の渡米前にこの前例を作らんとして調印を急ぎ、日本をしてよく、英仏の恫喝にたえしめんとしたと語り、税率とアヘン輸入禁止は実に条約の要目であった。しかるに、せっかくの心入れも数年を出でずして、税率は清国と同一率となったのは遺憾であると彼が語ったのであった。これには多少のおまけはあるとしても、事実として首肯されるところである。
(同上書 p.31~32)
全権委員もハリスに様々な要求をしたことは、条約の原文を読めば面白い条文がいくつかあるのでわかる。たとえば第八条。
「亜墨利加人 日本人堂宮を毀傷する事なく 又決して日本神仏の礼拝を妨げ、神躰・仏像を破る事あるへからす 双方の人民互に宗旨ニ付て争論あるへからす」
日本全権に、戦国時代にイエズス会宣教師の教唆により多くの寺社や仏像などが破壊されたとの認識がなければ、このような条文が作られるわけがないだろう。
勅許を待たずに条約調印を急いだ背景
またこの本には、江戸幕府が勅許をまたずに条約調印を急いだ事情について、こう記されている。
(安政五年:1858年)六月に入って下田に入港した米艦ミシシッピーは、意外なことをハリスに告げたのである。即ち、アヘン戦争以来、シナ侵略に手をつくした英国が、アロー号事件を契機として何度目かの難題をシナに吹きかけ、英仏連合軍の下に討滅していたが、破竹の勢いを以て北上随所に所在のシナ軍を破って、天津に迫り天津条約を締結し、その余威を駆って日本に来たり迫らんとすの情報である。
ミシシッピー号に続いてボーハタン号が、再び来たって風雲の急を告げたので、ハリスも条約の功を英仏に奪われてはと直ちに神奈川に入り、堀田閣老に次第を告げて善処を要望した。
堀田閣老も事ここに至っては、勅裁を待たずして調印せんとし、井伊掃部守は言葉をつくして阻んだが、海防掛一致の進言に条約調印決行と決し、わが陰暦六月十九日、西暦1858年7月29日わが国最初の歴史的通商条約は神奈川に於いて、ハリスと井上、岩瀬との間で行われたのであった。
(同上書 p.29~30)
前回の歴史ノートにも書いたが、アロー号事件は1858年6月の天津条約締結では終わらなかった。清国では英仏軍が引き上げたのちこの条約に対する非難が高まり、清国が条約の批准を拒んで砲撃を仕掛けたことから英仏軍は上海に引き返して再度武力衝突が始まった。英仏軍は天津に上陸したのち北京を占領し、円明園の宝物を掠奪した上、建物を破壊したのである。
ハリスはイギリスに日本を占領する意思があると伝えて、条約交渉を有利に導こうとした意図があったことは言うまでもないが、それまでイギリスがインドや中国などにしてきたことの詳細を知れば、「日本も同様な方法で弱体化され、侵略される可能性が高い」と誰でも考えることであろうし、天津条約締結でアロー号事件が集結しいよいよイギリス使節が日本に向かうと考えることも当然のことである。ハリスが功を急いで出鱈目を言ってわが国にブラフをかけたわけではないだろう。
もし条約交渉の最初の相手国がイギリスであったなら、わが国は条文の内容も充分に理解できないまま、圧倒的武力で圧力をかけられて、もっとひどい内容で締結させられたのではなかったか。最初の条約交渉相手がアメリカであり、全権がハリスであったことは、わが国にとっては幸運であったと思う。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、昨年(2019年)の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。
通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。
読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。
無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント