イギリス代理公使ニールの砲艦外交
生麦事件のあと英代理公使のニールは、島津久光に対して武力行使を行うとする意見を斥け、幕府と直接交渉することを選択したのだが、実際にどのような交渉が行われたのであろうか。
GHQに焚書処分された柴田俊三 著『日英外交裏面史』には、こう解説されている。
生麦事件の報が幕府に達すると大混乱に陥り、ほとんど為すところを知らぬという状態であった。この時英国公使オールコックは帰国中で、ニール中佐が代理公使を勤めていた。早速幕府に対し下手人の処罰、ならびに謝罪を促す書状を寄せ来たり、また米、仏、蘭三国の公使らからも忠告するところがあった。
(島津)久光は自藩から下手人を出すことを好まなかった。先供の岡野新助という足軽が斬りつけたのだが、その場から脱走して行方不明になっていると言い、幕権既に衰えて薩藩を処置し能わず荏苒(じんぜん:なすことがないまま)日を送っているので、ニール代理公使は耐え兼ね、京都へ行って条約を結ぶであろうなどと言い出した。
「英国は徳川幕府と条約を締結したが、大君(将軍)の威権行われずして、条約上の履行致し難きに於いては、京都へ上り、全日本の支配権を握る天皇と条約を結ぶであろう。かつ人心不折合などとは、国内に威権の行き渡らぬ虚偽の政府で、英仏などはかくの如きものではない。虚名の政府と交わるのは好まざるところである、云々」
(柴田俊三 著『日英外交裏面史』秀文閣 昭和16年刊 p.47~48)
そして文久三年一月十五日(1863/3/4)にニール代理公使にイギリス外相・ラッセルからの訓令が届いている。
内容は、犯人が判明していながらこれを逮捕処罰しないでいる幕府に対し、公式な謝罪と賠償金10万ポンドの支払いを要求せよ。幕府がこれに応じない場合は、英国海軍の司令官に要請し報復(船舶の捕獲、海上封鎖など)せよ。薩摩に対しては犯人の処刑と妻子養育料として2万5千ポンドの支払いを要求し、薩摩が拒否した場合は艦隊を率いて鹿児島に向かい、横浜と同様の行動を取れというものであった。
そして、横浜港にクーパー提督が三隻の軍艦を率いて来航し、後続の軍艦や以前から碇泊していた軍艦と合わせて十二隻の大艦隊が集結したのだが、アメリカのペリーが浦賀に現れた時は四隻だったので、その三倍の規模になる。ニール代理公使は日本に対する武力行使は、かえって居留民の損害を招き莫大な貿易の利益を失う恐れがあるとし、この艦隊の示威により要求貫徹をはかることとした。

前掲書に二月十九日(4/6)にニールが幕府に送った脅迫状が要約されている。
生麦において英人を殺害した島津三郎(久光)、ならびに一類の者を残らず召捕り、英人立会いの上首を刎ねよ。もし日本政府の権威衰えてその処理を遂げ得ざれば、償金として十万ポンドを支払わるべし。この回答のため二十日の猶予を与える。もしこれを拒絶せらるるにおいては、即刻軍艦を廻して大阪をはじめ、長崎、箱館の他の諸港に至るまで、出入りの船を奪取し、かつ江戸を焼き払うであろう。これ英国人の国旗並びに条約に対し、日本政府の過失なるを以て拠(よんどころ)なくこれ請求に及ぶ。
(同上書 p.49)
幕府は諸大名に出仕を命じて、ペリー来航の時と同様に、浜御殿、越中島、大森、御殿山、羽田などの警備に割り当てたという。当時の江戸や横浜の人々の反応が『横浜市史稿. 政治編二』にこう記されている。
ここに於いて江戸市中は大騒動となり、老若婦女は周章狼狽して、近郊に避難する者引きも切らぬ状況であったが、したがって横浜の如きも、十六日に神奈川奉行浅野伊賀守氏祐の令があったので、市民は皆避難することになり、次の日、奉行支配一同の家族の立退きが命ぜられ、その動揺は決して江戸に譲らぬ有様であった。
(横浜市 編『横浜市史稿. 政治編二』横浜市 昭和六年刊 p.439)
このような経緯から、横浜市中の多くは空家となり貿易はほとんど停止されてしまったという。
しかしながら、将軍家茂が数日前に京都に出発したため不在であり、「二十日」の回答期限内に回答できる状況ではなかった。幕府は米仏公使に調停を依頼したところ、一旦謝絶されたというが、米国公使が動いたという。『日英外交裏面史』によると、
米国公使は見るに見かね、英国公使に忠告して曰く、米国はこれまで幾多の苦心と財力と犠牲として、漸く日本に開国せしめた。しかるに貴国は艦隊を連ねて日本を脅すので、商人は皆恐れて逃げ隠れ、ために貿易派休止の有様となった。貴国もし日本に向かって開戦するに至らば、日本は再び鎖国して貿易を拒み、米国が苦心惨憺の結果、日本に開国せしめた努力も水泡に帰するであろう。貴国幸いに我が言を容れて反省する所あれと。英国側が回答延期を承諾したのも、米国公使のこの忠言があずかって力があったろう。
(『日英外交裏面史』p.50~51)
このブログで少し前に書いたが、万延元年十月に孝明天皇が和宮降嫁を勅許した際に、幕府は攘夷の実行を約束していた。将軍家茂が京都に向かったのはその説明をするためであったのだが、当時の京都は過激な攘夷熱で沸き立っていた。家茂は二月十九日(4/6)に二条城に入り、三月七日(4/24)に参内し、十一日(4/28)には孝明天皇の加茂行列に供奉したという。四月十一日(5/28)の石清水八幡宮への行幸には欠席したが、四月二十日(6/6)に「五月十日(6/25)を以て攘夷を実行する」旨の奉答書は出さざるを得ないような状況であったようだ。
一方、ニール代理公使は、二度にわたり回答期限の延長に応じたのち、三月十五日(5/2)に幕府が三度目の回答期限延長を求めてきた際に幕府高官の派遣を要請し、外国奉行の竹本正雅と竹本正明が横浜に派遣されている。この時にニールらは、フランスの提督を巻き込んで、鎖国攘夷を唱える雄藩を弾圧するなら武力援助しても良いと外国奉行に申し出たという。
この申し出に対して幕府はいかなる回答をしたのか。GHQ焚書の大熊真 著『幕末期東亜外交史』に詳しく書かれている。(日付については原著は西暦で統一されているが、ここでは漢数字を和暦、英数字を西暦として併記した)
竹本正雅は数回援助の申し出を拒否したが、英仏公使らはこの回答だけで満足しなかった。そこで将軍の意向を確認することとなった。
竹本甲斐守は京都に急行し、将軍の指令を仰いで帰東し、四月八日(5/25)、英仏公使と会見し、その武力援助を謝絶した。当然のこととはいいながら、また、攘夷を標榜し、その方法と期限を定めるために、朝廷のお膝元に行っている将軍として、撃攘すべき当の相手たる外夷と結び、その助けを借りるということは、出来る筈はない――とはいえ、幕府がかかる誘惑を斥け得たことは、ひとまず大出来であったといえよう。
ニールとの交渉の全権を委任せられた閣老小笠原長行は、四月六日(5/23)京都から江戸に帰着した。幕府は「償金は償金、攘夷は攘夷、二者は混同すべきに非ず」との方針で、小笠原閣老は四月二十一日(6/7)償金支払の意思をニールに報告した。…中略…
しかるに、あす第一回の償金支払いという五月二日(6/17)に、閣老小笠原はニールに「予見せざりし事情のために」償金の支払いはできないと申し送った。これは江戸への帰途にあった将軍後見職(徳川)慶喜から、小笠原に宛て、償金支払差し止めの命令を発したからであった。
ニールは一方に於いて米国公使ブルインに斡旋を依頼し、他方においてクーパー提督に報復を要請した。
五月六日(6/21)クーパー提督は、日本側の挑戦行動なき限り、八日間を待ち、敵対行動を開始する旨を宣言した。その間に、英国住民はその財産と家族を、港内の英国船に移す用意をせよと命じた。
五月六日(6/21)の会見に於いて、幕府代表は、ブルイン米公使に言った。表にては攘夷を標榜しているが、本心はそれを実行する意思なく、条約を守って外国との親善と貿易に努力する考えであると語った。五月七日(6/22)の深夜、神奈川奉行は、ブルイン米公使に申し入れた。「大君政府は五月九日(6/24)に償金を支払うであろう」又「小笠原図書頭は再び上京して、朝廷の排外的空気を一変せしむるであろう」
(大熊真 著『幕末期東亜外交史』乾元社 昭和19年刊 p.165~168)

先ほど、徳川家茂が孝明天皇に対し四月二十日(6/6)に五月十日(6/25)を以て攘夷を実行することを約したことを書いたが、攘夷を約した後にイギリスに償金を払っては天皇との約束に反することになる。老中小笠原長行は、この償金は払わざるを得ない金であるので、家茂が攘夷奉答を行ったの四月二十日(6/6)の翌日にニール代理公使に支払い意志を表明し、攘夷実行期日である五月十日(6/25)の前日である五月九日(6/24)に全額を支払っていることは注目して良い。そしてこの支払いに関しては、老中小笠原長行の独断によるものとされるが、五月三日(6/18)の支払い差し止めを指示した徳川慶喜の公伝にはこう書かれている。
幕府が久しく困(くる)しみたる生麦の償金は、斯く図書頭(ずしょのかみ:小笠原長行のこと)の独断といえる名目にて始めて解決せられたるが、これ併しながら一朝一夕の思い立ちにはあるべからず。去る三月図書頭が京都を発するに臨み、「勅命とさえあれば、利害得失をも計らず、ひたすらに遵奉し給えるは、婦女子の途にして、御職掌に叶わせられざることなり。唯民命を救い、国脈を存するの大義に著眼せられ、天朝尊崇の真意を御事業の上に顕わさるるこそ本意なれ」といえるは、実に図書頭の識見なりき。…
この度償金交付の事伝わるや、識者は「さては廟堂に人ありけり」と喜び合えりしが、幕府の有司は、皆事の意外に呆然たり。殊に尊攘派は、これを聞きて憤慨せざるものなく、「幕吏は皆国賊なり、神罰を免れず」と呪い、悪声は延きて水戸中納言と公(一橋慶喜)とに及び…まして図書頭の非難は、四方に囂々(ごうごう)たり。されど公と図書頭との黙契は、外間かつて知る者なかりしなり。[徳川慶喜公伝]
(徳富猪一郎 著『近世日本国民史. 第50 攘夷実行篇』民友社 昭和11年刊 p.104~105)
このように、手続き上は事後承諾となったかもしれないが、償金を支払うことがやむを得ない点については、慶喜も認めていたと思われる。いずれにせよ、小笠原長行のこの決断がなければ、わが国がイギリスとの戦争に巻き込まれていた可能性が高かったことを知るべきである。
攘夷実行期限前日にとった幕府の戦略
ところが老中の決断は、償金を支払うということだけではなかった。彼は続けて各国公使宛に次のような通告書を出している。文中の「大君」は将軍(徳川家茂)を意味する。
書翰を以て啓上す。京都よりの大君の命によれば、諸港は閉鎖すべく、外国人は追放すべしとあり。蓋しこの国の人民は、外国との交際を欲せざるが故なり。本件交渉の全権は余に付与せられあり。余はまずこの事実を貴下に通告し、追って詳細に関し談判を遂げんとす。
(『幕末期東亜外交史』p.169)
通告書の日付は文久三年五月九日(1863/6/24)だが、この日は将軍徳川家茂が孝明天皇と約した攘夷実行期限の前日である。幕府はこの日を以て鎖港談判開始の日としたのである。

各国の公使が小笠原の通告に接して驚いたことは言うまでもない。英国のニール代理公使は、その日に返事を書いているが遠回しな表現になっているので、イギリスが具体的に何を提案しているか分かりにくい。英国外交官のアーネスト・サトウはこう書いている。
思うに、それはイギリス側から大君に与えようという物質的援助の計画を暗示するもので、この援助によって、日本政府の対外親和政策に反対する西南部の諸大名の運動を抑制し、また天皇の条約批准を阻害するために大君と天皇の正式な妥協を妨害する運動を、抑圧しようというものであったろう。この種の援助がうまく実行されれば、大君は祖先伝来の地位に安定し、その後継者を顚覆させた1868年の革命は困難となり、おびただしい流血なしには成就しなかったであろうし、また日本国民は外国の援助で自己の地位を強化した支配者を憎悪するに至ったであろう。
(岩波文庫『一外交官の見た明治維新(上)』p.102~103)
サトウの言うように、幕府がイギリスの軍事的援助で生き延びようと考えていたわけではなかったと思うが、少なくとも小笠原は京都の世論を開国に向けさせようとした。そのために幕府は諸公使との会談を申し入れ、英国商船二隻を借りることに成功している。
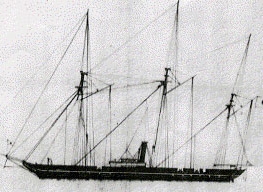
そして五月二十五日(7/10)に幕府の軍艦蟠龍丸、朝陽丸と英船二隻が一千数百の幕兵を乗せて横浜を出発し、六月一日(7/16)までに大坂に現れた。総帥の小笠原長行は京都に向かったが、将軍の直書により淀で食い止められたために入京は果たせなかったという。
大熊真氏は前掲書で、小笠原の入京の目的について、①将軍家茂の江戸帰城 ②京都の空気を討幕から公武合体に変える ③京都の空気を鎖国攘夷から開国に変える 点にあったとし、①については、将軍は二日後に東下を許され六月十六日(7/31)に江戸城に戻っており ②については期せずして八月十八日(9/30)の政変で達成されたが、 ③については幕府の存続する限りどうにもならなかったと書いている。
しかし、小笠原のこの行動により幕府の本心が攘夷ではなく開国にあり、攘夷は京都への申し訳程度の形式的なものに過ぎないことが外国側に理解されるようになった。
一方長州藩が馬関海峡を封鎖し、航行中の外国船に対して無通告で砲撃を加え始めていた。
外国側にとって、済ましておれないのは、長州の外船砲撃である。関門海峡が通れないため、上海・長崎・横浜の海上交通が、瀬戸内航路を封じられてしまった。のみならず、打ち続く長州の外船打払いは、日本全国に飛び火する危険が大であった。
ことに英国にとっては、生麦事件の未解決の反面がある。即ち薩摩との直接交渉がそれである。
(『幕末期東亜外交史』p.175)
小笠原の行動は結果として、攘夷の中心勢力がどこにあるかを諸外国に知らしめた。その後外国勢は薩摩・長州を砲撃することとなるのだが、その点については次回以降の「歴史ノート」で記すことにしたい。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。
通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。
読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。
無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。
電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。


コメント