GHQ焚書リストの中には、なぜこのような本を焚書処分したのかと思うようなタイトルの本が少なからず存在する。軍事のことを書いたわけではなく思想書でもない本の多くが焚書処分されているのだが、「日本語」に関する本まで多くが焚書処分にされていることは意外であった。
『日本語の世界化』
最初に紹介させていただくGHQ焚書は、言語学者の石黒修が昭和十六年に著わした『日本語の世界化』である。石黒は、昭和初期に於いてエスペラント語の教育者として何冊かの著書を出しているが、その後大東亜共栄圏を始めとする外国への日本語教育に関与した人物である。彼は多くの著作を残しているが、GHQの焚書処分にかかったのは、この一冊のみである。
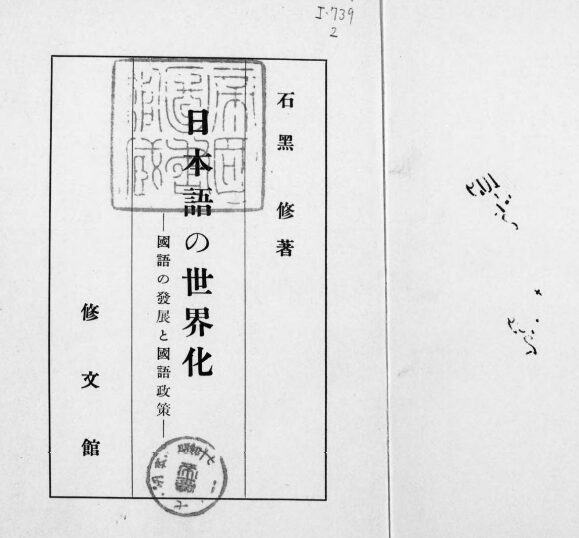
大東亜共栄圏における共通言語として日本語の普及が図られたのだが、そのことによりアジア世界に日本語が急速に広まって行った。同上書には次のように記されている。
日本語は、満州国において事実上の国語となり、支那において北・中・南のわが占拠地域に大量的な普及をみている。一方、ハワイ、北アメリカ・南アメリカなどわが同胞の発展地はもとより、フランス領インドシナ、タイ、オーストラリアをはじめ、諸外国にも、わが物資の海外進出、満州事変を契機とするわが国力の伸展に伴って、日本語は着々国外に進出し、世界において二億に達する通用者と学習者を持つに至った。
石黒修著『日本語の世界化』修文館 昭和16年刊 p.24
当時のわが国の人口を調べると、日本本土で約七千三百万人、朝鮮半島で約二千五百万人、台湾で約六百万人、南洋諸島で約十万人で、合計すると一億五百万人程度の数字になる。それに満州国、支那の一部地域を加えても二億という数字とは大きく乖離するのだが、「通用者と学習者」と範囲を拡大すれば二億に達するというのである。
日本語は戦前からアジア各地で学習されていたという。もちろんわが国が統治もしていない国に対し、日本語学習を強制するようなことはあり得ない。
先頃(昭和十三年十二月)タイ首府バンコックの日本文化研究所が新しく開設した日本語の講習は、定員百五十八名に対し、四百五十余名の申し込みがあり、摂政、文部・司法の二大臣、その他の顕官列席の下に盛大なスタートを切ったということが同地の新聞に写真入りで報道されていた。
世界の情勢の変化につれて、個々の国については一進一退はあるが、わが国運の発展に伴い、日本語も海外進出、普及の一路をたどっている。
かくして日本語はイギリス語につぐ世界の大言語になり、東洋においてはかつてイギリス語の占めた地盤をとって代わりつつある。
これはいうまでもなく、我々日本人にとって、まことに喜ばしく、望ましいことである。しかし、これが本当にそうなるためにはまだいろいろな条件が伴われなければならなぬことを知らねばならない。
例えば、国内において、無自覚な外国語崇拝を改め、自国語を尊重して、私たちがまず国語に対する愛とほこりをもつことが必要である。
同上書 p.33~34
「大東亜共栄圏」という言葉が使われたのは昭和十五年のことで、それ以前から日本語学習熱が各地で高まっていたわけだが、特定の語学を学ぶ動機は、国から強制されることがなければ、ビジネス上の必要があったか、文化的に興味を覚えたかのいずれかであろう。
言うまでもなく第二次世界大戦前においては欧米諸国を除く世界は、わが国とタイ以外のすべての国が欧米の植民地であった。欧米諸国にとっては、彼らが統治している植民地において現地人の間で日本語を学ぶ者が急増している状況は、脅威であったことに違いないだろう。彼等にとってわが国が文化力で植民地の原住民に影響を拡大し続けていることは、わが国の「静かなる侵略」と目に映ったのではないだろうか。
『大東亜共栄圏と国語政策』
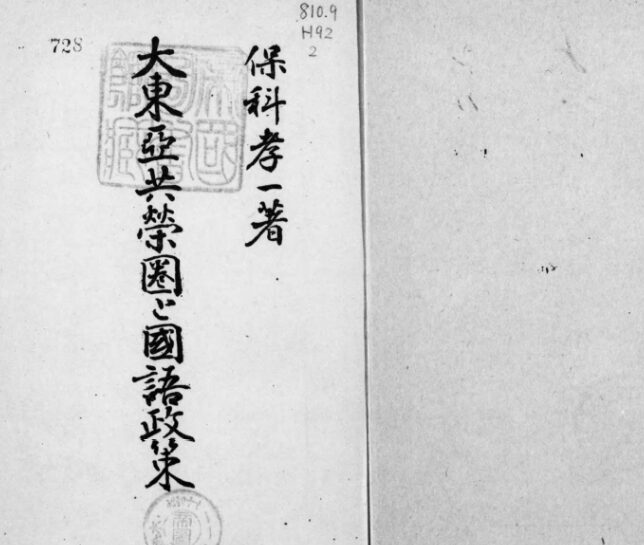
日本語学習が熱心であったのは、いわゆる「大東亜共栄圏」の国々だけではなかったことが、国語学者・保科孝一 著『大東亜共栄圏と国語政策』の第八章に詳しくレポートされている。日本移民が多数居住していた米国やハワイ、南米等で熱心に学習されていた。同書にはブラジルの事例について次のように記されている。
ブラジルにおける日本語熱も近来頓に向上し、これを学ぶ者が多くなり、大学に日本語講座設置の議も起こっているそうである。サンパウロ、バラー、アマゾナス三州における日本人経営の小学校で、ブラジル人に日本語を教授している。先般ブラジルに関する報道として、まことに耳よりのものを読んだ。それは支那事変当初ブラジルにも、わが国を侵略国と誤解して反感を持つものがあったが、近来ようやく正当な理解を得て、わが国に対する態度が好転して来た。その結果日本語熱が急速に向上し、サンパウロ法科大学では、前アルゼンチン公使古谷重綱氏が開設した日本語講座に、七十余名の生徒があり、リオ・デ・ジャネイロでは、中央協会支部に六十余名の生徒が熱心に勉強している。
保科孝一 著『大東亜共栄圏と国語政策』統正社 昭和17年刊 p.323~324
日本人が移住した国の原住民の間に日本語を学ぶ者が多かったことは戦後のわが国ではほとんど知られていないが、当時南米ではブラジルだけでなくアルゼンチンやチリ、メキシコなどでも日本語熱が高かったという。
次に支那をみてみよう。支那において徹底的な排日・抗日教育が行われたことは誰でも知っていることなのだが、支那でも日本語を学ぶ支那人が多かったのである。
支那事変が起こってから、皇軍の向かうところ、草木もなびかぬものがない。事変後いくばくもなくして、北支に中支に南支に、日章旗があざやかに国威を宣揚している。さきに述べた通り、国威の宣揚するに従って、国語の発展がこれに伴うのが原則であるが、今回の事変がもっともよくこれを実証しているのである。
日支両国の友情こまやかであった時代には、支那からわが国に留学する学生もすこぶる多数に上り、それらの学生が学成って帰国の後、それぞれ要職に就いたので、ついには日本語を知ることが、幸福を招来する所以であると信ずるようになった。
されば排日・抗日の気勢がさかんになって来てからも、日本語熱が依然として衰えなかった。であるから、今次の事変以来、ことに大東亜戦争開始後わが旋風のなびくところに、たちまち日本語熱が高まっていることは、新聞における幾多の通信が、これを証明している。
同上書 p.336~337
以前このブログで『支那の少年は語る』という本を紹介させていただいたが、支那事変後に多くの中国人がわが国に留学のために来日したことは事実である。
支那で排日運動が始まったのは1919年だが、一般の支那人は必ずしも排日・抗日ではなかったことを知るべきである。
今日では世界各国で日本の文化が高く評価され、訪日外国人は年々増加し、日本語を学ぶ外国人も各地で増加していると聞く。戦前とよく似た状況が世界規模で生じているのだが、今のわが国の無能な内閣を見ていると、どこかの勢力がわが国の文化や制度を破壊しようと強い圧力をかけているのではないかと思うのは私ばかりではないだろう。
日本語、国語に関するGHQ焚書リスト
GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルから判断して日本語、国語に関係のありそうな本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。
分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。
| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |
出版年 | 備考 |
| 国語論集日本語の朝 | 島田春雄 | 第一公論社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1126262 | 昭和19 | |
| 国民学校国語の修練実践 | 米田政栄 | 啓文社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1440032 | 昭和17 | |
| 言葉の魔性神秘性に徹せる 国語教授へ |
金子彦二郎 | 昭和出版社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1464817 | 昭和3 | |
| 少尉候補受験国語 | 今田哲夫 | 子文書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1457752 | 昭和12 | |
| 少尉候補模範国語 | 関口正次 | 一二三館 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和18 | ||
| 戦争と日本語 | 釘本久春 | 龍文書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1857286 | 昭和19 | |
| 大東亜共栄圏と国語政策 | 保科孝一 | 統正社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1126345 | 昭和17 | |
| 大東亜言語建設の基本 | 志田延義 | 畝傍書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1872034 | 昭和18 | 大東亜文化建設研究 ; 第6 |
| 日本語の世界化 : 国語の発展と国語政策 |
石黒 修 | 修文閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1126348 | 昭和16 | |
| 日本精神徹底の国語教育 | 菅根正三郎 | 新生閣書店 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1443739 | 昭和9 | |
| やまとことば | 吉沢義則 | 教育図書 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1069635 | 昭和17 |
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


【ブログ内検索】
大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。
前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。
全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。
電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。
またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。







コメント