首将はかくあるべし
『戦う国・戦う人』を読み進むと、軍の首将たる者はどのような人物であるべきかについて述べている箇所がある。軍隊だけではなく企業や団体などあらゆる組織のリーダーにも参考になる話だと思うので、引用させていただく。

軍の目的は敵を亡ぼすにあるのです。呉子は「門を出づれば敵を見るが如し」といっています。
一たん軍の指揮を執った以上、何人の干渉も受けてはならないのです。手を引っぱったり、足を引きずったりされては、軍の指揮は執れないのです。
フランスでは、前線を視察した代議士までが、大砲の音にビックリして、攻撃中止の命令を要求したことさえありました。前の大戦のことです。しかし、こんどもそういうことがあったようです。大局の戦況も知らず、ただ目の前の激戦をみて、仰天したのです。…中略…
フランスは、一将軍に兵馬の権を与えたという例がなかったのです。ペタン*に全仏軍の統帥を委任したのは、ズッとあとのことでした。
*フィリップ・ペタン:フランスの軍人、政治家。第一次大戦後元帥に昇進。1940/7~1944/7首相軍中のことを知らないものが、一般政治と同様に行ったのでは、戦争の指揮は執れないのです。軍に干渉することを、孫子では「縻軍」といっています。糸で引っぱる意味です。「三軍のことを知らずして、三軍の政をおなじうすれば、即ち軍士惑う」と、孫子のいう如くです。
一家でも統帥権が紊れたらメチャメチャです。一たん開戦となった以上、内政も外交も、すべて戦争の一本建てです。呉子は「文武を総ぶるものは軍の将なり」といっています。武の方面ばかりで将をみることは出来ない。勇ばかりでは将の器でない。それは猪大将というものです。文徳の備わった人、――柔和にして、剛毅なる人こそ将である。「剛柔を兼ねるは兵の事なり」とあります。
「およそ、人の将を論ずる、常に勇に観る。勇の将におけるは、すなわち数分の一のみ」と、呉子はいっているのです。
酒井忠勝*が真田信幸を招待して、「御家に兵法の御相伝がありと承るが、御伝授を願いたい」というと、信幸は「家来を愛することである」といいました。信玄も兵法の家伝として「人は城、人は石垣、人は堀、情は味方、仇は敵なり」といいました。
*酒井忠勝:徳川家光~家綱時代に老中・大老を務めた
桜井忠温『戦う国・戦う人』偕成社 昭和19年刊 p.69~71
部下を信頼しないようなトップでは部下がついてこないのはどこの組織でも同じで、命がかかっている軍隊では尚更である。孫子は「彼を知らずして己れを知るものは一たびは勝ち、一たびは敗れる。彼も知らず、己れも知らなければ、戦うごとに敗れる」「上下欲心を同じうするものはかつ」という言葉を残しているが、上下の心が一つにならなければ、思い通りに組織を動かすことが出来ない。桜井はこんな事例を紹介している。

ナポレオンがエジプトへ遠征したとき、暑くはあり、バタバタ病人が出来たので、ナポレオンは「馬に乗るものは下りて、病人を乗せて行け」といいました。そして、自分も馬から下りて、病人を乗せ、そのあとからついて歩きました。
家康も「主の題字は従者が救い、従者の危難は主が助けるものだ」といいました。
三略(兵法)にも、「将は士率と滋味を同じうし、安危を同じうす」とあります。…中略…
黄金の前に頭を下げたり、栄達のために、恥を恥と思わぬ人間は、人を率いる器もなければ、人に率いられる値もないのです。
同上書 p.91
しかしながら、軍のリーダーでありながら部下を残して戦場から脱出する者もいた。
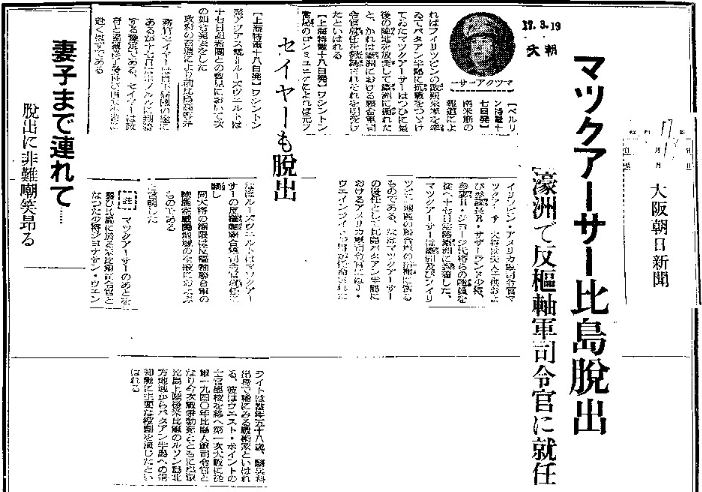
マッカーサーが、フィリピンを逃げ出すとき、ルーズヴェルトに当てて、電報を打ちました。
「日本人は戦争のために生まれ、戦争のために訓練してある。かかるものと戦争をしても勝ち目はない」
というのです。それも丁寧に二通も同じものを打っているのです。
如何に日本の兵隊といっても、戦争のために生まれて来たのではありません。しかし、戦争のために訓練してあることだけは確かです。
なんというなさけない大将でしょう。
同上書 p.84
南京戦でも蒋介石や唐生智も、日本軍と戦う前に兵士を残して南京から逃亡したのだが、兵士からすれば、こんな将のもとではバカバカしくてまともに戦う気がしなくて当然である。日本軍が接近して明日にでも南京が陥落しそうになると、大量の支那兵たちは南京城から逃げ出すために北西にある挹江門に殺到し、逃亡を防ごうとする督戦隊との同士討ちによって付近には大量の死体が残されたことは以前このブログで書いた通りである。
一兵百殺
日本兵にとっては国のために戦うことは当たり前であったのだが、そのような戦い方をした国ばかりではなかったのである。桜井は次のように記している。

支那兵は、褒美一つで戦をするのです。「あの町を取ったら、金もとり次第、食い放題、しっかりやれ」といって、兵士の尻をたたくのです。蒋介石は「克く拠点(大切なところ)を死守し、進んで退かざる者に対しては、三級を昇級し(月給の三段跳びです)栄を三代に贈り、流芳百世に伝えん」などと訓令を出しました。
よく働いたものには、月給を増してやるというのです。支那兵は月給のために死ぬようなものです。
国のために死ぬのではないのです。アメリカ兵も、イギリス兵も、何のために戦うのかも知らないのです。「敵は日本だ」というだけが彼等のすべてなのです。「人、戦いに勝って厚賞の利あるを知るときは、白刃を冒し、矢石に中って、楽しんで以て進む」というのが支那流、アメリカ流、イギリス流です。褒美めあてのいのちです。昭和十七年四月十八日、東京はじめ各地を爆撃したアメリカ兵には、無事に帰ったら十万ドルやると、賞金で釣ったのです。サーカスのつもりで、志願したのだから驚いたものです。中には、どこへ行くとも知らずに、志願したところが、東京を爆撃するのだと聞かされてビックリ仰天したものもあったが、もし日本で捕虜になっても「日本人は親切だから、お前たちを殺すようなことをしない。褒美は思いのままだ」といわれたので、腹を決めたということです。
こんなことで、真剣な戦が出来ると思っているのでしょうか。笑止千万です。戦争を賭け事と考えているのです。張学良が、突撃兵に一元ずつの前褒美をやったことがあります。金をやらなければ突撃しないからです。冥途の土産に一円ずつ貰って行こうというのだから現金なものです。死んだら、もともとどおり引き上げられるのだから、見せ金で突撃させるようなものです。
孫氏は「敵の利を取るものは貨なり」といって、金でいのちをすてさせているのです。
同上書 p.95~96
こんな姿勢で戦っている敵兵を相手に戦っていた日本兵は少数であっても何度も敵兵を倒してきた実績がある。
マライでも、フィリピンでも、ソロモンでも、――支那大陸でも、日本軍は一対十、二十、五十、時に百倍という敵と戦ったのです。ラバウルでも、ニューギニアでもそうです。いつでも小を以て大を討っているのです。比較にならぬ違いです。
山西の聞喜城(現在の山西省運城市にある城)では、敵に囲まれながら五十日も戦いました。敵は数十倍する兵力です。敵をなるべく多く引き寄せて、他の方面の戦況を有利にする任務を持っていました。しかし、五十日もよくこの大敵を支えたものです。
メリケン粉の団子一つが、一日の食糧でした。それでもがまんしたのです。
死んだ鳥を屠り、犬を捕って食いました。そしてとうとう三箇師の敵を、追い払いました。
ある決死隊は、三十名で敵の九百と、九十日にわたって戦ったことさえあるのです。ソロモンの敵の飛行機は、われに十数倍するものです。それをドシドシ撃墜しているのです。
昭和十八年十一月二日、二百数十機の敵機がラバウルに殺到し来たったが、対空砲火でその五十一機を、戦闘機は百二十七機を、その他二十三機、合わせて二百一機を撃墜しました。空前共空前、驚くべき戦果でした。こういう例はどこの国にもないのです。ナポレオンは「六割の兵力を以て戦うは、ほとんど賭博に等しい」といっているのです。それに皇軍はあらゆる兵学者の説を破っているのです。
同上書 p.101~102
ソロモン諸島の戦いで日本軍は少ない兵力で良く戦ったのだが、最終的には空軍力で圧倒的に優っていた米軍に敗れてしまった。しかしながら、兵力では圧倒的に劣勢であったにもかかわらず、支那事変では強かった。それは戦い方についての伝統的な考え方が、わが国と支那とは随分違っていたことを指摘している。
相手に及ばないものがあったとしても、その及ばないものを以て戦うことも出来るのです。われの「短」が、却って敵に取って苦手である場合もあるかも知れないのです。
孫子は――「少なければ則ち之を逃れ、若かざらば(及ばなければ)則ち之を避く」といっています。敵より少ないと見たら逃げろというのです。敵に及ばないと見たら旗を巻けというのです。
これは支那式です。こんな意気地のないものは役に立たないのです。いつでも逃げる支那兵などはこの流儀です。柳生但馬守は、「わが剣短ければ進んで行け。一歩を進みて長くすべし」といったが、これが日本式です。剣が短ければ進んで行け、長短大小は問題でないのです。孟子は、「小は固に以て大に敵すべからず。弱は固に以て強に敵すべからず。寡は固に以て衆に敵すべからず」といいました。弱は強に敵わないのは道理でも、小と大とが相撲にならないというのは大間違いです。孟子流なら、小さい相撲取りがいつでも負ける勘定です。
支那では、そういうことが戦争の建前になっているのです。何でも大きなもの多いもので頑張ろう、押そうという風があるのです。日本式ではどこまでも地味に、ガッチリと行こうという流儀です。大、決して恐れるに足りないのです。
敵の不利を見出して、われの利とするのが戦術です。奇襲し、強襲し、夜襲するのも、敵の過失に乗じ、思わざるところに飛び出すのです。小兵にして大兵を破るのはこういうところに曲があり、妙があるのです。
同上書 p.108~109
敵より少ないと見たら戦わずに逃げるのでは、武力戦に勝つことはありえない。しかしながら、何度も繰り返してそのような戦い方をしていれば少なくとも自軍が負けることはなく、時間をかけて相手を疲弊させることはできる。日本軍はそのために苦しめられたのだが、その点については桜井は触れていない。
ムチャクチャ兵法
善良な人物は支那の兵隊にはならず、軍に集まるメンバーは盗賊のようなものが多かったというのだが、その原因は孫子の兵法の影響があると思われる。
孫子の兵法は支那の戦法だから、戦争だか泥棒だかわからないところがあります。「饒野(富んだ土地)を掠めれば、三軍(軍隊)食するに足る」などといって、十分食うものもあるから、兵隊を喜ばせ、兵隊を働かすことが出来る、といった風に、まるで泥棒かせぎです。ただ兵法として取るものがあるので、二千五百年も昔の兵法ながら、今にもてはやされているのです。
「往くところなければ固く」といって、兵隊も、帰るに帰れずとなれば勇敢に死闘する、といった風です。
兵隊を人間扱いにしていないのです。「陥れば懼れず」といって兵隊を苦しめさえすれば、仕方なしに死戦するといったムチャクチャな兵法です。…中略…
支那の大将は、兵隊を火の中に入れることを、石ころか何かのように思っているのです。…中略…人を服すのは徳です。支那軍のようでは、尻をたたいて戦わせても、いつかは離れるのです。部下を一万二万と引きつれて、帰順するものがあるのも、蒋(介石)の人徳が足らないからです。戦うべきものなら、どこまでも戦うべきです。それがいつの間にか離れてしまうのです。
支那軍にも、イギリス軍にも督戦隊というものがあって、前方にいる兵隊をうしろから監督しているのです。心太のように、うしろから押し出すのです。逃げたら撃ち殺す役です。イギリス軍はインド兵を前へ立てて、うしろからピストルを向けているのです。…中略…
孫氏の兵法は、いいところは非常にいいが、そこらの野良兵共をつれて戦争に行くようなことを考えているのです。
同上書 p.120~123
確かにムチャクチャな兵法のように見えるのだが、結局日本軍は個別の戦場では勝利しても支那兵は降伏はせず、潜伏しては民家や鉄道などの施設の襲撃を何度も繰り返し、そのために日本兵の疲労は蓄積していった。長野朗はこのような支那の戦い方を「遊撃戦」と呼んだが、支那共産党は正規戦よりも遊撃戦を重視し、長期戦に持ち込むことを狙っていたのではなかったか。桜井のこの書には「遊撃戦」には触れていないが、わが国は支那との戦争に手こずっている間に第二次世界大戦に巻き込まれていくのである。
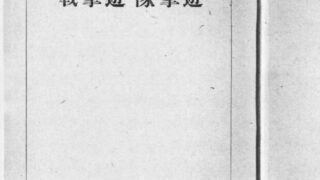

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


【ブログ内検索】
大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。
前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。
全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。
電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。
またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0cb3edfa.2c8ab20f.0cb3edfb.f5cdd14c/?me_id=1213310&item_id=19552219&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1931%2F9784286201931.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント