インドに病苦と災厄をもたらしたアヘン
前回記事の最後にアヘンの事を触れたが、インドは世界最大のアヘンの生産地にされていたのである。GHQ焚書処分された本に百々巳之助 著『植民専制史論』という本があり、そこには次のように解説されている。
インドは世界中一番多くアヘンを算出する。そしてその約半分がインドで消費され、残りの半分が輸出されている。アヘンの輸出を盛んにするために、イギリスは支那と二年間も戦争している(アヘン戦争)。インドが消費するアヘンは毎年百七十萬ポンドに及ぶ。その製造、吸引はわが日本に紹介されている様に決して秘密のアヘン窟で行われているのではない。官立のアヘン販売所が七千もあり、その製造も純然たる政府の事業となっている。そして世界の医学によって定義されている人体に有害なアヘンの吸飲を奨励している。イギリスがインドに侵入するまでインドにおけるアヘンの吸飲はごく穏やかな程度で、今日の如く公然かつ宏大には行われてはいなかった。それは国民の宗教上の心情がこのことを固く禁じていたからである。ゆえにガンジーも
「イギリス国民が来るまでインドでは如何なる政府もその税金欲しさにアヘンの吸飲を奨励しアヘンの害毒をこの国に植え付けた政府はかつてない。アヘンの消費は今世紀に入ってから著しく増加している。英政府は恐るべき堕落と言語に絶する惨めさと、癒しがたき病苦と災厄をインド国民に齎した」
と憤慨しているほどである。だが英政府はアヘンの課税なしにはやっていけないと宣言する。1923年に政府の緊縮委員会が発表した報告書によると「アヘンの販売高を維持することが重要な財源である。」と強調している。
(百々巳之助『植民専制史論』p.97~98)

(実から採取される果汁を乾燥させてアヘンを製造する。アヘンは麻薬の原料となる)
イギリスは毎年のように多くの餓死者が出ている中でインド人にケシを栽培させ、アヘンを製造させていたことになる。そして彼らは、インド人に対してアヘンの吸飲を禁止していたのではない。むしろ推進していたのである。その目的はインド民族を弱体化させるためであったと著者は述べている。
なぜ町々のアヘン販売所がアヘン溺飲者の群れを誘発するか。英国のインド政策の裏にはこんな悲惨も織込まれている。即ち田畑や工場で働かねばならぬインドの女たちが子供たちに飢えて泣き叫ばれては堪えられぬ。そこで手近なアヘンを子供たちに与えるという方法が聡明なイギリス人によって教えられ、かくてインドの平均寿命がわずかに26年という結果と民族の弱体化とがもたらされたが、これがイギリスの思う壺なのである。(子供たちの90%迄は二歳になるまでにアヘンを飲まされている。)しかもボンベイでは今日毎年一千人の子供のうち六百六人は死亡するという驚くべき統計が示されている。またそれがペスト、コレラ、来廟、結核などが猖獗を極める理由なのであり、1918年から翌年にかけて流行したインフルエンザが飢餓とアヘンと酒による害毒によって一層弱められていたインド人の一千二、三百萬人を死に至らしめた理由なのである。――大戦四年の全参加国が失った総人員より多い――。
(同上書 p.98~99)
飢餓とアヘンと酒でインドの人々は栄養不良のため、インフルエンザの流行で多くの命が奪われ、その死者の数は第一次世界大戦の全参加国の死者よりも多かったというのはすごい話である。
異常な平均寿命の低さ
平均寿命が26歳というだけでも驚きだが、他の本にはインド人の平均寿命はそれからさらに低下していったことが書かれている本がある。
これから紹介する金子健二 著『印度』もGHQによって焚書処分された本だが、この本の中で各国との平均寿命の格差が解説されている。
インド人の平均寿命は…年々低下しているのは事実である。例えば大正十年に男子の寿命が平均二十四歳八か月で、女子は二十四歳七か月と言われていて、いわば、この点では男女の間に大きな差がなかった。然るに昭和六年になると男子は二十三歳三ヶ月、女子は二十二歳八か月となっていて、女子の寿命が短くなってしまった。そしてこの年の我が日本人の寿命は男子四十六歳五か月、女子四十六歳五ヶ月となっている。しかるに英国人の寿命ははるかに我々より長い。すなわち、昭和七年度にはイギリスの男子の寿命は五十八歳七か月、女子は男子よりは長命で六十二歳九か月となっている。またドイツでは昭和九年度によれば男子五十九歳九か月、女子は男子より寿命が長く六十二歳八か月となっている。
(金子健二 著『印度』湯川弘文社昭和12年刊p.122)
異常な一人当たりアヘンの消費量
アヘンの危険性についてイギリスが認識していなかったことはあり得ない。イギリス本国ではアヘンの使用も売買も厳しく取り締まっていたにもかかわらず、インドではほとんど無制限の使用を奨励していたのである。
ではインド人一人当たりどの程度消費されていたのであろうか。
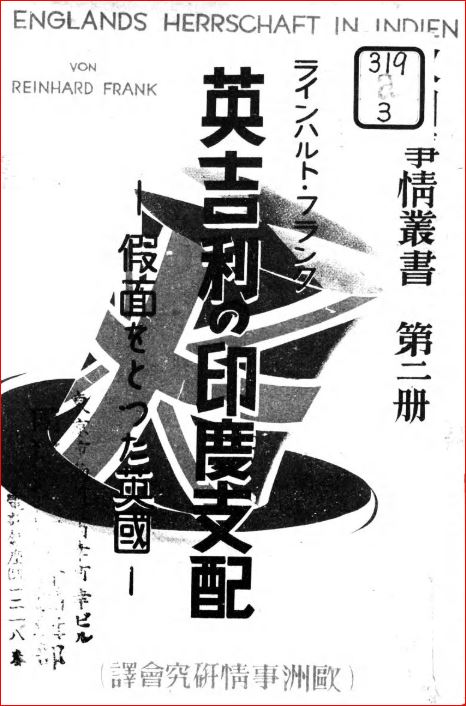
GHQに焚書処分された『英吉利の印度支配 : 仮面をとつた英国』にはこう解説されている。
ジュネーブの連盟の一委員が確証するところによれば、医療用のアヘン消費量は通常平均人口一万人について6キログラム以下に過ぎぬ――すなわち一人当たり0.6グラムに過ぎない。しかしアッサムの若干の地方に於いては、年平均のアヘン消費量は、一万人につき106乃至227キロ(すなわち前記の17倍乃至38倍)であり、カルカッタに於いては一万人につき144kgこれは一人ひとりの量として大したものである。パンジャブの住民は元来、全員土中最も頑健にして、勇猛であり、同地は大戦後擾乱が勃発し、かのアッシリアの殺戮によって鎮圧された地方であるが、こうした人民の力もやがてアヘンの為に打ち砕かれるであろう。というのはアヘンが、1920年代アムリツア事件以来おそろしく侵入しており、既に十年前アヘンの平均消費量はラホールでは一万人につき40kg、ルージャナでは49kgに上っていたのである。
(『英吉利の印度支配 : 仮面をとつた英国』p.89~90ニッポンプレス昭和15年刊)
イギリスが、有害と知りながらアヘン販売を奨励した理由
当時の世界においてアヘンが有害であることはどの程度認識されていたのであろうか。
フィリピンでは長い間アヘンが販売されていたが、アメリカ政府はこれを完全に禁止している。シナではアヘンの害は甚大であったが1907年から1917年の間にはほとんど禁止されていた。その後ももし外人がいて商売などしていなかったとしたら、もちろんシナにアヘンは絶えていたはずである。また日本では、アヘンの害を認められた台湾において、10年の間にこれを禁止し得た…。
(同書 p.92~93)
このように、世界では多くの国がアヘン販売禁止に動いていたのだが、イギリスはインドで販売を奨励しつづけ、反対運動を許さなかったのである。同書にはこう記されている。
このアッサムにおいてガンジー一派は、アルコールとアヘンに反対する運動を行った。彼らは単に、道義心に訴えて説得するのであるが、同地方における使用を50%減少することに成功した。しかしこれに対して政府は何をしたか?63名の演説者のうち44名を捕らえて投獄したのである。
(同上書 p.91~92)
イギリスはインドにおける反対運動を封じて、アヘン販売を禁止することはしなかったのだが、その理由の一つは財政上の理由と説明した。そして、後にアヘンの販売を制限されることになっても、販路を拡大することによって穴埋しようとしたという。
英国政府はアヘンの税収入を断念することは出来ないと宣言した。1923年の財政委員会は、一報告に於いて、インドのアヘン販売は国庫収入の重要な源泉であってこれを保存することが必要であると強調し、それを軽減することはできないと明瞭に宣言している。ある一人の利口者がうまいことを考えついた。それは最小量のアヘンの使用から最大量の税収入を得る方法である。即ち新領土の隣接地法にアヘンがまだ喫飲されていない所があれば、そこにアヘンの販路を拡張するということである。
そこで、アメリカの宣教師・ジョン・リギンス氏は、彼のアヘンに関するパンフレットの中に次の如く記している。
「ビルマ(東部印度)が英人の権力によって征服されなかった前、即ちビルマがインドに合併されなかった前は、ビルマではどこでもアヘンは厳禁されていたことは、あたかも今日の日本の如くであった。日本人もシナ人もアヘンが破壊以外の何物ももたらさぬことをよく知っているのである。ところが英国人が、ビルマの支配権を握るようになると、英人の下級官吏はアヘンを土着民の間に販売して利益を得るようになった。」
(同上書 p.90~91)
しかしながら、税収を増やすことが真の目的であったならば、アヘンを禁止した方が国民の労働力が高まり、生産性向上とともに消費も増加し、結果として税収も増えると考えるのが普通であろう。そのことはイギリスが分かっていないはずはなかった。
ではなぜ英国政府はこの利益のある道をすすまなかったのだろうか?否、逆にアヘンの使用をあらゆる手段で以て奨励したのはなぜだろう?彼らが臆面もなく「金が必要なのだから仕方ないさ」というところのその「財政の必要」は結局のところやはりまだ一つの口実であって、その蔭にもっと悪いことが隠されているのではないか?インドには、三億五千万人のインド人と十一万五千人のイギリス人が住んでいる。即ち、一万人のインド人に対して三人のイギリス人という割合になる。
(同上書 p.97)
もし多くのインド人が元気であり、物事を考える力を保有していては、少数のイギリス人によるインド支配から逃れようと行動することになるに違いない。
そうなると三億五千万人の民族に対する英国の支配はどうして維持することが出来るか?そうすると七万人の英人の一人一人が機関銃を一つ宛手にして各五万人のインド人を抑圧することはとてもできない。その他また、若い英国人は、もう段々とインドに来たがらない傾向がある。それは種族の力が衰えてインドの風土が彼等には耐えられなくなったためである。
こういうわけで英国はインドをフーゼル酒とアヘンの毒で制圧するのである。
こういうわけで町々の店がアヘン嗜好者を誘惑するのである。
こういうわけで農村や工場のインド人の女はその小さな子供に、アヘンを与えているのである。(これらの子供の9割までが、2歳になるまでアヘンを与えられる。)
こういうわけでインド人の平均寿命は23歳である。 …
(同上書 p.99~100)
イギリスのインド統治がひどかったという事実は戦前には書物だけでなく新聞でも伝えられていたのだが、戦後になってからはほとんど日本人に知らされていないのではないだろうか。こんな暗い話を知る必要がないという考えの方もおられるとは思うが、こういう史実を知らずして、なぜわが国がこのような国々と戦ったかを正しく理解することは困難ではないだろうか。わが国が国防をおろそかにして国の主権を奪われてしまえば、インドと同様に国民は奴隷のように扱われるか、のちに主権を取り戻すために大量の犠牲者を生むことになる可能性を誰も否定することはできないだろう。当時の日本人は、このようにならないために国を守ろうとして立ち上がったという見方ができると思うのだが、その論拠となる史実の多くは、戦後のわが国では今も封印されたままの状態にある。
この記事で紹介した書籍はいずれもGHQによって焚書処分されてしまったが、今では『国立国会図書館デジタルコレクション』でネット公開されており、誰でも無料で読むことが出来る。
イギリスの植民地統治に関する書籍は外にも多くの書籍がGHQによって処分・廃棄されており、昨日そのリストをこのブログにアップさせていただいた。これらの書籍は、以前このブログで採り上げたGHQの検閲指針で言うと「英国に対する批判」に該当したと判断されて焚書処分されたものと考えるが、多くがネットでは公開されていない。国立国会図書館では著作権保護期間が終了した著書はネット公開する方針であるので、ほとんどの焚書がネットで読める日が早く来ることを期待している。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、昨年(2019年)の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。
通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。
読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。
無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの店舗でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。


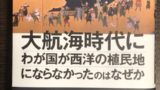
コメント
いつもありがとうございます。
たのしく拝見させていただきました。
読んでいただきありがとうございます。
今の中国も酷いことをやっていますが、19世紀から20世紀にかけて最も酷かったのはイギリスではなかったでしょうか。しかし、戦後のわが国では、このような史実が語られることは殆んどありません。いつの時代もどこの国でも、勝者が歴史を書き換えることの典型ですが、こういう史実を知らないことには、戦勝国に対して対等に渡り合うことは困難ですし、相手に忖度するだけではまともな外交が出来ませんね。