戦後の教育やらマスコミの解説などで、軍人はわが国を戦争に巻き込んだ犯罪者のようなイメージを擦り込まれていて、私の場合、恥ずかしながら軍人の書いた文章を読む機会はほとんどなく、読んではいけない本であるとか、学ぶところがないに違いないと、長い間勝手に決めつけていた。しかしながら、実際にGHQが焚書処分した本を読んでみると、軍人の著作は当時の世界情勢やわが国の状況の本質をよくとらえていて、勉強になる著作が多いのである。

海軍少将の真崎勝次が第二次大戦参戦二年前の昭和十四年に著した『非常時局読本』という本の一節を紹介したい。
近代戦の特徴が武力戦の外に思想戦であり、外交戦でありまた経済戦であるということは、今日では皆異口同音に唱えているところであって、今更呶々(どど:くどくど説明すること)を要せない所である。しかしながら、よく詮索してみるとこれは今日に始まったことではないのであって、昔からの名将と言われる人は必ず武力戦を有利に進展せしむるためには、いわゆる思想戦も外交戦も経済戦もこれと並行して実行しているのである。
例えば徳川家康公の大坂城攻略にしても直に武力を以て落としてはいない。また敵方に廻りそうなものに対しては人質を取ってその死命を制するような手段も採っている。シナにおいては合従連衡の謀略が盛んに行われ、またヨーロッパにおいてもパルチザン戦その他後方攪乱の手段が行われて有利に兵戦を指導していくというようなことは古来盛んに行われているのである。ただ昔は武士という特別な人のみが戦争に従事していたので、真に国民の総力戦でなかったために、思想戦も外交戦もあるいは経済戦も今日ほど戦争に対して重要なる役割を演じていなかったに過ぎないのである。
しかして、更に突っ込んで考えると、思想戦が近代戦の特徴であるというよりも、むしろ近代戦は思想戦そのものだと解してよいくらいである。すなわち兵衛そのものを左右し、外交を支配し、経済を指導し、また戦争そのものの原因を作っているのであるが、この点については未だ研究の足らない所が多々あるのである。
しからば思想がどういう風に兵衛そのものを変化せしめ指導しているかというと、一例をあげれば、孫子も戦争をするには五つの事が一番大事であると申している。すなわち第一に道と言うことを挙げている。その道とは今日でいうといわゆる大義名分、戦の旗幟であってこれが一番大事であると言っている。次に時、いかなる時機に戦うかということ、それから地の利、つまりどういう所で戦うかということ、その次には将を選ぶことの大事であるということを説き、最後に法ということを挙げている。法とは今日でいう戦術である。しかしてこの五つのうちどの点に重きを置くかということは、その時の政府首脳者や軍の統率者の思想によって変わってくるのである。
一番大事な大義名分を忘れて、むやみに地の利や開戦の時機ばかりを焦って戦を始める者もあり、大義名分が立派でなければ戦争をせぬ者もあり、また戦争の時機も土地柄も構わず戦術さへ巧みにやれば勝つと思って無理に戦を指導する者もある。それらはすべてその時の当事者や首脳部や乃至は一般の思想によって決定される。
さらに委(くわ)しくいうと、いわゆる、正攻法を重んじこれを主として戦をするか、または奇襲を主体として戦うかというようなこともその時代の思想に支配せられているのであって、…時代の兵衛の洋式も、または国防そのものの観念洋式も、あるいは建艦の洋式も、即ち主力艦を主とするか、潜水艦や飛行機に重きを置くかということも、また軍隊の教育も編成も訓練の仕方もすべてこれが支配を受けるのである。
外交にしても同様であって、現に防共協定などといってこれを現代日本の外交の枢軸であるかのように言っている如く、明らかに思想が中心になって外交が行われていることはすでに周知の事実である。またその樽俎折衝(そんそせっしょう:宴会などで和やかに折衝すること)の方法にしても、やはり思想によって変化する。即ち誠実にやるか、自主的にやるか、あるいはペテン外交をやるかという事もみな思想の支配を受けるのである。
次に経済の如きももちろんである。即ち自由主義の下における資本主義経済、あるいは共産主義の下における極端なる国家管理、統制経済、あるいはファシズムの下における全体主義というようなわけで、思想そのものが完全に経済の形態原則を支配しているのである。かくのごとくに思想そのものが戦争を支配し、兵衛を支配し、外交を支配し、経済を指導しているのであるから、近代戦の特徴は武力戦のほかに思想戦、外交戦あるいは経済戦であるというよりも、むしろ近代戦は思想戦だと言ってもよいくらいであるのである。
(真崎勝次 著『非常時局読本』慶文社 昭和14年刊 p.1~6)
真崎はこう記した後、大正十年(1921年)頃に支那事変(日中戦争)が避けられないと考えるようになったという。その理由は、その年のワシントン軍縮会議において主力艦の保有比率が英米各5、日本3とすることが決定されると、ロシア人やシナ人が急にわが国を軽蔑するようになったのだそうだ。日本人は駄目じゃないことを彼らに示さねば将来ロシアやシナに何もできなくなると考えたが、日本人の思想もどういうわけか大きく変わってしまった。
日本人の中にも一人一人ではシナ人やロシア人に負けるものが沢山あるから、駄目でないことを示すには、わが国体を基調とする全国民の団結力になる題なる力を以て彼らに一撃を食らわして反省を促さなければ、このままの和平交渉では徒らに彼らを増長せしむるのみであると考えたのである。また彼らは、その時分から日本人の思想も大分赤化してほとんど胸の辺まで真っ赤となって来たから、日本を崩壊に導くことはただ時機の問題だなどと言っておった者もあり、昭和の初めころには日本の軍隊の赤化工作も略々目的を達したなどと、彼らの密偵達の報告もあり、また新聞の記事にもあったのである。
次にいよいよ第一次ロンドン会議が行われるに及んで、益々彼らは増長して軽蔑し始めたのである。かくのごとく彼らは日本人よりも却って著しく日本人の思想の動向や内部の情勢について注意し、常に一喜一憂を感じておったのである。今回の事変(日中戦争)の数年前、シナ人中には日本人の最も特徴である国体観念につき、既に昔日ほどではなく、したがって国民の団結力もさほどではなく恐れるに足らずとして軽蔑的の言葉を弄していた者もあったのである。以上によって明らかなるが如く今次事変の原因は、一口に言うと欧米の自由主義ないし共産主義と日本精神との衝突であり、特に日本人が日本精神を失ったというところに帰着するのである。それであるから、この事件を解決するためにもまず日本人が日本精神に還るということが何よりも先決問題であり、何よりも重大事件であるのである。
(同上書 p.9~11)
以前別のブログに書いたことがあるのだが、昭和初期には学生や軍部に共産主義思想が蔓延していたのである。レーニンの『敗戦革命論』にもとづき、共産主義者は進んで軍に入隊し、「軍隊を内部から崩壊させ」「自国政府の敗北を助成」せよと指導されていたのである。
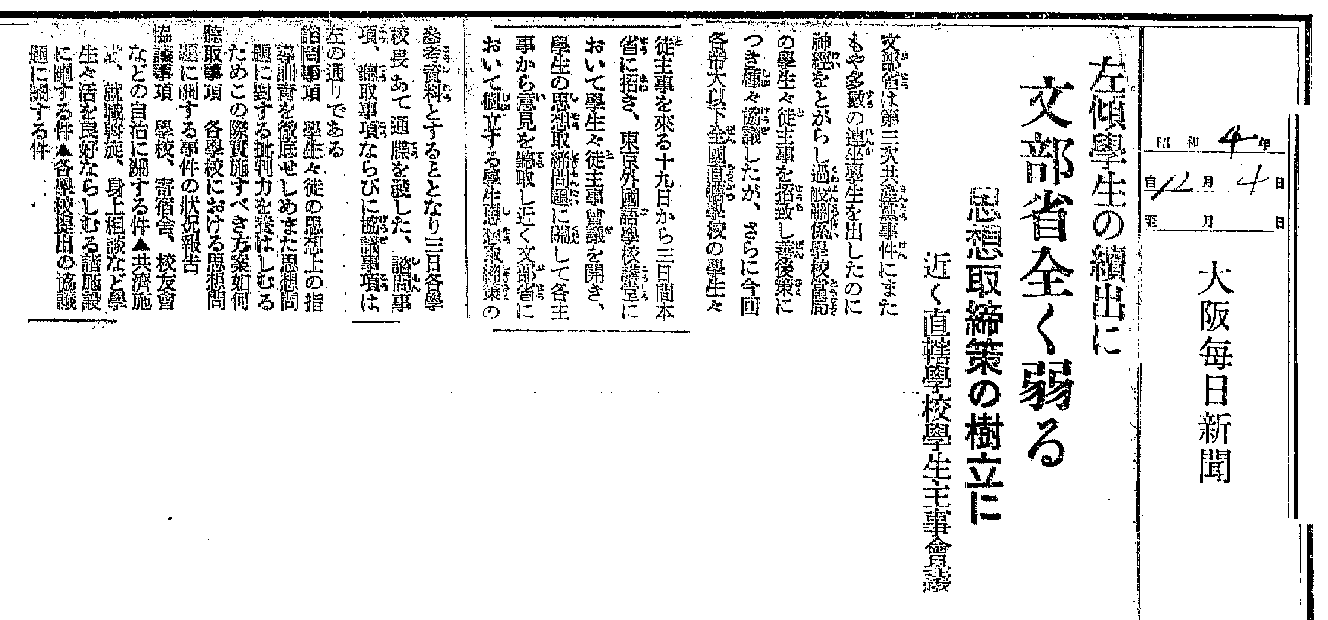
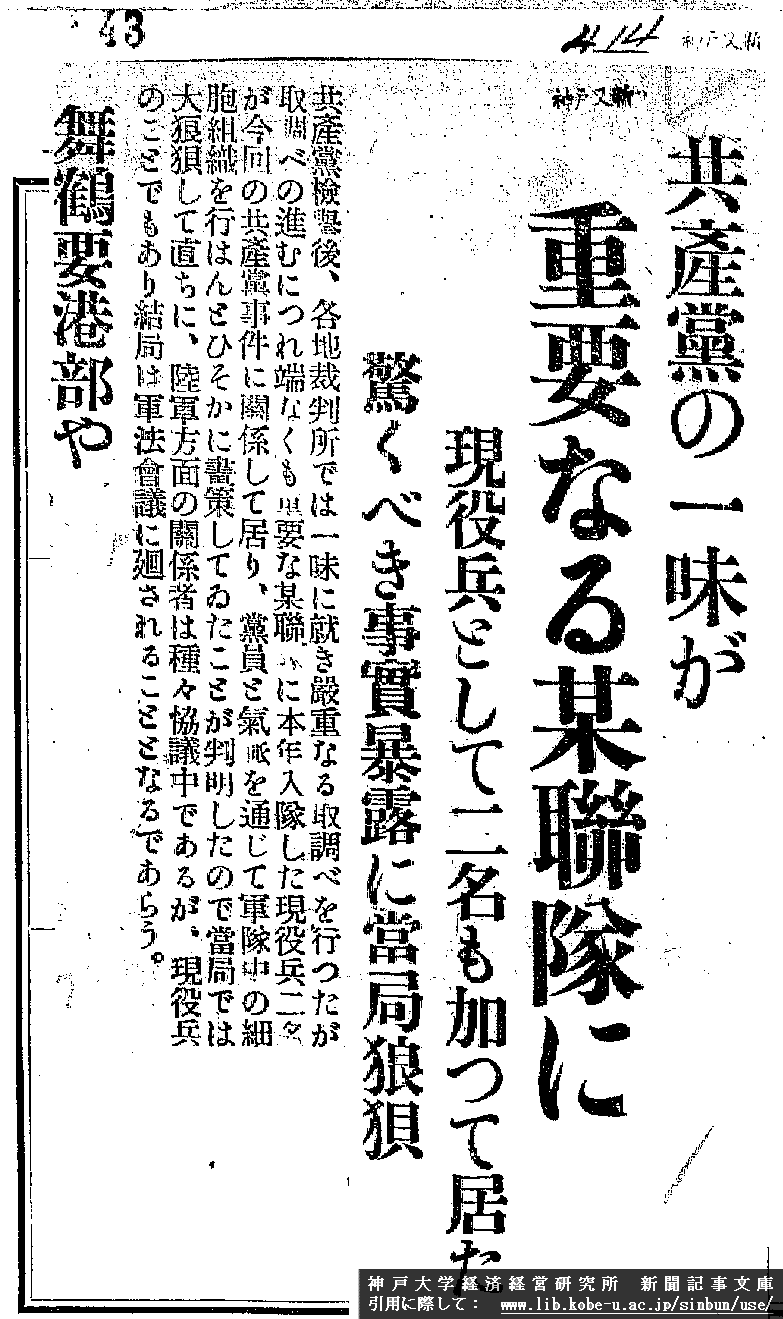
上の記事は昭和三年四月十四日の神戸又新日報の記事だが、第六回のコミンテルン大会が開かれる三ヶ月以上前のものである。第六回のコミンテルン大会では、共産主義者は「列強国同士が戦う状況になれば、戦争に反対するのではなく、戦争によって自国政府が敗北し崩壊に向かわせて、プロレタリア革命を遂行せよ」という決議がなされ、積極的に軍隊に入隊することを指令していたのだが、それよりもかなり前から日本軍の赤化工作が開始されていたことになる。この記事には海軍にも浸透工作が行われていたことが記されているので、興味のある方は読まれることをお勧めしたい。
同様な記事は神戸大学の新聞記事文庫で「軍隊 赤化」「軍隊 共産」などで検索すればかなりの数がヒットするので、見出しから絞っていけば、戦後の日本人には知らされていない内容の記事を数多く見つけることができる。
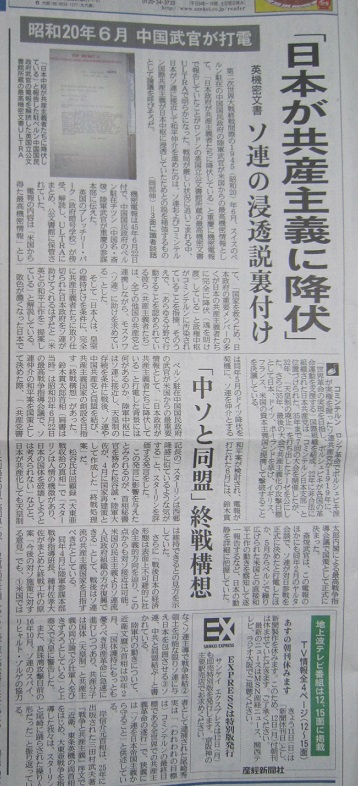
日本軍の暴走はコミンテルン(国際共産主義運動の指導組織)の工作に基づくものである可能性が高いということになるのだが、終戦の年の六月に、スイスのベルン駐在の中国国民政府の陸軍武官が米国からの最高機密情報として『日本政府が共産主義者達に降伏している』と重慶に機密電報で報告していたことがロンドンの英国立公文書館所蔵の最高機密文書に残されている。日本軍の中によほど共産主義主義者がいないと、終戦の日に天皇の玉音放送のレコードを奪おうとした終戦クーデターは理解不能で、彼らはソ連が日本を占領するまでは終戦させてはいけないと考えていたと理解すべきだと思う。そのような歴史理解は、最近江崎道朗氏が紹介しておられる、最新の欧米の第二次世界大戦に関する研究と全く矛盾しないのである。
下記のリストは、GHQ焚書のリストの中から、軍人が書いたと思われる著書を抽出し、著者の五十音順に並べたものである。全部で165点見つかり、そのうち85点が「国立国会図書館デジタルコレクション」でネット公開されている。
GHQ焚書のリストには知らない著者名が多いため、抽出洩れがかなりあるかもしれないが、読者のみなさんの力を借りて、できるだけ修正していきたいので、ご協力のほどよろしくお願いします。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


ブログ活動10年目の節目に当たり、前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しています。
通説ではほとんど無視されていますが、キリスト教伝来以降ポルトガルやスペインがわが国を植民地にする意志を持っていたことは当時の記録を読めば明らかです。キリスト教が広められるとともに多くの寺や神社が破壊され、多くの日本人が海外に奴隷に売られ、長崎などの日本の領土がイエズス会などに奪われていったのですが、当時の為政者たちはいかにして西洋の侵略からわが国を守ろうとしたのかという視点で、鉄砲伝来から鎖国に至るまでの約100年の歴史をまとめた内容になっています。
読んで頂ければ通説が何を隠そうとしているのかがお分かりになると思います。興味のある方は是非ご一読ください。
無名の著者ゆえ一般の書店で店頭にはあまり置かれていませんが、お取り寄せは全国どこの書店でも可能です。もちろんネットでも購入ができます。
電子書籍もKindle、楽天Koboより販売しています。
Kindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことが可能です。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。







コメント