前回記事で、コミンテルン(1919年にレーニンの指導のもとに創立された共産党の国際組織)による日本赤化(共産主義化)工作が進み、昭和七年に五・一五事件が起きた記事までを紹介した。赤化工作は軍部と青年に向けて重点的に行われていたのだが、対策を講じても青年の赤化は進んでいった。

「師範学校」というのは戦前のわが国の初等・中等学校教員の養成学校であったが、都下小学教員の間に強力な極左組織網が存在していることが明るみに出て四十名が検挙されたことが報じられている。赤化工作を仕掛ける側からすれば、青年に対する工作は師範学校が重要なターゲットにされたことは、当然のことだと思う。
その過半数を出している豊島師範学校では現在の師範教育制度を再吟味した結果、赤化教員の多くは若年者で在学中は大多数自宅その他から通学していた生徒なることが判明した。その結果今後通学許可制度を撤廃し原則として生徒を附属寄宿舎に強制入舎せしめることに方針を決定。取りあえず一月から断然実施すると共に来春四月よりの新入学生に対しては何れも寄宿会に入舎を厳格な条件として入学を許すことになった。
昭和7年12月15日 報知新聞 所蔵:神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫
このように、最も多くの赤化教員を出した豊島師範学校では自宅通学者が狙われたことから、翌月から全員寄宿舎に入れて外部との接触ができないようにしようとしたのだが、「現在通学生中には毎月補給される十一円を家計費に繰入れている切実な人達もあるので、それらの人々としては寄宿舎に入れば当然なくなるので気の毒なわけです」という理由で強制はできなかったようである。

日本共産党(コミンテルン日本支部)中央執行委員長佐野学、中央執行委員鍋山貞親は昭和7年11月に東京地裁で治安維持法違反により無期懲役を宣言され服役していたが、この巨頭二人が昭和8年6月7日に獄舎から弁護士らに宛てて、コミンテルンのやり方は誤っており、「以降コミンテルンとの縁を切って日本を中心とする一国的社会主義の建設を明確な目標として再編成さるべきである」という内容の速達を送付したことが報じられている。新聞などでは「思想の転向」などという活字が躍っているが、決して保守思想に転じたわけではない。
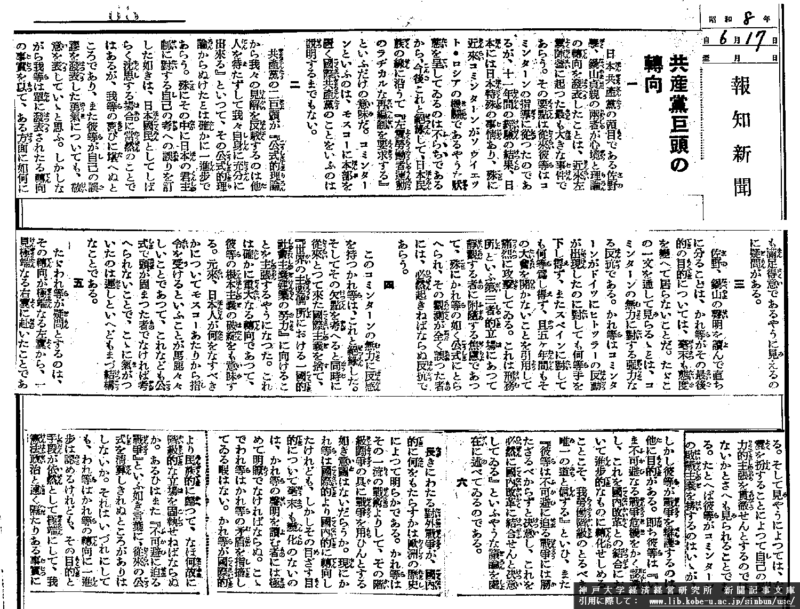
報知新聞は両巨頭の転向声明を次のように伝えている。
三 佐野、鍋山の声明を読んで直ちに分ることは、かれ等がその最後的の目的については、毫末も態度を変えて居らないことだ。ただこの一文を通して見らるることは、コミンターン*の無力に対する強力なる反抗である。かれ等はコミンターンがドイツにヒトッラーの反動が出現したのに対しても何等手を下し得ず、またスペインに対しても何等為し得ず、且五ヶ年間もその大会を開かないことを引用して痛烈に攻撃している。これは刑務所という第三者的立場にあって静観する者に附随する焦慮であって、殊にかれ等の如く公式にとらえられ、その観測が全く誤った者には、必然起きねばならぬ反抗であろう。
*コミンターン:コミンテルンのこと四 このコミンターンの無力に反感を持つかれ等は、これと絶縁した。そしてその欠点を考えると同時に従来とって来た国際主義を捨て、『世界の主要個所における一国的社会主義建築の努力』に向けることを主張するようになった。これは確かに重大なる転向であって、彼等の根本主義の破綻をも意味する。元来、日本人が何をなすべきかについてモスコーあたりから指令を受けるということが馬鹿々々しいことであって、これなども公式で頭が固まった者でなければ考えられないことで、ここに気がついたのは遅しといえどもまず結構なことである。
五 ただわれ等が疑問とするのは、その転向が極端なる左翼から、一見極端なる右翼に赴いたことである。そして見ようによっては、右翼を紛することによって自己の暴力的主張を貫徹せんとするのではないかとさえも見られることである。たとえば彼等がコミンターンの敗戦主義を排するのはいいが、しかし彼等が戦争を弁護するのは他に目的がある。即ち彼等は『いま不可避なる戦争危機をかく認識し、これを国内改革との結合において進歩的なものに転化せしめることこそ、我労働階級のとるべき唯一の道と信ずる』といい、また『彼等は不可避に迫る戦争には勝たざるべからずと決意し、これを必然に国内改革に結合せんと決意している』というような議論を処在に述べているのである。
六 長きにわたる対外戦争が、国内的に何をもたらすかは欧洲の歴史によって明らかである。かれ等はその一流の戦術よりして、その階級闘争の具に戦争を用いんとする如き意図はないだろうか。現にかれ等は国際的より国内的に転向したけれども、しかしその目ざす目的について毫末も変化のないのは、かれ等の声明を読む者には極めて明瞭でなければならぬ。ここでわれ等はかれ等の矛盾を指摘している暇はない。かれ等が国際的より民族的に帰って、なお何故に階級的な立場を固執せねばならぬか。あるいはまた『不可避に迫る戦争』という如き言葉に、従来の公式を清算しきれぬところがありはしないか。それはいずれにしても、われ等輪はかれ等の転向に一進歩は認めるけれども、その目的と手段が依然として極端にして、我憲法政治と遠く隔たりある事実に鑑み、不用意、無条件に賛意を表する如きことなきを希望せざるを得ない。
昭和8年6月17日 報知新聞 所蔵;神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫
両巨頭に続いて500人以上に上る大量の集団転向が行われたのだが、多くのメンバーは戦争を通じて革命を実現するという夢を捨てていなかったと思われる。一方、転向を拒否する党員も多くいて、日本共産党の活動は地下に潜るようになっていった。
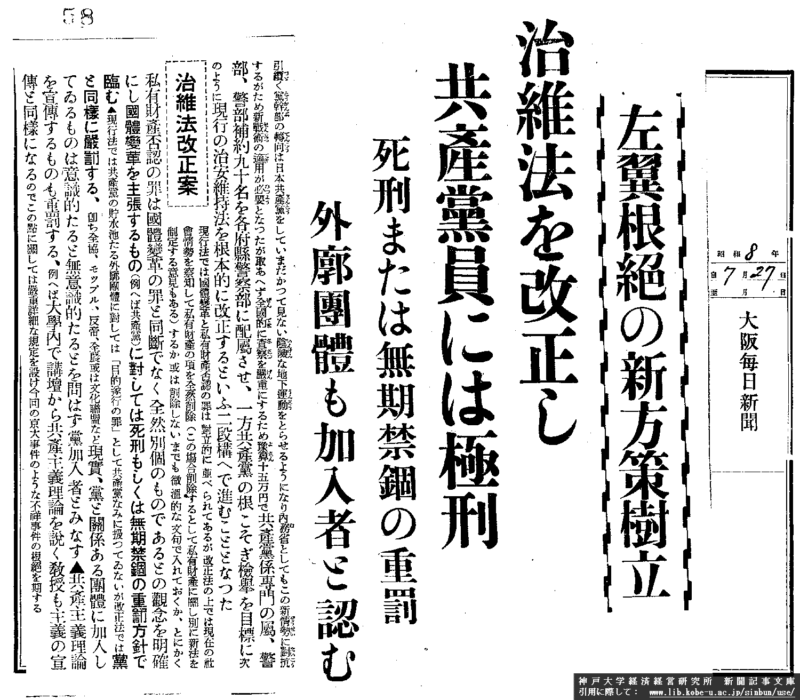
引続く党幹部の転向は日本共産党をしていまだかつて見ない陰険な地下運動をとらせるようになり、内務省としてもこの新情勢に対抗するがため新戦術の適用が必要となったが、取あえず全国的に査察を厳重にするため予算十五万円で共産党係専門の属、警部、警部補約九十名を各府県警察部に配属させ、一方共産党の根こそぎ検挙を目標に次のように現行の治安維持法を根本的に改正するという二段構えで進むこととなった。
昭和8年7月27日 大阪毎日新聞 所蔵:神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫
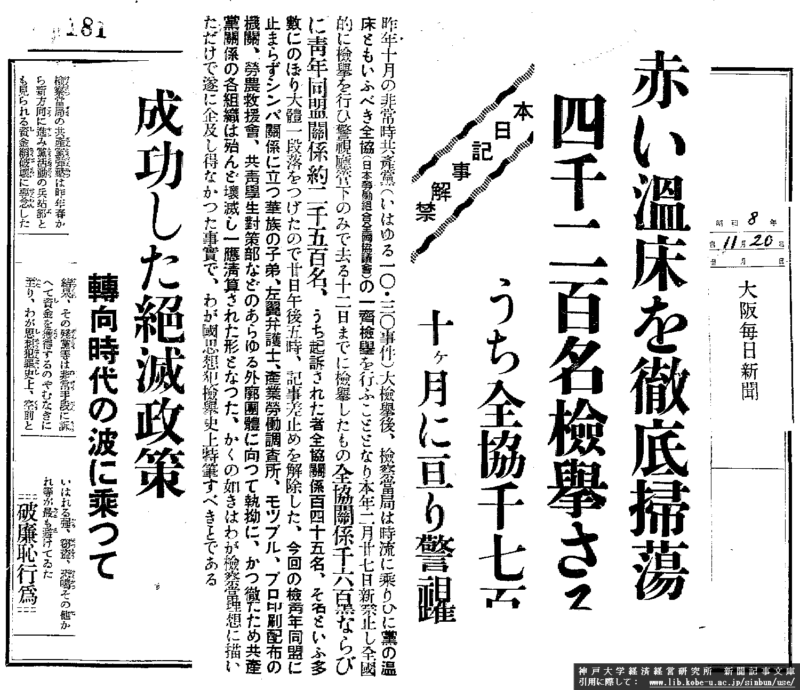
検察当局の共産党弾圧は昨年春から新方向に進み、党活動の兵站部とも見られる資金網破壊に専念した結果、その残党等は非常手段に訴えて資金を獲得するのやむなきに至り、わが思想犯罪史上、空前といわゆる強、窃盗、恐喝その他かれ等が最も避けていた破廉恥行為を敢てするに至り、これらが端緒となって昨年十月三十日の全国的大検挙を見るに至ったが、当局は従来大検挙の後の気のゆるみから、その間隙に乗じ残党をして再組織の余裕を与え、しばしば失敗している苦い経験に鑑み全国的に直ちに追撃戦に移らしめた。これがため昨年末から本年初頭にかけ検挙洩れの捕えられるものも多かったが一面全協が永年隠秘していた○○○廃止の看板を掲げ、その運動も積極的となり従来の温床的態度を捨てて進んで党中央部再建のために狂奔するなど殆ど党と運動上の地位を顛倒するに至り、従来の取締方針では目的が達せられなくなったので、断然治安維持法第一条第一項を適用して大々的に検挙しさらに五月には党再建の中央部、共産青年同盟中央部、華族の子弟その他に向って弾圧の歩を進め十一月に入っては殆ど左翼運動者の息の根を止めるまでに終息せしめることが出来た。
昭和8年11月20日 大阪毎日新聞 所蔵:神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫
転向できずに日本共産党に残ったメンバーは地下に潜ったが徹底的に掃討されて、この記事では「殆ど左翼運動者の息の根を止め」たかのように記されているが、獄中での両巨頭の声明に動かされて合法でなければならぬという考え方が広がったことの影響は小さくなく、「左翼運動者」の多くは、その後「合法的」に活動を続けようとした。

昭和九年四月に開かれた日本共産党満州事務局の党員二十一名の公判で、裁判長より共産主義についての現在の心境を問われて、首領の松崎被告は次のように答えたという記事が出ている。文中の「コムミンターン」は「コミンテルン」と同義である。
第一に世界の主要個所に於ては一国的な社会主義の建設は必要である、第二に一国社会主義には各国の個別的なる特殊条件が非常な力を持っていることは絶対に信ずる、第三に日本、満洲、支那を含む東洋全般に対し日本を中心とした東洋独自の社会主義を建設することは可能であると思う、第四に民族、国民性の重要なることを感ずる、第五にコムミンターンを離れた労働階級の独創的な総意による指導権を獲得すべきだと思う、最後に前衛機関の結合は絶対必要である、
昭和9年4月6日 満州日報 所蔵:神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫
と従来の日本共産党が奉じていた思想と全然異った一国社会主義を述べ、更に
日本に於ては君主制は日本の過去現在は勿論、将来に於いても絶対に大きな力を持っていることを信ずる、コムミンターンは日本が持つ絶対的勢力君主制と徹底的に闘争せよと命じているがこれは大きな認識不足で、共産党の形式は日本では全く駄目である、来るべき日本の社会改革は天皇を中心として民族的統一と、労働階級の大いなる力を確立することによってのみ行われるのである、
と全般共産主義を離れた国家社会主義理論の概括的陳述を行い、明確に転向を表明した。かくて首領松崎の陳述は午後二時三十分終了して、十分間休憩後同じく獄中被告広瀬進の陳述に移ったが、対共産主義意向に関しては全く松崎と同意見であると述べ、更に補助的に先ず日本の社会経済制度の発展段階を述べた後
一国社会主義はその内容に於て当然国家社会主義の色彩を多分に含まねば成功しない、この点より日本に於ける一国社会主義は当然皇室中心によって派生して来なければならない
と松崎同様転向を明言…
当時に於いて、共産主義者が「天皇制」を否定しない言動は「転向」したと評価されていたようだが、彼らにとって「天皇制」とは、一般の国民の理解しているものとは異なっていたのではなかったか。『ビルマの竪琴』の著者・竹山道雄は昭和初期の状況をこう記している。
インテリの間には左翼思想が風靡して、昭和の初めには『赤にあらずんば人にあらず』というふうだった。指導的な思想雑誌はこれによって占められていた。若い世代は完全に政治化した。しかしインテリは武器を持っていなかったから、その運動は弾圧されてしまった。
竹山道雄『『昭和の精神史』講談社学術文庫p45-47
あの風潮が兵営の厚い壁を浸透して、その中の武器を持っている人々に反映し、その型にしたがって変形したことは、むしろ自然だった。その人々は、もはや軍人としてではなく、政治家として行動した。すでに北一輝などの経典があって、国体に関する特別な観念を作り上げていて、国体と社会改造とは背馳するものではなかった。しかし、北一輝だけでは、うたがいもなく純真で忠誠な軍人をして、上官を批判し軍律を紊(みだ)り世論に迷い政治に関与させることは、できなかったに違いない。…いかに背後に陰謀的な旧式右翼がいたところで、それだけで若い軍人が『青年将校』となることはありえなかった。これを激発させたのは社会の機運だった。このことは、前の檄文*の内容が雄弁に語っている。
*五・一五事件の檄文
…
青年将校たちは軍人の子弟が多く、そうでない者もおおむね中産階級の出身で、自分は農民でも労働者でもなかった。それが政治化したのは、社会の不正を憎み苦しんでいる人々に同情する熱情からだった。インテリの動機とほぼ同じだった。ただ、インテリは天皇と祖国を否定したが、国防に任ずる将校たちは肯定した。ただし、彼らが肯定した天皇と国体は、既成現存の『天皇制』のそれではなかった。
竹山の表現を借りると、青年将校たちは「天皇によって『天皇制』を仆(たお)そうとした」、「革新派の軍人が考えていた『国体』は、『天皇制』とはあべこべのものだった」ということだが、竹山が知る青年将校は、『天皇制』は認めても「天皇」というポストに就くべき人物は昭和天皇ではなく、スターリンのような人物を考えていたというのである。
戦後の歴史教育では『軍国主義』を恐ろしいものとして何度も教えられてきたが、よくよく考えると「軍」という組織は、国民の生命と財産を護る存在である限りは怖ろしいものではありえない。
いつの時代であっても、またどこの国にとっても、「軍」が恐ろしい存在となるのは、その組織の中に、他国の為に動こうとしたり、革命を夢見て権力を掌握しようとするメンバーが存在し、その目的のために組織的に武力を用いる意思を持つようになった場合であろう。軍部が暴走していったのは、軍部が右傾化したからではなく、実質的に左傾化が進んでいったからではなかったか。
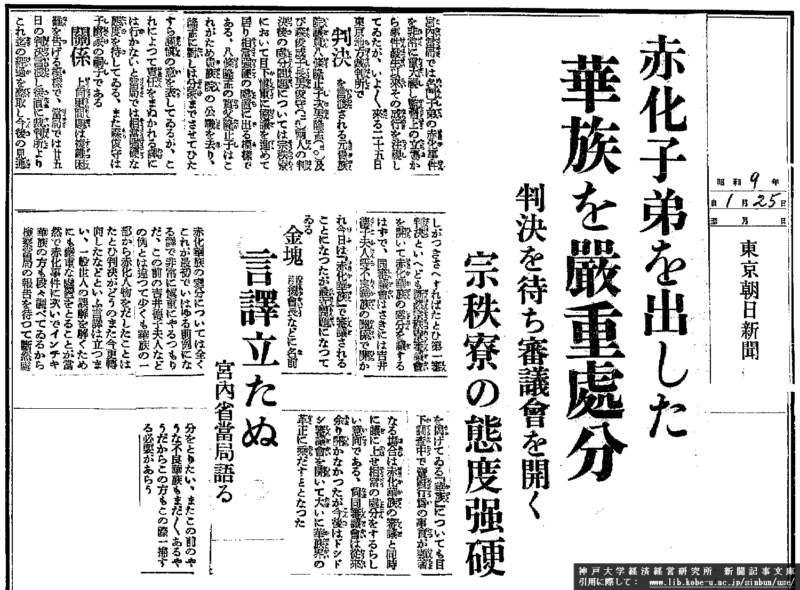
赤化工作は華族にも及んでいたのだが、友人・知人を媒介として宮家や天皇の親族まで共産主義思想を浸透させていく工作が行われていた可能性がある。「しんぶん赤旗」によると、昭和八年に昭和天皇侍従の子弟を含む10名の華族が治安維持法で検挙され、ほかにも同様な思想を抱く華族がいたという。もし将来天皇となりうる人物に左翼思想を信奉させることに成功すれば、「天皇を中心とする社会主義国家の建設」、あるいは天皇制の破壊の道筋が見えてくるとの考えがあったのではなかったか。そういえば、「赤い宮様」と呼ばれた皇族がおられたという話もあるようだ。

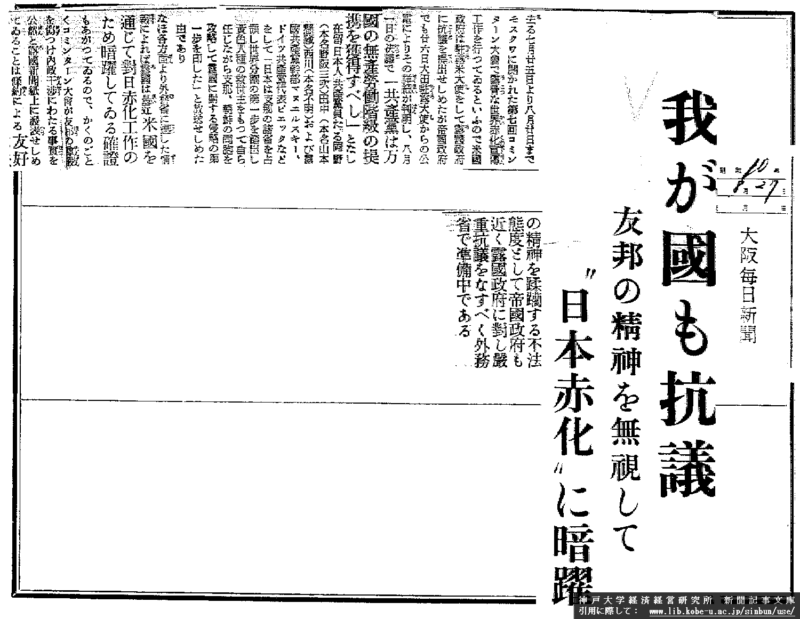
両巨頭がコミンテルンと縁を切ると宣言して以降取締りか強化されて以降、日本共産党の組織は壊滅的状態となっていったのだが、ソ連のわが国に対する赤化工作はその後も途切れることなく続けられていたことを知るべきである。ソ連は日本共産党は壊滅したようにみせながら、工作資金を「転向」したとされるメンバーに向けていたのではなかったか。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


【ブログ内検索】
大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。
前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。
全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。
電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。
またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。
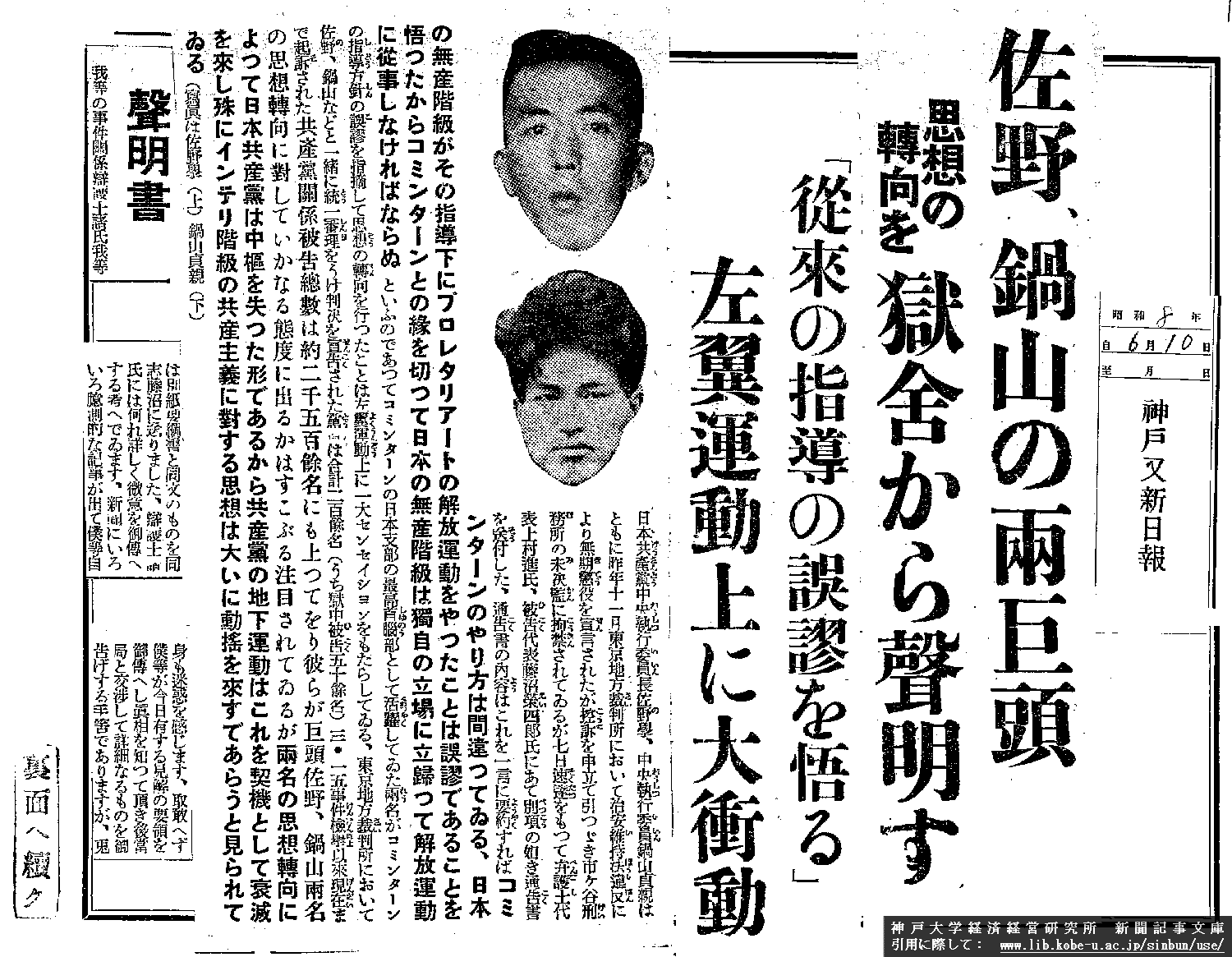


コメント