日貨排斥を煽動したのはやはり英米の宣教師
中国の排日運動はまもなく日本製商品の排除に動き出している。教科書などではサラッと書かれているが、実態はかなり酷いものであった。当時の状況は各紙が英米の宣教師が背後で動いていたことを報じている。五四運動から約一ヶ月後の大正八年(1919年)六月六日に報じられた神戸新聞の記事を紹介しよう。
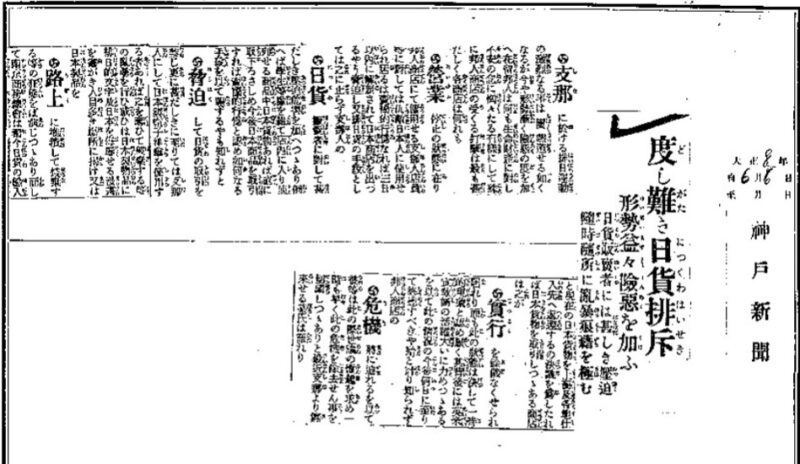
支那に於ける排日運動の激烈なる事は屡(しばしば)報道せる如くなるが、今や形勢漸(ようや)く険悪の度を加え、在留邦人は何も生命財産に対し不安の念に恟々たる有様にして、殊に邦人商店の受くる打撃は最も甚だしく、各商店は何れも営業停止の状態に在り。
邦人商店にて傭用せる支那人店員等に対しては、仇敵日本人に使用せられ居るは売国的行為なれば、三日以内に解雇されて日本商店を出づるよう脅迫し、又排日貨の手段としては之に止らず、支那人の日貨販売者に対して甚だしき圧迫危害を加えつつあり。
例えば学生等隊を組て店内に入り、陳列せる商品中日本貨物あれば直に取下ろさしめ、今後日本商品を取引すれば売国的行為と認め、如何なる手段を以て報ずるやも知れずと脅迫して日貨の取引を禁じ、更に甚だしきに至りては、支那人にして日本製帽子洋傘を使用する者あれば、之を奪いて破棄する等の乱暴を行い、或いは日本製物品に排日的文字及日本を侮辱せる漫画を画き、人目多き場所に掲げ又は日本製品を路上に堆積して焼棄する等狂態を演じつつあり。
而して南京商務総会は爾今日貨の輸入と現在の日本貨物を上海及各地仕入先へ返還するの決議を為したれば、日本貨物を取引しつつある商店は之が実行を余儀なくせられ居れり。而も此の状態は決して一時的現象と認め難く、其背後には英米宣教師の活躍大いに力めつつあるを以て、此の情況の今後何日に至りて終熄すべきや殆ど計り知られず。邦人商店の危機将(まさ)に迫れるを以て彼等は此の際世論の憤起を求め、一時も早く此の危機を除去せん事を切望しつつありと最近支那より帰来せる某氏は語れり。
大正8年6月6日 神戸新聞 神戸大学新聞記事文庫 外交23-101
この日貨排斥運動で乱暴行為を働いたのは学生が多かったようだが、その背後に英米の宣教師がいたという戦勝国にとって都合の悪い真実は、戦後の歴史叙述からはスッポリと抜け落ちている。
日貨排斥が日中貿易に与えた影響
「日貨排斥」とは、ただ日本商品を排斥するというだけではなかった。中国に進出した日本企業には多くの中国人が雇用されていたのだが、彼らは仕事をサボったり、日本商品を取扱うことを拒否したりしたという。同年六月十一日の大阪朝日新聞は次のように報じている。
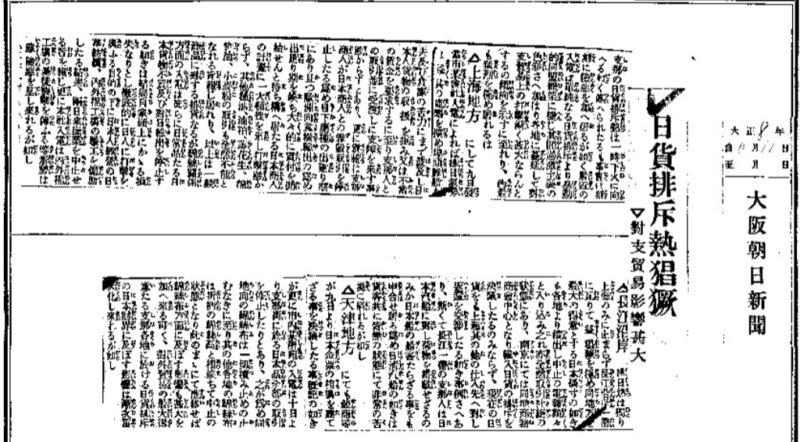
支那の日貨排斥熱は一時下火に向える如く伝えられたるも、事実は刻刻に険悪を加え居るが如く、最近の入電は単純なる日貨排斥より暴動的同盟罷業に変じ、其間過激主義の色彩さえ加わり、各地に蔓延して対支貿易上の打撃漸く甚大ならんとするの傾向を示すに至れり。内最も猛烈を極め居れるは上海地方にして、九日発当市某会社入電によれば排日気勢は益々他の範囲を拡め、埠頭艀船人夫及び倉庫の苦力にまで波及し、日本人貨物の取扱を拒み又は不当の賃金を要求するに至り、支那人との取引並に受渡しに支障を来す事少からずとあり。
更に別報は支那商人は日本商人との雑穀取引を停止したる為め、目下薬種の出廻り期にあり且つ欧洲向食糧輸出の為め出廻り期を竢ち大々的に買付を開始せんと待ち構え居たる日本商人の計画に一大頓挫を来し、打撃少からず。 其他種油、油粕、落花生、棉実油、小麦粉の取引も全然不能となれる旨報じ居れり。以上は一般商品に対する排貨なるが、綿糸関係方面の入電は徒らに日常品たる日本貨物不買及び対日輸出を停止する如きは結局自家頭上にかかる損失なりとし、徹底的に日人に打撃を与うる目的の下に日本人経営の日華紡績、内外棉工場の職工を煽動したる結果、連日来操業を中止せる旨を報じ更に本社入電は内外棉工場の某と襲撃を伝うる等形勢は愈険悪を呈し来れるが如し。
長江沿岸排日熱は独り上海のみに止まらず長江沿岸一帯に亙りて益々猖獗を極め、同地方を最大の得意とする日本燐寸の如きも各地より積出し中止の電報頻々と入り込み、之れ亦全然取引杜絶の状態にあり。南京にては同地商務商会中心となり輸入日貨の排斥を決議したるのみならず、現在の日貨をも上海其の他の仕入先へ対し返還を交渉したる如き事例さえあり、斯くて長江一帯の支那人は日本汽船に対し荷物を搭載せざるのみか、日本船の船客たらざる事をも申合せ居る為め、日清汽船の如きは貨客共に皆無の状態にて非常の苦境に陥れるが如し…
当時の中国の最大の貿易相手国は日本であったのだが、こんな活動が続けられていたら、これまで中国市場で取り扱われていた日本商品の売れ行きがどんどん悪くなって当然である。同年六月十七日の報知新聞に八木商事の課長のこんな談話が出ている。
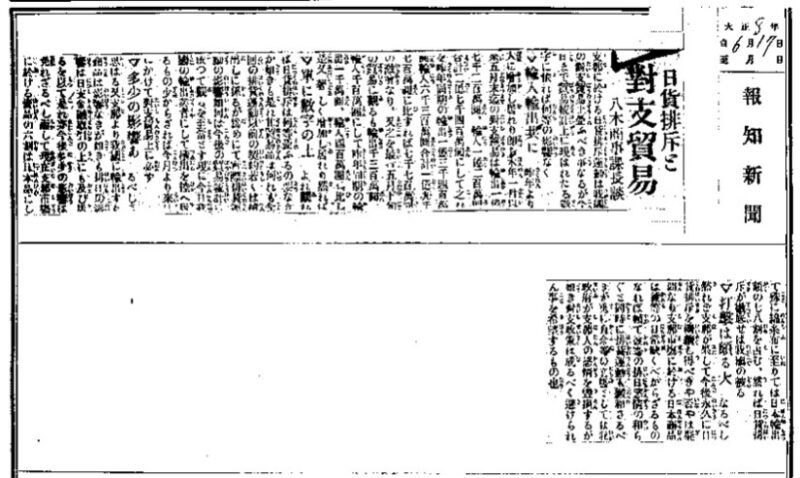
実際排貨運動の影響如何は今後の貿易統計に依って観るを至当とす。現に今日我国の輸出業者にして積出を控え居るもの少からざれば、今月より来月にかけて対支貿易上に必ず多少の影響あるべしと思わる。又支那より我国に輸出する商品は影響なきが如きも、排日の影響は日支金融取引の上にも及び居るを以て是れ亦今後多少の影響は免れざるべし。
而して現在支那市場に於ける買品の六割は日本品にして殊に綿糸布に至りては日本輸出額の七八割を占む。然れば日貨排斥が徹底せば我国の被る打撃は頗る大なるべし。
然れど支那が果して今後永久に日貨排斥を継続し得べきや否やは疑問なり。支那市場に於ける日本商品は彼等の日常欠くべからざるものなれば、幀て彼等の排日感情の和らぐと同時に排貨運動も緩和さるべきが、兎に角余等の立場としては我政府が支那人の感情を毀損するが如き対支政策は成るべく避けられん事を希望するもの也。
大正8年6月17日 報知新聞 神戸大学新聞記事文庫 外交23-168
中国の輸入品の六割は日本で、そのうち綿布については七~八割は日本からであったのだが、生活必需品が多かったので日貨排斥は長くは続かないと予想し、政府が中国人を刺激するような対支政策をとらないことを希望しているのだが、このような認識は甘すぎたと言わざるを得ない。
日本政府が宣伝戦の対策を講じなかったのは何故か
当時のわが国の内閣は本格的政党内閣と言われた原敬内閣であったのだが、中国を刺激するような施策をとらなかった。英米の宣伝工作に対抗してわが国も中国に対する宣伝が必要であることを、早くから主張した新聞社もあった。例えば同年六月二十二日の京都日出新聞には次のように記されている。
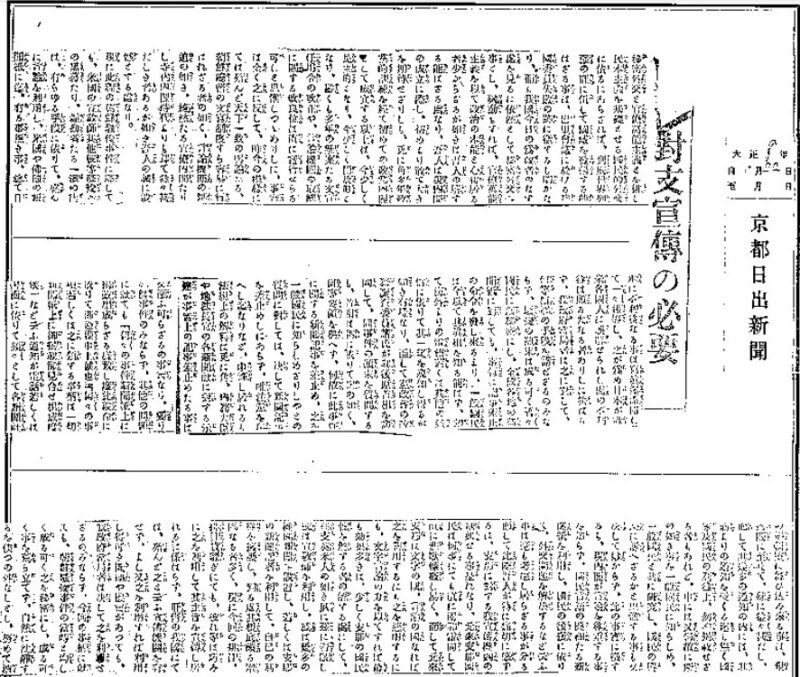
吾人が特に痛切に感ずるは、支那に対する我宣伝機関の欠如せる事是れなり。元来支那国民は何事にても直に附和雷同して直に悲歌慷慨し易く、而して元来支那は文字の国、言論の国なれば之を善用するにも之を悪用するにも、文字言論の力を以てすれば最も効果多きは少しく支那の国民性を解する者の解する処にして、在支英米人の如き夙に茲に着眼し或は宣教師を利用し、或(あるい)は幾多の機関新聞を設置し、若(も)しくは支那の新聞記者を利用して、自己の利益を擁護し、到る処(ところ)其(その)根柢頗(すこぶ)る鞏固なる者多く、現に今回の排日、排日貨騒ぎにても、彼れ等は巧みに之を利用して其主旨を宣伝し居れるに係わらず、肝腎の我国にては、殆んど之と云う宣伝機関を有せず。
よし又之を利用すれば利用し得可き機関や機会があっても、我政府当局者は決して之を利用せざるのみならず、今回の事柄に就ても、朝鮮騒擾事件の当時と均しく成る可く之を秘密にし、成る可く事を荒ら立てず、自然に沈静するを俟(ま)つの外なしとし、努めて消極的の態度を取り、積極的に我国の真意の存する処を彼等支那国民若しくは第三者の前に宣伝し、彼等の誤解を解くなど云う事は毫(いささか)も考慮せざる者の如く、之が為め支那各地に在る我同胞の被る処の損失は決して少からず。何れも皆我政府の態度に慊焉(けんえん:不満足)たる者あり。…中略…
我帝国が東洋に於ける平和の維持者として、其最も関係深き支那国民の親善を保ち、支那国民の諒解を得んと欲せば、今に及んで最も完全にして最も有力なる宣伝機関を有する事は、最も緊急必要の案件たる可し。聞く処に依れば、満鉄及び台湾銀行の関係者其他在支実業家の有力者等にも、輓近益々其必要を感じ、寄り寄り其実行方法等に就き協議中なりと。之れ等の有力者に依りて此事の実行せらるるは、勿論吾人の希望して止まざる処なり。然れども之と同時に為政の局に当る者も、又区々たる対内政策にのみに没頭せず、党派党観念を捨て、此際我国民の真意を全支那国民に宣伝する計を講ずるは、当然の任務にして、若し当局者に一片の誠意あれば之を実行する又必ずしも困難の事業に非らざるなり。
大正八年六月二十二日 京都日出新聞 神戸大学新聞記事文庫 政治14-54
このような主張がされていたにもかかわらず、政府は動かなかったことは例えば同年十月三十一日の東京朝日新聞は次のように解説していることから想像がつく。
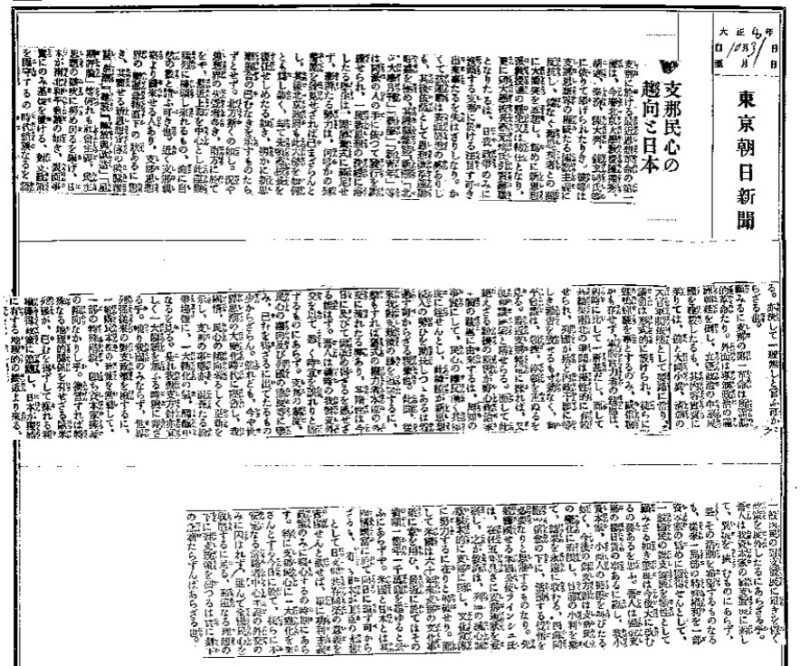
従来我対支政策の跡を追懐するに、動もすれば旧式の権力者本位の外交に流れたる幣あり。其隋性は今日に及びて尚改め得ざるを感ぜざる能わず。吾人は嚢時の我対支外交を以て悉く時宜を誤れりと断ずるものにあらず。支那の制度、民心の趨向及び列国の態度等に鑑み、已むを得ざるに出でたるもの少からざらん。
然れども、今や世界思潮の大変化時代に際会し、我国情、民心の傾向著るしく更新を示し支那の事態亦、混沌たる紛争場裏に、一大転化の気、醞醸(うんじょう:ある雰囲気が生まれ高まる)中なるを見る。是れ我対支方針亦(また)宜しく一大刷新を加うる時機に非ざる乎。唯り我国のみならず、世界列強従来の対支政策を検するに、一般国民本位の政策を無視して、一部の特殊階級、即ち資本家擁護の傾向なかりし乎。換言すれば特殊なる地理的関係を有せざる欧米列強が、已むを得ずして採れる利権獲得政策に追随し、日本が独特に有する地理的の接近より来る、一般国民の対支発展に重きを置く政策を度外したるにあらざる乎。吾人は我資本家の対支発展に対して、意義を挟むものにあらず、益その活動を希望するものなるも、従来一局部の特殊権利を一部資本家の為めに獲得せんとして、一般国民の対支発展を犠牲として顧みざる如き態度は今後大に改むるの要あるを思う。吾人は過般支那の排日貨の事あるに際し、我小資本家、小商人の擁護を叫びたる如く、今後の対支方針は支那民心の変化に着眼し、目前の小利を棄て、結果を永遠に収むる、四海同胞□信念の下に、活動する覚悟を必要なりとし思惟するものなり。
先般帰国せる米国公使ラインシュ氏は、在任五年具さに支那現状を査察し、之が救済は、列国の誠心誠意根本的に支那に対し、文化宣伝に努力するに在りと喝破せり。而して米国は六十年来支那の文化事業に意を用い、最近に於てはその費額一箇年一千万円を超えると云うにあらずや。米国と日本とは其国情国富に於て同日に論ず可からざるも、苟も日本が東亜の先進として日支間共存同栄の意義を実顕せんと欲せば、単に功利主義政策のみに腐心するの時期にあらず。特に支那民心に一大変化を来さんとする今日に於て、徒(いたずら)に不安定なる当路者中心主義の外交のみに囚われず、進んで全国民心を収攬するに足る、高遠なる理想の下に対支政策を樹つるは実に刻下の急務たらずんばあらざる也。
大正8年10月31日 東京朝日新聞 神戸大学新聞記事文庫 外交18-160
中国に多額の投資をしたり、売上高の多くを中国輸出に依存していた日本企業は、中国を刺激することを怖れていた。わが政府がこのような財界の意向を汲んだのか、これまでの対中政策に関与して来た官僚や先輩政治家に忖度したか、別の理由によるかは定かではないが、結局「我小資本家、小商人の擁護を叫びたる如く」の政策が続けられて米国による対支那工作をやりたい放題にやらせてしまったのではなかったか。わが国が世界から孤立していった原因のひとつはこのような対中政策にあったのだと思う。
今の政府も、中国に多額の投資をした大企業や、工場の中国移転を推進した官僚に忖度しているからか、中国に対する施策が他の主要国と比較して甘すぎるように思うのだが、このような「中国を刺激しない政策」の継続が、再びわが国を孤立化させる危険性はないのだろうか。中途半端な政策をとり続けて戦争に巻き込まれていった昭和の歴史を繰り返して欲しくないものだと思う。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


【ブログ内検索】
大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。
前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。長い間在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、このたび増刷が完了しました。
全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。
電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。
またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。


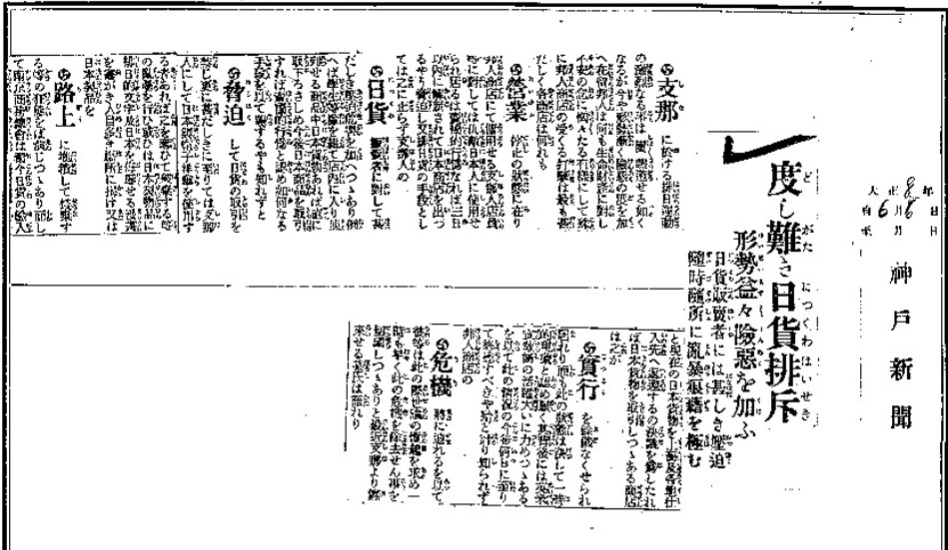




コメント