GHQ焚書リストの中から、本のタイトルに「詩」を含む本を絞り込むと、「詩集」が多いことは当然であるが、自らの戦争体験を綴った日本兵士の作品もあれば、ドイツ兵の詩集や、幕末の志士の詠んだ漢詩を集めて評釈している本、タイ国の風物詩など様々である。
『遠征と詩歌』
これまでこのブログで、日本軍兵士が戦場で詠んだ俳句や短歌を交えながら自らの戦争体験を綴った作品を紹介させていただいたが、今回は支那事変従軍中にある古典文学を持参したことが非常に役に立ったという『遠征と詩歌』という本の一部を紹介したい。
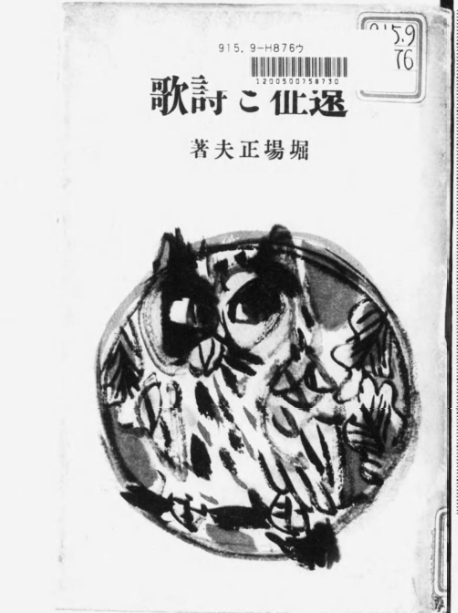
著者の堀場正夫に関する情報はネットで探しても殆んど出てこないが、昭和十六年に『悖徳者』という小説と『遠征記:富水渡河より武漢まで』という従軍記を書いている。『遠征記』に本人が記した序文によると、「名古屋新聞学芸部の行為によって、志願により従軍することになったのは昭和十三年八月下旬のことであった。当時情報部でも偶々文学者の従軍派遣のことが盛大にくわだてられた。(p.1)」とあり、彼は文学者として支那事変に従軍することを志願して派遣された一人のようである。また「彼の地では何かと御厄介になった久米正雄氏、深田久弥氏、佐藤惣之助氏、丹羽文雄氏と共に記して以て深甚の謝意を表する次第である。(p.4)」と記しているが、外にも石川達三、火野葦平、林芙美子、西城八十、草野心平など多くの作家や詩人や画家が従軍派遣されていたことが知られている。
堀場正夫の『遠征と詩歌』の一部を紹介させていただく。
従軍中萬葉集を携行し、揚子江の単調な船旅や戦線のつれづれに時折ポケットから取り出しては、実にこれまでなかった新鮮な感動をもって愛誦した。それも最小の計画ではいわば支那旅行案内書として唐詩選上下二巻だけ用意し、他は一切戦線の荷厄介になるのを避けるために携行しないことにしたのだったが、愈々武漢攻略戦に従軍するため内海の美しい港を出帆するにあたり、波止場へ向かう車の中で懐中電灯の必要を思いつきふいに車をとめた。そのついでに何気なく購入したものだったが、これが後になって非常に役立ったのである。ただ上海に登陸してから気が付いてみると、あの時は何しろ出航間際のこととて随分気がせいていたものとみえ、岩波本上下二巻のうち、下巻のみが訳文で、上巻は不覚にも白文だったのだから、折角の思いつきも半分だけで我慢しなければならぬという残念な結果になった。しかし、それでも半歳にわたる戦線彷徨中、唯一無二の友たることは失わなかったのである。
「今日よりは顧みなくておおきみの醜の御楯*」といで立つ人々が「おおきみの詔かしこみ磯に触り海原わたる父母をおきて」遠征に旅立つ時のあわただしい心事は、
水鳥の発の急ぎに父母にもの言わず来にて今ぞくやしき (有度部牛麿)
や、また、
防人に立たむ騒ぎに家の妹がなるべきことをいわず来ぬかも (若舎人部廣足)
など、古え、筑紫、壱岐、對島など西海道辺要の地を守備するため召集派遣された防人たちの歌がよく表している。まして武漢攻略戦と言えば国をあげての戦いであるばかりか、日本の歴史はじまって以来の大規模な遠征である。「大君の醜の御楯*」といでたつにしろ、はたまた、
草まくら旅の丸寝の紐絶えば吾が手とつけろこれの鍼持し
防人に行くは誰か夫ととう人を見るがともしさもの思いもせず
防人にたちし朝けの門出に手離れ惜しみ泣きし子らはも
おおきみの命かしこみ愛しけ眞子が手はなれ島づたいゆく
草まくら旅ゆく夫が丸寝せば家なるわれは紐とかず寝む
蘆の葉に夕霧たちて鴨が音の寒きゆうべし汝をばしぬばむ
障敢えぬ勅命にあれば悲し妹が手枕はなれ奇にかなしも
と銃後にとどまるにしろ、総ての国民がこの壮大な構想の中にあって世界史の大きな脈拍を耳にし、多少ともおもわずにいられない状態にあった。…中略…
愈々あと数十分したら日本の国土をはなれるという、ただならぬ騒ぎの中にあって、突嗟に心をとらえたものが他ならぬ萬葉集であったということは非常に意義深いことではなかろうか。ぼくは今にしてそれを惟う。つまりこの場合、最初にして最後のもの、いいかえれば究極のところに於いて萬葉は単に日本の最も古い古典であるばかりでなく、日本そのものとして働きかけたのである。このことは従軍中、萬葉が与えてくれた多くの新たな感動や啓示のうち最も重くかつ大きい事柄だったと言うことができる。
*醜の御楯:命がけで 外敵を防ぐ者。 武人が自分を卑下していう語。
堀場正夫 著『遠征と詩歌』ぐろりあ・そさえて 昭和17年刊 p.16~19
こんな具合に文章に数多くの萬葉集の歌が出て来るのだが、千二百年近く前に防人が詠んだ歌が、これから家族と別れて戦地に向かう作者の心に響いたことはよくわかる。この従軍記には萬葉集だけでなく、唐詩選の作品も良く登場する。
昨日は五里、今日は七里という激しい対激戦の日々がつづいた。折柄あわただしい江南の秋もたけなわのこととて、そうした軍に従いながら時折ポケットから取り出して読む唐詩選は別して感慨深いものがあった。戦車と空軍との猛攻に、敵が遺棄していったソヴィエト製の重砲や、自動車の散乱する血なまぐさい沿道で、杜甫の
国破れて山河在り
城春にして草木深し。
時に感じては花にも涙を濺ぎ
別れを恨んで鳥にも心を驚かす。
烽火三月に連り
家書万金に抵る。
白頭掻いて更に短く
渾に簪に勝へざらんと欲す。を読むと、彼の慟哭がとりわけ胸をえぐるように迫ってくる。元来李白のなまめかしさより杜甫の悲壮を愛好する自分ではあるが、ここでは杜甫のもつ慟哭が一層強くしかも深くひびき、国破れて山河在りの一句が単に戦のあとの自然を謳ったものでないことが、つくづく思われるのである。かつてわが蕉翁も、みちのくの旅に杖を平泉に曳いた時「三代の栄耀一睡にして」と秀衡があとを偲び「偖も義臣すぐってこの城にこもり、功名一時の叢となる。国破れて山河在り。城春にして草青みたり」と杜甫の句をかりて
夏草や兵どもが夢の跡
と弔っている。勿論それとこれとには新戦場と古戦場との相違があるが、それにしても詩句のもつ悲痛という点では、この東洋の自然人の調べは、とうてい杜甫の慟哭の深さには比ぶべくもなく、ひとしく戦いの悲劇でありながら支那と日本とはこうも異なるものかと感慨されたほどだった。南京、九江、蘇州、杭州など昔から知名な土地をはじめとして、かつて楚の荘王の覇業以来、二千五百年の歴史に重きをなした武昌さえが、今は黄鶴楼一つ残していないのである。明日が明治節という日の夕くれがた、揚子江岸壁の蛇山公園一角に佇んだ時、ぼくも年代記だけがあって歴史のない国、動乱常なく、保存の伝統のない支那の荒涼たる有様に、しみじみ「国破れて山河在り」の慟哭を味わった。
同上書 p.30~32
黄鶴楼というのは、三国時代の223年に呉の孫権によって軍事目的の物見櫓として建築され、後には主に観光目的の楼閣となったのだが、幾度も焼失と再建が繰り返され、1868年に再建されたものも1884年に太平天国の乱で焼失してしまっていた。確かにこの国は何度も戦乱を繰り返し数多くの文化財が失われてきた。この国の人々の自然や歴史ある建物を護る意識が、わが国とはかなり違うようだ。
『われら戦ふ : ナチスドイツ青年詩集』
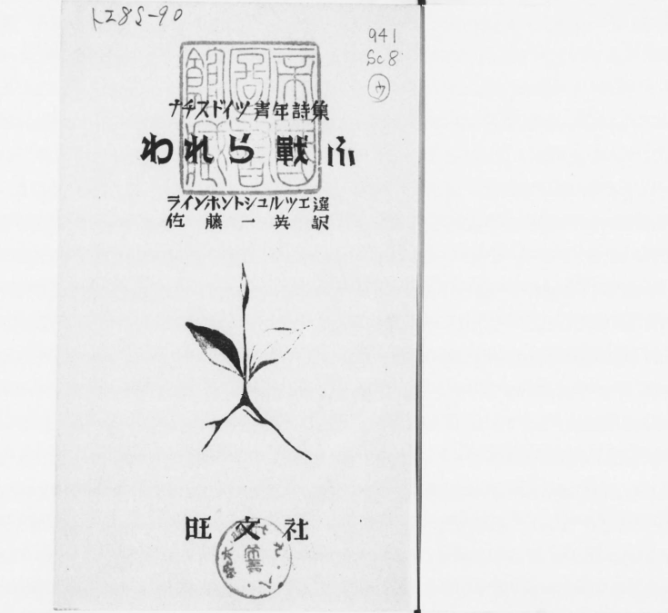
次に紹介させていただくのは『われら戦ふ : ナチスドイツ青年詩集』である。
千九百十八年の帰還
やっと還った ――― ひっそりとした軍隊だ・・・・
いちどだって破れたか! だのに心はこうも重い。
鳴らぬ太鼓と垂れた旗 ―――
森閑とした軍楽隊、げっそりした行軍だ。列はしっかりしているが ――― 何と少ない兵の数・・・・
これが最後の連隊だ ―――モーゼル谷の坂道を物言うものもあらばこそ、
やっと来た、荒れはてて知るものもない故郷に。雨は流れる鉄兜、銃や剣に・・・・
こんなさびしい行軍はまたとなかった。
もうわれらには故郷もない。
やっとこれだけ、中隊だけだ!・・・・
ラインホント・シュルシエ 著『われら戦ふ : ナチスドイツ青年詩集』旺文社 昭和17年刊 p.8~9
「いちどだって破れたか!」という言葉の意味を理解できなければ、この詩の作者が何を訴えているかを理解することは不可能だ。1918年というのはドイツが第一次世界大戦に敗れた年であるのだが、戦後のわが国では第一次世界大戦でドイツが敗れた理由について学ぶ機会はほとんど皆無であったといって良い。
この詩の解説には次のように記されている。
〔解説〕
ドイツ軍は、西部戦線では一歩も敵軍をしてドイツ国内に足を踏み入らせなかったが、長期の戦争に人は倦み、海上封鎖に基づく食糧・物資の窮乏は、戦線に銃後に、激しい不安動揺を齎して、戦いはむしろ銃後より破れて行ったのである。
1916年5月31日、6月1日両日に亘るスカゲラックの海戦以来、空しく不自由な艦上生活に時を過ごしていたドイツ海兵は、1917年の夏にも一度反乱を起こしたが、翌18年11月3日キール軍港に革命の烽火を挙げたのである。その焔はたちまちにして全国に拡まり、ドイツ帝国は倒れて、陸海の反乱軍と労働者の名によって共和制が宣言せられ、取り敢えずソヴィエトロシアにならって人民委員制が布かれることとなったのである。
かくしてドイツ軍は、11月11日遂に連合軍側の停戦条件を受諾したのである。そのうちには占領地帯よりの即時撤退という一項目が含まれ、翌十二日には既に一部の撤退が開始されたのである。四年有余にわたる戦に疲れ果てた軍隊は、黙々と故郷に向かって帰って行く。しかもその故郷は窮乏と混乱と、そして赤化の魔手に全く容を異にしたものとなっていたのである。
同上書 p.10~11
以前このブログで紹介させていただいたが、第一次世界大戦では、ドイツは武力戦で勝ち続けながら、三年目に入ってから食糧が不足して敗れてしまった。当時のドイツの食糧自給率は九割程度あったのだが、開戦と同時に食糧閉鎖を受け、さらに大凶作の為に飢餓による死亡者が七十六万人も出たと言われている。このような重要な史実が戦後の教科書や参考書には殆んど書かれておらず、マスコミが採り上げることもないことは大問題である。
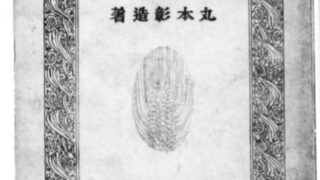
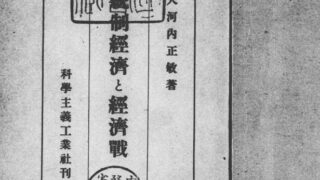
わが国の食糧自給率は四割を切り、農業従業者の高齢化が進み離農者が増えるばかりであるのだが、こんな状況でわが国が戦争に巻き込まれれば、食糧閉鎖により国民の過半が飢えることになることは確実である。武力戦で戦うためにいくら戦闘機や兵器を調えても、海上封鎖されたら戦いに敗れるしかない。農業自給率が低いことは国防上の大問題なのだが、そのことをしっかり理解している政治家、官僚、財界人が今のわが国にどれだけいるのか、心配でならない。
これまでこのブログで採り上げた、本のタイトルに「詩」を含むGHQ焚書
これまでこのブログでGHQが焚書処分した詩集について、以下の書物を採り上げている。
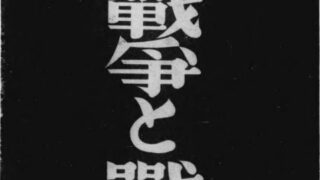
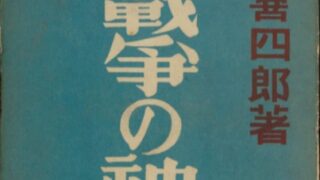
本のタイトルに「詩」を含むGHQ焚書リスト
GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルに「詩」を含む本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。
分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。
| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |
出版年 | 備考 |
| 愛国詩歌 | 井上満寿蔵 | 文化研究社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1069661 | 昭和19 | |
| 愛国詩吟物語 | 鷲尾温軒 | 牧書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1036132 | 昭和17 | |
| 愛国詩謡集 | 大本営海軍報道部 | 興亜日報社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128796 | 昭和18 | |
| 維新勤王志士国事詩歌集 | 丹 潔 | 雄生閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1028611 | 昭和15 | |
| 維新志士回天詩歌集 | 藤田徳太郎 | 金鈴社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127380 | 昭和19 | |
| 維新志士勤王詩歌評釈 | 小泉苳三 | 立命館出版部 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1265963 | 昭和13 | |
| 遠征と詩歌 | 堀場正夫 | ぐろりあ・そさえて | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1130980 | 昭和17 | 新ぐろりあ叢書 |
| 大君の詩 | 平田内蔵吉 | 山雅房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1684410 | 昭和14 | |
| 旗艦先頭 : 少年少女詩集 | 西村皎三 | 中央公論社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1869371 | 昭和17 | |
| 勤皇志士詩歌集 | 黒岩一郎 | 至文堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1718083 | 昭和18 | 青少年日本文学 |
| 弘道館記述義・回天詩史 | 小林一郎 | 平凡社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1038342 | 昭和16 | 皇国精神講座 第2輯 |
| 産業戦士詩集 われらの戦場 | 中村巳寄 編 | 高田書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128820 | 昭和18 | |
| 詩集 皇民之詩 | 森際盞武郎 | 詩洋社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1129055 | 昭和18 | |
| 詩集 此の糧 | 尾崎喜八 | 二見書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1129140 | 昭和17 | |
| 詩集 三種の神器 | 梶浦正之 | 詩文学研究会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128952 | 昭和17 | 内務省検閲発禁図書 |
| 詩集 戦闘機 | 蔵原伸二郎 | 鮎書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1129009 | 昭和18 | |
| 詩集 祖国礼拝 | 三井甲之 | 原理日本社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1226190 | 昭和2 | |
| 詩魂 第一輯 絶句編 | 鈴木一水 編 | 維新日本社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1089822 | 昭和11 | |
| 詩集 百万の祖国の兵 | 近藤 東 | 無何有書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1028403 | 昭和19 | |
| 詩集 赴戦歌 | 田中令三 | 鮎書房 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和20 | ||
| 詩集 兵魂 | 福島青史 | 軍事界社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和18 | ||
| 傷痍軍人詩集 | 寺田 弘 編 | 八重樫昊 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128848 | 昭和18 | |
| 少年愛国詩集 | 西条八十 | 大日本雄弁会講談社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1220550 | 昭和13 | |
| 職場の詩 | 中村 悳 | 増進社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1129086 | 昭和17 | |
| 正気歌と回天詩 | 菊池謙二郎 | 小川書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1882440 | 昭和18 | |
| 聖戦詩史 : 国民精神総動員 陣中読本 銃後必吟 |
四宮憲章 | 皇明会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1032881 | 昭和12 | |
| 戦魂 : 詩集 | 小田 栄 | 日本新国策研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1256060 | 昭和14 | |
| 戦線詩集 魂の突撃 | 飯塚野想 | 紙硯社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/10298342 | 昭和18 | 内務省検閲発禁図書 |
| 戦線詩集 : 附:江上日記其他 | 佐藤春夫 | 小学館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1129162 | 昭和17 | |
| 戦争詩集 | 大阪詩人倶楽部 | 大阪詩人倶楽部 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1263144 | 昭和14 | |
| 戦争と戦争 : 政治詩集 | 田中喜四郎 | 日本社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1036840 | 昭和12 | 戦争ブツクレツト ; 第1編 |
| 戦争の神々 : 政治詩集 | 田中喜四郎 | 日本社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1256048 | 昭和13 | 戦争ブツクレツト ; 第2編 |
| 大行颪 : 詩集 | 手塚 尹 | 東海出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1686380 | 昭和15 | |
| 泰国風物詩 | 宮原武雄 | 岡倉書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1272924 | 昭和17 | 新東亜風土記叢書 1 |
| 大東亜戦役詩史 | 塩谷 温 | 弘道館図書 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1900577 | 昭和19 | |
| 大東亜戦詩 | 日本文学報国会 編 | 龍吟社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1884685 | 昭和19 | |
| 大日本詩集 聖戦に歌ふ | 大日本詩人協会 編 | 欧文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128797 | 昭和17 | |
| なかつくに 肇国史詩 | 加藤一夫 | 竜宿山房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128942 | 昭和17 | |
| ナチスドイツ青年詩集 われら戦う | ラインホントシュルツェ | 旺文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1132131 | 昭和17 | |
| 日独詩盟 | 青山延敏 編 | 南山堂書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1069263 | 昭和18 | |
| 飛行詩集 翼 | 笹沢美明 編 | 東京出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128841 | 昭和19 | |
| 満支戦線 詩と随筆の旅 | 白鳥省吾 | 地平社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1884663 | 昭和18 |
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


【ブログ内検索】
大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。
前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。
全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。
電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。
またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。


コメント