今回は原口統太郎著『支那人に接する心得』の紹介の二回目である。一部しか紹介できないのは残念だが、この本は『国立国会図書館デジタルコレクション』でネット公開されているので、誰でもPC等で読むことが出来る。
惜しみなく金を撒け
前回記事では、支那人から接待を受けたり贈答を受けても返礼すらしない日本の政治家や外交官がいて国益を損ねたことを書いたが、支那ではカネをばらまかないとうまく行かないことを書いている。金銭についての考え方は日本人とは随分異なる。
支那人は金銭のことを言うのに一向頓着しない。即ち何でも金銭で解決する風がある。であるから、召使いとか下の者に対しては、機会あるごとにできるだけ金を与えることを心掛けるがよい。
例えば、支那人を訪問した時でも、その家の召使などに、玄関で外套を着せてもらった時とか、洋服の埃を払って貰った時などでも、すべてそういうような場合は、一々五銭なり、十銭なりの金をやるようにした方が宜しい。大官等を訪ねた場合でも、その家の取次に沢山な金銭をやらなければ、取り次いで貰えぬというのが、昔から支那一般の習慣である。こんなわけで、支那人はこのような場合非常に奮発して金を出す。然るに、日本人は、自分が金銭のことを言うのを、潔しとしないためか、金銭の使い方がケチだ。支那にいる間はもっと露骨に金銭を以て、物事を解決しようと考えてもちっともおかしくない。かえって、それが支那人の心を得る所以だ。
原口統太郎『支那人に接する心得』実業之日本社 昭和17年刊 p.247~248
金銭がなければ大官が動かない社会がいい社会だとは思えないが、中国は今も同様に賄賂が横行し、今年の1月10日にNHK WEB NEWSで報じられた、中国の新疆ウイグル自治区の元副書記が20年間あまりで受け取った賄賂が日本円にして177億円という金額には驚いた。地域や人物によって金額の差はあるのだろうが、同様話はあの国の各地で起こっているのだろう。
最近ではわが国で中国人から賄賂を受け取って中国人に便宜を与えるような政治家が現れた。今年の一月に週刊現代が報じたニュースだけではないのだろうが、なぜ巨額の賄賂を受け取った政治家が逮捕されないまま放置されているのか気になるところである。
支那人に支那人と言うな
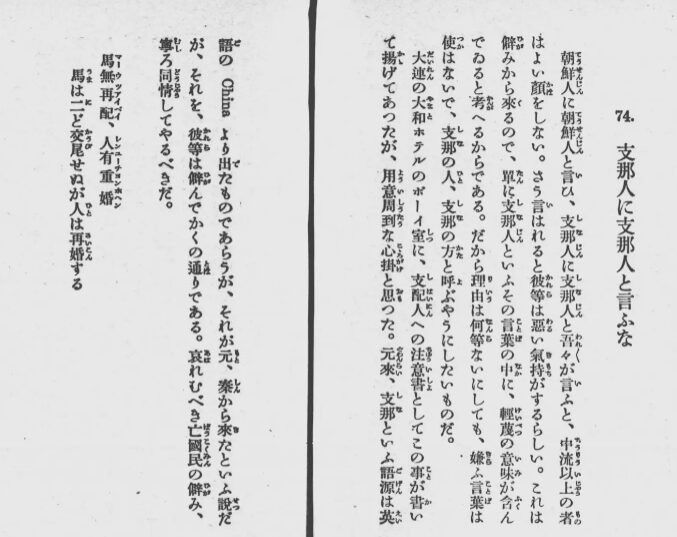
西洋人がこの国をChinaと呼ぶのは、紀元前三世紀に誕生した中国最初の統一王朝である秦が由来であるという説があり、「支那」というのはその音訳だと言われている。わが国では戦前・戦中までは「支那」と呼ぶことが普通であったのだが、戦後になると外務省から「中華民国」を用いる旨の通達が出て、「支那」という言葉はほとんど使わなくなった。しかしながら当時から中国の人々が「支那人」と呼ばれることを好まなかったと書いている。
朝鮮人に朝鮮人と言い、支那人に支那人とわれわれが言うと、中流以上の者はよい顔をしない。そう言われると彼らは悪い気持がするらしい。これは僻みから来るので、単に支那人というその言葉の中に、軽蔑の意味が含んでいると考えるからである。だから理由は何等ないにしても、嫌う言葉は使わないで、支那の人、支那の方と呼ぶようにしたいものだ。
大連の大和ホテルのボーイ室に、支配人への注意書としてこのことが書いて掲げてあったが、用意周到な心掛けと思った。元来、支那という語源は英語のChinaより出たものであろうが、それが元、秦から来たという説だが、それを、彼らは僻んでかくの通りである。哀れむべき亡国民の僻み、寧ろ同情してやるべきだ。
同上書 p.256~257
そもそも支那というのは地理的な概念だが、当時の「中華民国」は支那のごく一部を支配していたに過ぎず、わが国が支那に住む人々のことを支那人と呼んだことに問題があったとは思えないし、欧米はChinaと呼ぶことに昔も今も大きな問題にはなっていない。これはどう解釈すれば良いのだろう。
この文章の中で著者は「国民の僻み」という表現をしているのだが、この意味を理解するためには当時の「中華民国」が統一国家ではなかったことを知る必要がある。
以前このブログで松岡洋右の国際連盟脱退時の演説を採り上げたが、この演説で松岡は、支那は広大な国土を持ち多くの軍隊を持ちながら自国の防衛も国民の生命財産も守れないばかりか、諸外国から派遣された外交官を守るために、各国からの軍隊派遣が不可欠な状態にあったこと考えると、Chinaは欧米人が用いる意味での「国家」ではなく、ただ広大な地域を指しているに過ぎないと述べている。
一方わが国は欧米から先進国として認められており、そのことは支那人としては不愉快なことであり、また日本人から「支那人」と呼ばれることに僻みを持ったということも理解できるのである。
支那を比喩して散砂という
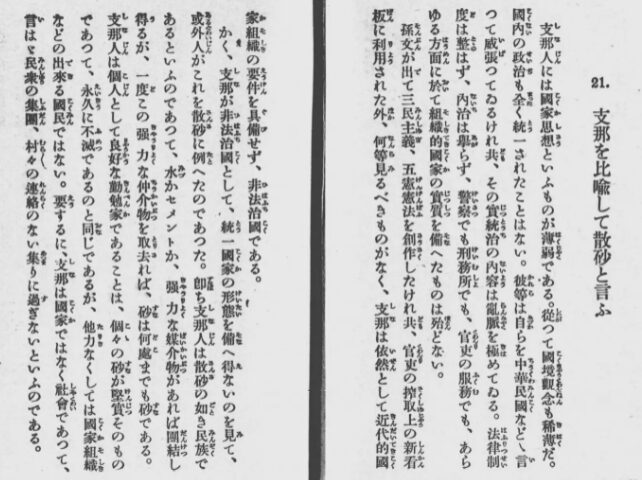
著者は当時の支那が中華民国が国家の体を為していなかったことについて次のように述べている。
支那人には国家思想というものが薄弱である。したがって国境観念も希薄だ。国内の政治も全く統一されたことはない。彼らは自らを中華民国などと言って威張っているけれども、その実統治の内容は乱脈を極めている。法律制度は整わず、内治は挙がらず、警察でも刑務所でも、官吏の服務でも、あらゆる方面に於いて組織的国家の実質を備えたものは殆んどない。
孫文が出て三民主義、五憲憲法を創作したけれども、官吏の搾取上の新看板に利用された外、何ら見るべきものがなく、支那は依然として近代的国家組織の要件を具備せず、非法治国家である。かく、支那が非法治国として、統一国家の形態を備え得ないのを見て、ある外人がこれを散砂に例えたのであった。即ち支那人は散砂の如き民族であるというのであって、水かセメントか、強力な媒介物があれば団結し得るが、一度この強力な仲介物を取り去れば、砂は何処までも砂である。支那人は古人として良好な勤勉家であることは、ここの砂が堅実そのものであって、永久は不滅であるのと同じであるが、他力なくしては国家組織等のできる国民ではない。要するに、支那は国家ではなく社会であって、言わば民衆の集団、村々の連絡のない集まりに過ぎないというのである。
同上書 p.68~69
このように原口は、松岡洋右と同様に支那は国家ではないと述べ、「民衆の集団、村々の連絡のない集まりに過ぎない」と表現し、人々が全く統制の取れていない状態にあったことを示唆している。
日本人の優越感
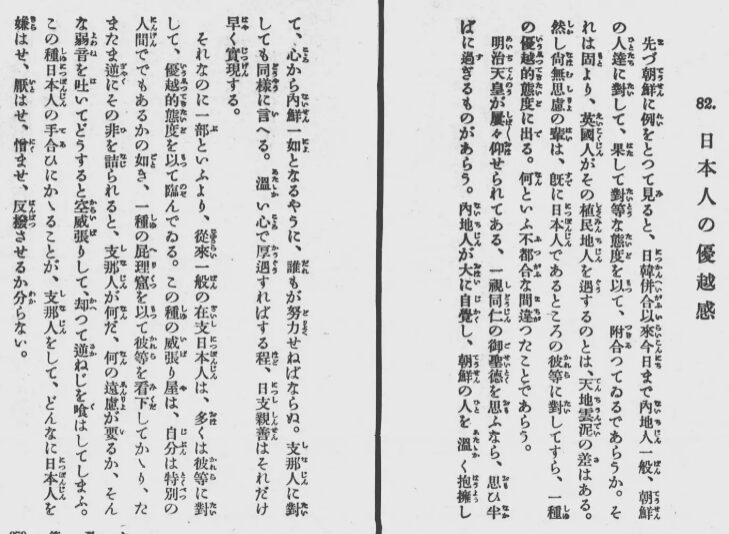
一方原口は、日本人の支那人や朝鮮人に対する接し方について苦言を呈している。
まず朝鮮に例をとってみると、日韓併合以来今日まで内地人一般、朝鮮の人たちに対して、果たして対等な態度を以て、付き合っているであろうか。それは固より、英国人がその植民地人を遇するのとは、天地雲泥の差はある。しかしなお無思慮の輩は、既に日本人であるところの彼らに対してすら、一種の優越的態度に出る。何という不都合な間違ったことであろう。
明治天皇がしばしば仰せられてある、一視同仁*の御聖徳を思うなら、重い半ばに過ぎるものがあろう。内地人が大いに自覚し、朝鮮の人を温かく抱擁して、心から内鮮一如となるように、誰もが努力せねばならぬ。支那人に対しても同様に言える。温かい心で厚遇すればする程、日支親善はそれだけ早く実現する。
*一視同仁:誰にも分け隔てなく平等に愛することそれなのに一部というより、従来一般の在支日本人は、多くは彼らに対して優越的態度を以て臨んでいる。この種の威張りや屋は、自分は特別の人間ででもあるかの如き、一種の屁理屈を以て彼らを見下してかかり、たまたま逆にその非を詰られると、支那人が何だ、何の遠慮が要るか、そんな弱音を吐いてどうすると空威張りして、かえって逆ねじを食わしてしまう。この種日本人の手合いにかかることが、支那人をして、どんなに日本人を嫌わせ、厭わせ、憎ませ、反発させるか分からない。
世界人類の皇道化と、東洋人の東洋を目標に、まず皇道を東亜に宣揚せんとするに当たって、一にも二にも戒しむべきは、この頭からの優越感と優越的態度の空威張りである。わが民族の美点ともいうべき謙抑、節制、礼儀を以て、到るところ東亜諸民族を慰撫し、彼らをしてその所を得せしめ、その歓心を買うならば、東亜の平和は招かずして、自ずから来たるのである。深く深く考うべきだ。
同上書 p.278~280
このような何も考えない輩は日本社会にもたまにいて、もちろん周囲から嫌われることになるのは同じなのだが、こういう人物が半島や支那に渡って空威張りをすると、それまで現地の人々の信頼を得るために努力していた多くの日本人の苦労が台無しになってしまう。支那や朝鮮半島の排日運動は当初英米が仕掛けたものであったのだが、その運動がどんどん拡大していったことについては、日本人側にも原因の一端があったと考えるべきであろう。
日本人と欧米人との対照
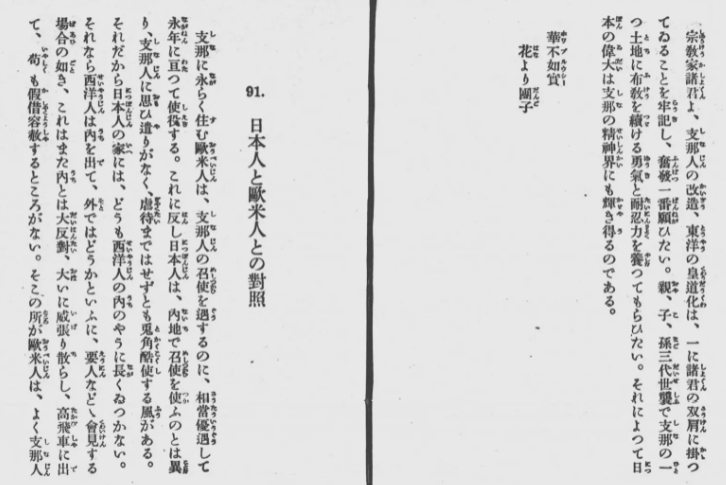
また原口は、支那人に対する接し方について、欧米人と日本人とを比較している。
支那に永らく住む欧米人は、支那人の召使を遇するのに、相当優遇して永年にわたって使役する。これに反し日本人は、内地で召使を使うのとは異なり、支那人に思いやりがなく、虐待まではせずともとかく酷使する風がある。それだから日本人の家には、どうも西洋人の家のように長くいつかない。それなら西洋人は家を出て外ではどうかというに、要人などと会見する場合の如き、これはまた家とは大反対。大いに威張り散らし、高飛車に出て、苟も仮借容赦するところがない。そのところが欧米人は、よく支那人の心を掴み、上下内外寛厳よく使い分けて、所期の目的を達し巧みに成功して来た。
さて、一方日本人となると、そこが甚だ下手だ。出る所へ出た場合、堂々たる態度を取らず、迎合的で態度駆引きが誠にまずい。その結果彼らの侮蔑を招くに止まると言いたい。この内と外とのやり方の違いを評すると、西洋人は支那人を取扱うのに内柔外剛の形となり、日本人はその反対ではなかろうか。とにかく日本人の方は上に弱く下に強い。西洋人はその反対だ。本来、日本民族はそんな筈ではなかったのだ。かの強きを挫き弱きを助けるという町奴の気風や、武士の伝統的魂は、今もなお存在するはずだ。それは決して狭い国内だけのことではなく、もっと海外にまでも至り及ぶ強力な精神内容を持つものである。
論語に「三軍もその師を奪うべし、匹夫もその志を威張宇べからず」とある。召使だって情をかけてやらねば、真の味方にはなり得ない。召使を本当によく使い得る人でなければ、百里に使いして君命を辱めず、という大丈夫の仕事は出来ないはずだ。要するに、欧米人のやり方が要領を得ているのであるから、彼らのするが如く、内に優しく外で強いという呼吸を学んでよかろう。
同上書 p.305~307
当時多くの植民地を持っていた欧米人は現地人との接し方について、やってはいけないことがわかっていたようだが、日本人の多くは支那人とどう接すればよいかが分からないまま、大陸に渡ったのであろう。
明治初期以降第二次世界大戦終戦まで中国本土や満州などで居住し活動していた日本人は少なくないのだが、支那人との接し方について著書を残したのは、『国立国会図書館デジタルコレクション』で検索して引っかかるのは原口統太郎の本書のみだと思われる。
日支親善の要諦
ところでこのような本が何故GHQによって焚書処分されたのであろうか。この本は日支親善のために記されたものだが、支那を反植民地としていた英米にとっては日支が仲良くなって接近してもらっては困ると考えたのかもしれない。
原口は、この本の最後に、日支両国の親善を阻害している主たる原因を詳説し、その原因を排除していくことが必要だと述べている。
…国力及び文化の優劣による、弱者の僻みから来る反日感情に対しては、日本が雅量、友愛、誘掖、綏撫等真に優者たる恩威を示し、日本の真の優秀点に対し、自ずから信頼の念を生ぜしむることによってその僻みを去り、反日感情を一層せしむることが出来、また弱国の強国に対する強迫観念の如きも、これに依って日本が決して領土的野心を有せず、経済的提携によって両国の共存共栄を図るものであることを十分理解せしめ得れば、自ずから氷解するはずである。
もしそれ優秀なる日本文化に対する彼らの懊悩と嫉妬、侮蔑と反感の如きに至っては、日本人が自ら省みて優越感を去り、親切なる指導誘掖によって寧ろ彼らをして日本の文化に憧憬し、日本に学び、日本人に兄事せしむべく、日本文化の真価を認識すれば自然に消滅すべきものである。…中略…
次に外国の使嗾の如き、又は支那の欧米依存の如き、畢竟世界の現勢に暗く、列国の情誼をわきまえず、東亜の大局を顧念せず、己の実力を自覚せざる等無智の致すところである。これは今後日本の指導開発によって彼等の蒙を啓くことにより、その適従を過まらしめないことが出来よう。同時に日本人自身の反省によって、…欠点を匡正しなければならない。…中略…
なお、日支両国の親善に欠くべからざることは、従来の如く支那の支配階級とのみの親善ではなくて、一般の国民即ち「百姓」との親善を心掛くべきことである。支那の一般国民は自己の生活さえ脅かされざる限り、如何なる異民族とも親和し得る国民である。単なる支配階級との政治的外交的親善は畢竟形式的表面的のものである。古人のいわゆる民を得るは国を得る所以なることを忘れてはいけない。
同上書 p.339~342
支那に進出した日本人の多くは支那の支配階級との親善を図ろうとしたが、原口は一般の国民との親善を心がけるべきだと書いている。はじめから一般大衆との親善をはかっていれば英米が仕掛けた反日運動はうまく行かず、両国の良好な関係を続けることが出来たのかもしれない。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


【ブログ内検索】
大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。
前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。
全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。
電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。
またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。



コメント