GHQ焚書リストの中には日本人の生きる姿勢や心構えに関する書籍が少なからず存在する。前々回及び前回に「武士道」及び「武道」に関するGHQ焚書を採り上げたが、今回は「臣道」(臣民の道)に関するGHQ焚書を紹介させていただくことにしたい。
「臣道」(臣民の道)という言葉は今ではほとんど用いられなくなっているのだが、一言で言えば「臣下としてあるべき心構え」という意味である。どうしてこのような本をGHQが焚書にしたかと考えながら何冊かを拾い読みすると、GHQが嫌がりそうな文章を結構見つけることが出来る。
『臣道読本』
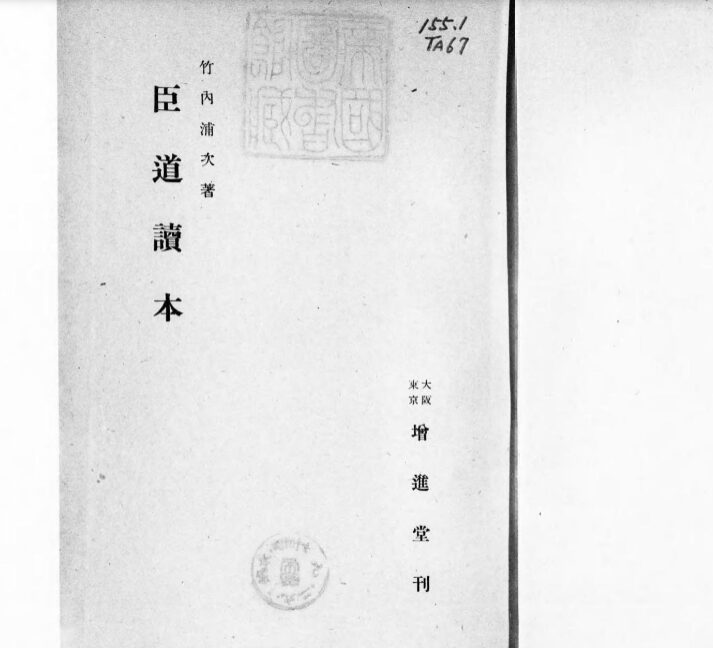
最初に紹介するのは、竹内浦次 著『臣道読本』。たとえば英国の紳士道、あるいはキリスト教精神というものがいかなるものであるかについて述べている部分がある。
…過去の精神文化を誇ったアジア民族は、科学と武力と財力とを背景とする狡猾なる欧米人に、政治的に、経済的に、思想的に征服せられて、日本を除いてはほとんど奴隷化され、植民地化されてしまいました。
極端なる差別感を抱く欧米人は「神は我らに世界を支配する権利を賜う」と宣言し、「アジア人は、我らの文化を信奉することによって幸福となる。彼らは元来奴隷的人種で、我らに征服されるように出来ている」と叫び、「スエズ以東に人道なし」の信念を平気で実行して来たのでありました。その標本がインドです。インド人の九割七分は文盲です。平均年齢二十三歳(英人四十五歳)、平均一日収入十六銭(英人二円六十銭)、彼等の半数は半年間は乞食になる。ちょっとの飢饉で何百万人が餓死しても、英人は平気で毎年二十五億の金を絞り上げる。三億五千万のインド人が二千三百の階級に分かれ、二百六十余種の言葉を使い、ヒンズー教、回教、仏教、キリスト教、ジェーン教、シーク教、バルゼン教、ユダヤ教の各派に分かれ、互いに嫉視反目して、争い続ける。
英国は、それを助長し利用して、ますます彼等を奈落の底に落として行く。総督の年収百万円、世界一に富強を誇り紳士国と号する英国が、百五十年の統治により、ある深遠な哲学や仏教を生んだインド民族を、世界一の貧乏人、世界一の無学者、世界一の意気地なしにしてしまった。
これが英国の紳士道であり、キリスト精神であり、国際正義であったのだ。
この点は仏印*もビルマ**も、東インド諸島***も大同小異であったようだ。
いずれも九十パーセント以上が文盲で、皆怠け者、骨なし者にされてしまった。
*仏印:現在のベトナム、ラオス、カンボジア(フランス領) **ビルマ:現ミャンマー(イギリス領)
***東インド諸島:現インドネシア、マレーシアのマラッカ州
竹内浦次 著『臣道読本』増進堂 昭和17年刊 p.172~173
イギリスのインド統治が如何に酷いものであったかについて書かれた書籍の多くがGHQに焚書処分されてしまったために、戦後生まれの日本人はほとんど何も知らされておらず、私も学生時代はイギリスは紳士の国だと思っていた。イギリスの植民地統治の真実を詳しく知ったのは十年少し前のことだが、「国立国会図書館デジタルコレクション」が無ければ、この分野の詳しい本を読む機会を得ることはなかったと思われる。
このような酷い植民地統治はイギリスだけではなく、フランスもオランダもアメリカもよく似たものであったのだが、戦後のわが国では学校やマスコミによる洗脳のために、ひどい植民地統治をしたのはわが国の方で、欧米諸国は現地人に文明を伝えたかのようなイメージを持っている人が多いのが現状である。


続いて『臣道読本』に、英米人と日本人とでは与えられた仕事や役割に対する責任感の強さが異なることについて述べている部分を紹介したい。
日本人の不思議な道徳的情操の一つに、徹底した責任感があります。
英米人の責任感は法律的であり、進んだ者も道徳的に止まります、
マレーやフィリピンの戦線で、住民弊を第一線に押し立て、自分達は後方にかくれて督戦*するのは、責任を最小限度にとらんとす民族的利己心、即ち法律的責任感から来るので、これを「いやしくも免れて恥なし」と申します。
*督戦:後方にいて前線の軍を監視し、逃亡・投降しようとする兵を攻撃して戦闘を強制すること
「バターン半島で最後まで反抗し、力尽きて降伏したのは、人間として最善をつくしたもので、われは名誉ある捕虜なり」と考えるのは、彼等の道徳的責任感であります。
死なぬ範囲で責任を果たす、不可抗力には責任を負わぬ、尻に帆をかけて逃げ出したマッカーサーをさえ英雄扱いするのが、米英の責任感であります。日本人の責任感は宗教的です。超理屈、超打算です。
神武日本に不可抗力はない。愚かなる心にも誠をつくせば、必ず天佑神助がある。祖霊の御助けがある。
その御助けを受けられない時は「武運が拙い」と反省する。
頼三樹三郎が国事に奔走したため、幕府の弾圧を受け、罪無くして刑死する時に
「わが罪は 君が代おもうまごころの 深からざりししるしなりけり」
と詠じ、一言の不平を述べず、足らざるを自ら責めつつ、従容死についたのは武士道的責任感によるものであります。
同上書 p.200~201
以前このブログで紹介させていただいた 西川佳雄著『比島従軍記』(GHQ焚書)に、米兵は常にフィリピン兵を戦場の最前線に立たせて自分たちは安全な後方にひきさがり、フィリピン兵の背後から銃口を突き付けて督戦していたことや、両足が鎖につながれて身動きできないように縛り付けられて、ひたすら機関銃を撃ち続けるフィリピン兵もいたという。
以前このブログで書いた通り、コレヒドール要塞が陥落後十分な武器や食糧を残していながら、大量の米兵が投降してきたのだが、日本軍ならこんなに簡単に降伏することは考えにくい。


督戦隊が存在した点については支那も同様で、同じ漢人でありながら最前線の兵たちは常に後方の督戦隊に監視されていて、もし逃亡しようとすれば督戦隊に銃撃されることを覚悟しなければならなかった。ところが、日本兵の場合には督戦隊の必要はなく、兵士各自が最期まで任務を全うしようと動くのである。竹内は「徹底した責任感」と述べているが、日本軍が死を怖れずに戦い抜こうとする姿勢に、戦勝国が怖れたことは言うまでもないだろう。
日本人の責任感の強さは戦後も同様で、かつては自分の責任で大きな失敗をして社会に迷惑をかけた際に、その責任を取って自殺したという類の話が新聞などで良く報道された。昨今では業務上の責任を取って自殺したという話をほとんど聞かなくなったが、それでも自分の仕事や役割はしっかり果たそうと努力する日本人が多いことは昔も今も変わらない。
『日本臣道の本義』
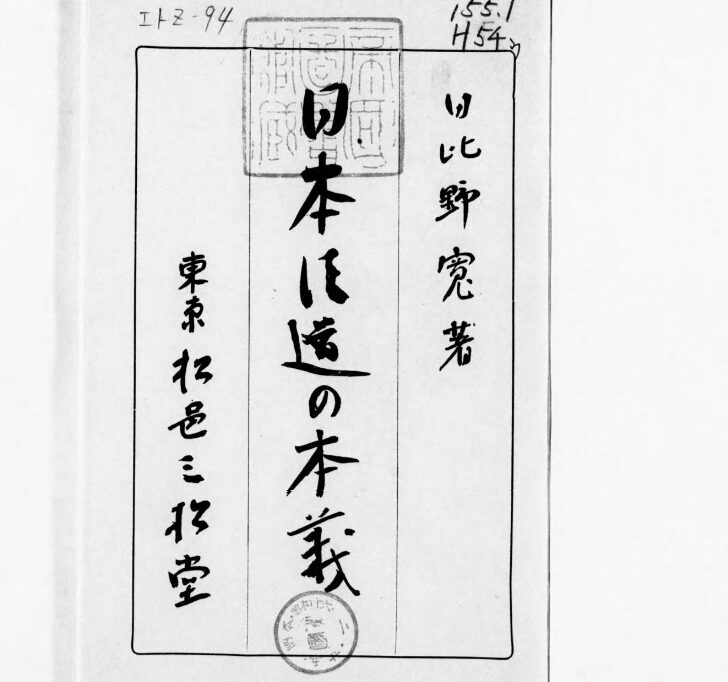
では、なぜ日本人の責任感は他国人と比べて相対的に強いのであろうか。この点を突き詰めていくと、日本人の生き方や考え方に関わって来ることになる。
大日本帝国憲法第一条には「大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」、とあり第三条には「天皇は神聖にして侵すべからず」と書かれているが、皇位が神聖であり永遠に続くことは憲法によってはじめて定められたわけではなく、太古から日本人に理解されている天皇を条文に示したものである。君臣の関係については「忠」、すなわち裏表のない態度で、誠意をもって仕える関係と理解されていて、世の為人の為になることをすることが「忠」につながると普通に考えられていたのである。
戦後の教育や左翼マスコミの影響のためにその点については相当崩されてしまった感があるのだが、為政者と国民との関係については他国とは全く異なっている。日比野寛 著『日本臣道の本義』には次のように記されている。
かく我が皇位の絶対性と、臣道即ち忠の絶対性とは、全世界に於いて、ただ独り我が国にのみ見ることの出来る特殊の事情である。
支那に於いては、君もし君たらずんば、臣は臣たるの必要ない。君が君として立つに於いて、臣は始めて臣たるの道を履むであろう。即ち、報恩感謝の意味の忠ならば為そう。君がもし無動にして、君として立つ資格を欠いたならば、我は君の恩恵を蒙らぬゆえ恩に報いる所もない。故に我もまた、君を君として戴かないであろう。
暴虐無動の桀たり紂たる*が如きことがあれば、一日も王位にしてはならぬ。というのが支那は勿論世界各国の思想である。即ち支那などでは君と臣とは相互的なもであり、交換的なものであるという観念の上に立っている。即ち君の善政を受ける時は報恩的に之に誠を致し、君が政道を失えば臣はむしろ新しい主権者を欲する。わが国の絶対に対して、彼は相対である。われ等の天皇に対する観念と、彼等の王者に対する観念とは全然相違している。彼のこの相対観念は、孝を百行の本とするところの民衆を基礎とした立国事情から生まれてきたものである。天皇の降下君臨によって肇国せられたるわが国とは、全く思想が異なり、そしてわが国では忠は百行の本なりとすべきである。
*桀、紂: いずれも暴君の代名詞で、夏の桀王は天乙に滅ぼされ、殷の紂王は周の武王に滅ぼされた人と人と相食み、種族と種族と相伐ち、社会と社会と相争って、そこに国を建てて、一人の優越者が自ら帝王と称するようになった国に於いては、君君たらずんば、臣臣たらざるのは怪しむに足らない。身を修めることによって、よく衆望を担い、民衆から王者として選ばれた者でも、それが一旦桀となり紂となって、君の資格を欠くに至れば、忽ち王位を奪われることは、むしろ当然のことである。これらはすべてわが皇国と、根本に於いて成立の事情を異にするからである。しかるに、わが国にも忠を相対的と誤り、忠は君の恩に報いることなりとの謬見を抱く者がないでもない。我と彼とは、その国家組織の上に於いて、根本的相違のあることを、明確に意識しなければならぬ。
我が肇国は他に類例なき上に成就されたものである。皇位の絶対性はわれ等の永遠に抜くべからざる信仰である。この信仰が、即ち忠であって、忠は、当然絶対性をもつものである。これ忠が日本臣道の源泉であり、われ等の生活の一切を支配し包括する根元たる所以である。而して忠が百行の本であり、大義の前には何ものもない所以も、実にここに存するのである。
日比野寛 著『日本臣道の本義』松邑三松堂 昭和16年刊 p.46~48
為政者に実力があり人望もある人物であれば、臣民たちは為政者に忠誠を誓うであろうが、為政者にその実力が無かったり、夏の桀王や殷の紂王のような暴君である場合は臣民が王から離れていき、いずれ滅ぼされる運命にあるのは支那に限らずどこの国でも同様であろう。しかしながら、わが国においては例外的に、臣民の天皇に対する忠誠心が揺るがずに続いてきた。わが国では国家は一つの大きな家のようなものであり、皇室は日本人の宗家の如く考えられてきたといって良い。
『臣民の道』
「臣道」とほぼ同義だと思うのだが「臣民の道」という言葉も良く用いられていたようである。
文部省教学局が昭和十六年に編纂し刊行した『臣民の道』という本がGHQによって焚書処分されている。
この本は欧米の個人主義的思想を否定し、国体の尊厳と忠君愛国精神を説く内容となっているが、近世史以降の世界の動きやこの難局をどう対処すべきかについて、当時の政府が国民に対してどのように解説していたかを知る意味で、一読の価値はある。また、同書については解説書がいくつも出ており、その多くが同様にGHQによって焚書処分されていることも注目点である。
『臣民の道』で近世史以降に欧米が何をしたかについて述べている部分を引用させていただく。
近世史は一言にしていえば、欧州に於ける統一国家の形成と、これらの間に於ける植民地獲得のための争覇戦との展開である。即ち近世初期にアメリカ大陸が発見せられ、それに引き続いて欧州諸国民は支那・インド等の遥かなる東亜の地へも、大洋の波を凌いで盛んに来航することとなった。而してその全世界への進出は、やがて政治的・経済的・文化的に世界を支配する端緒となり、彼らは世界をさながら自己のものの如く見なし、傍若無人の行動を当然のことのように考えるに至った。
この侵略を欧州以外の諸国はただ深い眠りの中に迎えた。南北アメリカもアフリカも、オーストラリヤも印度も、武力を背景とする強圧と、宗教を手段とする巧妙なる政策とによって、瞬く間に彼らの手中に帰した。阿片戦争によってその弱体を暴露した支那もまた、忽ちにして彼らの蚕食の地と化するに及んだ。我が国は、室町時代末より安土桃山時代にかけて、先ずポルトガル・イスパニア等の来航に接し、後に鎖国政策によって一時の静安を得たけれども、幕末に至りイギリス・フランス・アメリカ・ロシヤ等の来航漸く繁きに会し、神州の地もまた安からざるものがあった。
元来欧州諸国民の世界進出は冒険的興味の伴ったものであったとはいえ、主として飽くなき物質的欲望に導かれたものである。彼らは先住民を殺戮し、或いはこれを奴隷とし、その地を奪って植民地となし、天与の資源は挙げて本国に持ち返り、或いは交易によつて巨利を博した。されば彼らの侵略は世界の至る所に於いて天人共に許さざる暴挙を敢えてし、悲慘事を繰り返したのである。
アメリカ・インディアンはいかなる取り扱いを受けたか。アフリカの黒人は如何。彼らは白人の奴隷として狩り集められ、アメリカ大陸に於いて牛馬同様の労役に従事せしめられたのである。このことは大東亜共栄圏内に於ける諸地方の被征服過程と現状とに就いて見ても、思い半ばに過ぎざるものがあらう。
而して西暦十八世紀末より十九世紀にかけての欧州に於ける産業革命は、彼等の世界支配の勢いを劃期的に飛躍せしめたことはいうまでもない。機械の発明による工業の発達は、夥しい原料を要求すると共に、その莫大な製品を売り捌く海外市場を必要とした。彼らは愈々盛んに原料の獲得と製品のはけ口とを植民地に求めた。やがて勢いの趨くところ、彼ら同志の間に熾烈なる植民地争奪や貿易競争が起こり、かくして弱肉強食の戦いを繰り返したのである。近世に於けるイスパニヤ・ポルトガル・オランダ・イギリス・フランス等の間の戦争や勢力消長史は、海外侵略と密接な関係のないものはない。かかる弱肉強食的世界情勢の形成は、やがてその矛盾を拡大し、ついに西暦1914年の世界大戦の勃興を見ることとなった。
文部省教学局編『臣民の道』内閣印刷局 昭和16年刊 p.3~6
当時の日本人の多くがこのような世界情勢認識を持ち、わが国が攻撃される危機意識を共有していたことを理解せずして、第二次世界大戦は語れないと思う。戦後の学校教育もマスコミの解説も戦勝国史観に立つ状態が続いているのだが、政府やマスコミがこの歴史観を黙って中立的なものに変えることは期待できない。国民の多くが正しい歴史を自ら学んで洗脳を脱出し、政府に圧力をかけるぐらいでないと何も変わらないのではないだろうか。
臣道に関するGHQ焚書リスト
GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルに「臣道」あるいは「臣」を含む本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。
分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。
| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |
出版年 | 備考 |
| 学童の臣民感覚 | 東井義雄 | 日本放送出版会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1139090 | 昭和19 | |
| 教育勅語と臣民之道 | 井上清純 | 冨山房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039425 | 昭和18 | |
| 教本臣道の民 | 阿部仁三 | 目黒書店 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和16 | ||
| 皇国臣民の責務 | 中岡弥高 | 清水宣雄 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1216963 | 昭和15 | 戦争文化叢書 ; 第24輯 |
| 皇道原理と絶対臣道 | 田崎仁義 | 甲文堂書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039528 | 昭和18 | |
| 国体明徴と臣民の正念 | 石川金吾 | 日本精神宣昭会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1224087 | 昭和10 | |
| 国防国家と臣道実践 | 木島一光 | 大東出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1682978 | 昭和16 | |
| 実践する臣民の道 | 野依秀市 | 秀文閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1908032 | 昭和16 | |
| 詳解臣民の道 | 岡田怡川 | 興亜日本社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和16 | ||
| 臣格錬成の新国史教育 : 修正教科書に準拠せる |
中野八十八 | 伊藤文信堂 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1457136 | 昭和15 | |
| 臣道実践皇道読本 | 日本青年教育会編 | 日本青年教育会 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和18 | ||
| 臣道実践と農村婦人の立場 | 紀平正美 | 柴山教育出版社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039429 | 昭和19 | |
| 臣道読本 | 佐々木一二 | 三鈴社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1034058 | 昭和18 | |
| 臣道読本 | 竹内浦次 | 増進社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039455 | 昭和17 | |
| 臣道・武教小学 | 小林一郎 | 平凡社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1038338 | 昭和16 | 皇国精神講座. 第1輯 |
| 神道・仏道・皇道・臣道 を聖徳太子十七条憲法によりて語る |
暁烏敏 | 香草舎 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1111202 | 昭和12 | 北安田パンフレット ; 第47 |
| 臣民道の本義 | 牧野 秀 | 修養団 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1211768 | 昭和7 | |
| 臣民道を行く | 暁烏敏 | 一生堂書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039412 | 昭和17 | |
| 臣民の道 | 高阪太郎 | 東世社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和16 | ||
| 臣民の道 | 久松潜一 志田延義 |
朝日新聞社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和16 | ||
| 臣民の道 | 文部省教学局 編 | 印刷局 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1914030 | 昭和16 | 呉PASS出版で復刻 |
| 臣民の道 : 精解 | 三浦藤作 | 東洋図書 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039436 | 昭和17 | |
| 臣民の道精義 | 佐伯有義 | 広文堂 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039446 | 昭和16 | |
| 臣民の道精解 | 勝俣久作 | 右文書院 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和16 | ||
| 臣民の道精解 | 高山林太郎 | 湯川弘文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039454 | 昭和17 | |
| 臣民の道精義 改訂版 | 森吉左衛門 | 健文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039437 | 昭和17 | |
| 臣民の道精講 戦陣訓精講 | 大串兎代夫 | 欧文社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和16 | ||
| 臣民の道全釈 | 木下忠明 阿部喜三男 |
加藤中道館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1106923 | 昭和16 | |
| 臣民の道通義 | 紀平正美 編 | 皇國青年教育協會 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1899811 | 昭和17 | |
| 臣民の道通釈 | 小西重直 高橋俊乗 共 |
富山房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039431 | 昭和17 | |
| 臣民の道(点字版) | 文部省 編 | 大阪毎日新聞社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和17 | ||
| 臣民の道の実践 | 興亜教育研究会 編 | 目黒書店 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和18 | ||
| 臣民錬成の教育 :国防体制の学校経営 |
高田師範学校附属 国民学校 編 |
教育実際社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1440014 | 昭和16 | |
| 註解 臣民の道 | 文部省教学局 編 | 鉄道青年会 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |
昭和16 | ||
| 日本臣格の錬成 | 枩田輿惣之助 | 教育研究会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1025446 | 昭和18 | |
| 日本臣道史 | 小関尚志 | 刀江書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039509 | 昭和16 | |
| 日本臣道の本義 | 日比野寛 | 松邑三松堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039420 | 昭和16 | |
| 日本臣道論 | 森 清人 | 富士書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039438 | 昭和16 | |
| 日本臣道わが中心 報効篇 第一輯 |
小谷文済 | 大日本臣道会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1094004 | 昭和14 | |
| 日本の臣道・アメリカの国民性 | 和辻哲郎 | 筑摩書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1039409 | 昭和19 | Kindle版あり |
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。
↓ ↓


【ブログ内検索】
大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。
前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。
全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。
電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。
またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。
内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。


コメント
臣道というものがあるとは知りませんでした。それにしても英国は、この他にもアヘンだとかパレスチナ問題だとか、卑怯というか、狡猾な国だと思いました。
私もこの言葉を知りませんでした。辞書には出ていますが、戦後は殆んど死語になっていますね。
イギリスは調べれば調べるほどひどい国ですね。私の子供の頃は、テレビのアナウンサーが「イギリスはジェントルマンの国」などと呼んでいたのをよく覚えていますが、それ以来長い期間いい国であると思い込んでいました。
マスコミは昔から洗脳装置ですね。